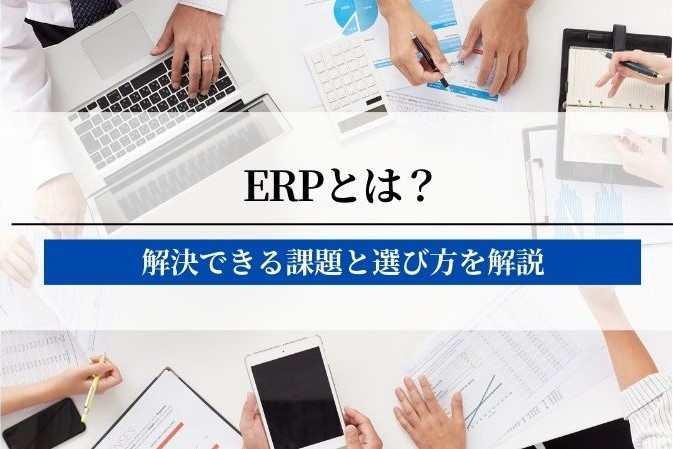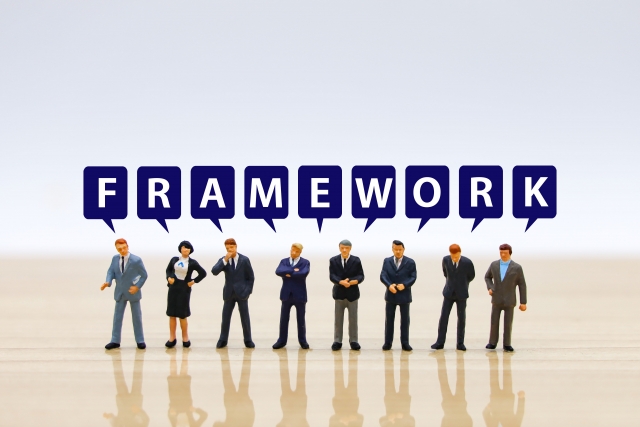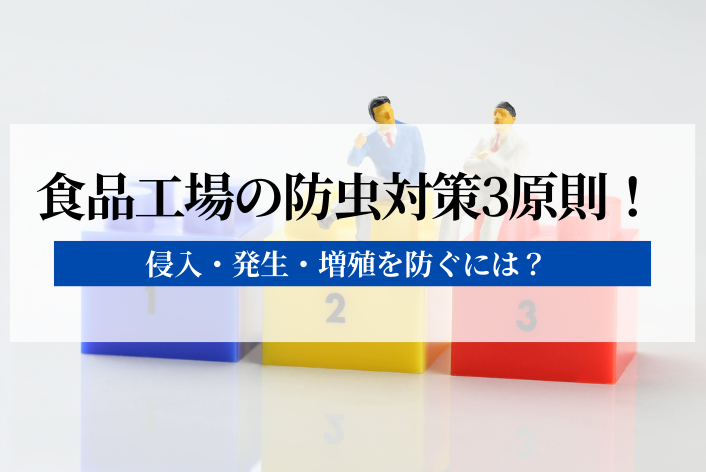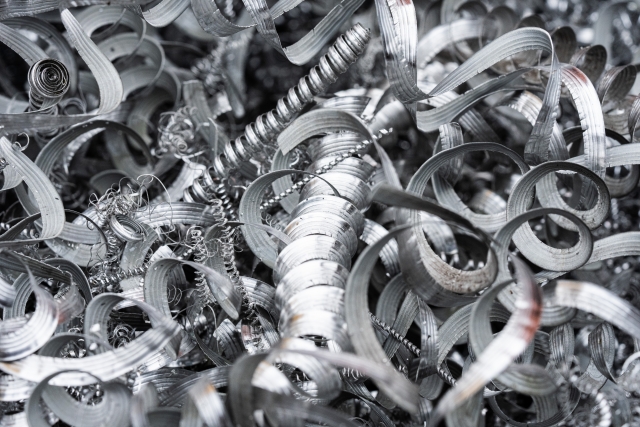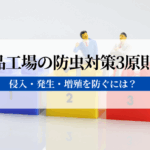HACCP 7原則12手順で守る「食の安全」!

食品を安全に届けるための仕組みとして国際的に普及しているのがHACCPという衛生管理手法です。
日本でも2021年からすべての食品事業者に導入が義務付けられ、衛生管理の基準として広く活用されています。
製造工程で起こり得るリスクを事前に見つけ、重要なポイントを継続的に管理することで、食中毒や異物混入などのトラブルを未然に防げます。
この記事では、HACCP制度の基礎から「7原則12手順」の具体的な進め方をわかりやすく解説します。
HACCPの基礎知識
HACCPとは?
HACCP(ハサップ)は、Hazard(危害)、Analysis(分析)、Critical(重要)、Control(管理)、Point(点)の頭文字を取った略称で、食品の安全を守るための国際的な衛生管理手法です。
食品の製造工程において、異物混入や食中毒菌の繁殖といったリスクを事前に洗い出し、それらを防止・低減するために重要なポイントを定めています。
この手法はもともと、アメリカで宇宙食の安全性を確保する目的で開発されたものです。
その後、国連のFAO(食糧農業機関)およびWHO(世界保健機関)が設置したCodex委員会によって国際基準として策定されました。
現在では世界中の食品安全管理の指針として広く採用されています。
従来の衛生管理との違い
HACCPと従来の衛生管理の大きな違いは、「事後対応」か「予防管理」かという点です。
従来は製品が完成したあとに一部を検査する方式が主流でした。
しかし、それでは不良品の出荷を完全には防げません。
HACCPは、製造過程の中でリスクが発生しそうなポイントを特定し、そこで集中的に監視・管理を行います。
これにより、問題の早期発見や再発防止が可能になります。
日本におけるHACCPの義務化
日本では、2021年6月からHACCPに沿った衛生管理の導入が、すべての食品等事業者に義務付けられました。
これは、2018年の食品衛生法改正によって決定されたもので、国際基準との整合性を図り、国内外における食品の安全性を高めることが目的です。
義務化に至った背景には、食のグローバル化と相次ぐ食品事故があります。
輸出入の拡大に伴い、日本の衛生管理も国際水準であるCodex規格に対応する必要がありました。
また、過去に発生した集団食中毒事件を教訓に、事後対応型の衛生管理から、予防型のHACCPへの転換が求められたのです。
事業者はその規模や業態に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかを導入します。
この仕組みにより、小規模事業者でも段階的に衛生管理を強化しやすくなっており、食品の安全性向上と消費者の信頼獲得が期待されています。
HACCP 7原則12手順の全体像
HACCPの仕組みは、7つの原則と12の手順で構成されています。
最初の5手順は計画を立てるための「準備ステップ」、後半の7手順が実際の運用に関わる「管理ステップ」にあたります。
ここでは、各ステップで何をするのかをわかりやすく解説していきます。
【手順1】HACCPチームを作る
まずは、HACCPの取り組みを推進するためのチームを編成します。
製造、品質管理、設備、物流など、各工程に詳しいメンバーで構成するのが基本です。
HACCPに関する専門的な知識がない場合は、外部の専門家を加えることも効果的です。
【手順2】製品説明書を作る
HACCPの基本資料となるのが製品説明書です。
原材料、添加物、保存方法、消費期限、使用条件などを明記し、リスク分析の基礎情報とします。
特に加熱の有無や保存温度などは、以降の手順で重要な判断材料となるため、正確な情報が求められます。
【手順3】用途と対象者を確認する
製品がどのように使用されるか、誰に向けて提供されるかを明確にします。
例えば「そのまま食べる」「加熱して食べる」など、使用方法の違いによってリスクの程度が変わります。
高齢者や子どもが対象であれば、より厳密な管理が必要です。
【手順4】製造工程一覧図を作る
製造工程を時系列でまとめた「製造工程一覧図」を作成します。
原材料の受入れから最終製品の出荷までの流れを整理し、作業内容、使用設備、温度や時間などの条件も含めて視覚化します。
この図が危害要因分析のベースとなるため、正確性が求められます。
【手順5】製造工程一覧図を現場で確認する
作成した工程図が、実際の現場と一致しているかをチェックします。
作業者の動きや設備の使われ方を確認しながら図面と照らし合わせ、必要に応じて図を修正します。
このステップは抜け漏れのない工程管理のために重要です。
【手順6-原則1】危害要因を分析する
ここからがHACCPの核心である「7原則」のスタートです。
最初のステップは、すべての製造工程において発生する可能性のある危害要因を分析することです。
この危害要因は以下の3つに分類されます。
・生物的危害:食中毒菌、ウイルス、カビ、寄生虫など
・化学的危害:残留農薬、アレルゲン、洗剤や金属などの化学物質
・物理的危害:ガラス片、金属片、毛髪、虫などの異物
分析では、手順4で作成した製造工程図を基に、各工程ごとに危害要因を洗い出します。
そして、それらの要因が実際に発生する可能性と、発生した場合の深刻度を評価し、HACCPの対象とするべき重要な危害を絞り込みます。
この工程はHACCP全体の精度を左右するため、チーム全体で慎重に進めましょう。
【手順7-原則2】重要管理点(CCP)を見つける
分析結果を踏まえ、リスクが高く、確実に抑制する必要がある工程を「重要管理点(CCP)」として特定します。
CCPとは、特定の危害要因を制御するために必ず管理すべき工程を指します。
具体例としては、以下のような工程が該当します。
・加熱処理:食中毒菌を死滅させる
・冷却工程:菌の増殖を防ぐ
・金属探知機の使用:異物混入の検出と除去
CCPの選定には、Codexの意思決定ツリーや過去の事故事例なども参考にしながら、科学的な根拠に基づいた判断が求められます。
不適切なCCPの選定は、HACCP全体の信頼性を損なう恐れがあるため、慎重な検討が必要です。
【手順8-原則3】管理基準(CLI)を設定する
各CCPに対して、その工程が適切に機能しているかどうかを判断するための「管理基準(CL:Critical Limit)」を設定します。
CLは、温度、時間、pH、水分活性など、数値化可能なパラメータで明確に規定します。
例えば、加熱処理のCLは「75℃以上で1分間加熱」など、科学的な根拠に基づくものが求められます。
また、CLはあくまで合否のラインであり、逸脱が確認された場合は直ちに是正措置を講じなければなりません。
設定には、法令基準、業界ガイドライン、過去のデータなどを活用し、
現場で確実に守れる、かつ安全性が担保される値を定めることが重要です。
【手順9-原則4】モニタリング方法を決める
モニタリングとは、CCPが管理基準を満たしているかを継続的に確認する作業です。
日常的な点検により、問題が起こる前に兆候を察知し、速やかに対応できる体制を整えることが目的です。
モニタリング計画では、以下の内容を明確にします。
・何をチェックするのか(例:温度、時間)
・誰が行うのか(担当者)
・どのように記録するのか(記録様式)
・どれくらいの頻度で行うのか(間隔)
なお、モニタリングは実行性と正確性が鍵となります。
設備の自動化やデジタル記録ツールを活用することで、人為的ミスを減らし、より信頼性の高い運用が可能になります。
【手順10-原則5】不具合があれば改善措置で是正する
モニタリングで管理基準の逸脱が確認された場合、ただちに「改善措置(是正措置)」を実施する必要があります。
これは、逸脱の影響を最小限に抑え、製品の安全性を確保するための行動です。
改善措置には以下のような対応が含まれます。
・不適合製品の隔離、再加工または廃棄
・問題のあった工程の修正
・原因の分析と再発防止策の実施
誰が、どのように、どのタイミングで対応するかをあらかじめ定めておくことで、緊急時にも慌てず適切な対応が可能となります。
また、すべての改善措置は記録に残すことが求められます。
【手順11-原則6】定期的に検証する
HACCPプランが現場で正しく実施され、想定どおりに機能しているかどうかを定期的に確認することが「検証」です。
検証には、内部監査や記録の確認、計測機器の校正、抜き取り検査などが含まれます。
検証は、以下の2つの目的で行われます。
・HACCPプランの有効性の確認
・現場でのルール遵守状況の確認
検証結果によっては、管理基準やモニタリング方法の見直しが必要になることもあります。
HACCPは「作って終わり」ではなく、運用しながら改善を繰り返す仕組みであるため、定期的な検証は欠かせないプロセスとなります。
【手順12-原則7】記録を文書化して保存する
最後のステップは、HACCPのすべての活動を記録し、それらを文書として保存することです。
記録には、モニタリング結果、是正措置、検証内容、教育訓練の履歴などが含まれます。
記録は以下の役割を果たします。
・食品安全管理の「証拠」としての機能
・トラブル時の原因追跡
・監査・検査時の提出資料
紙の帳票による運用に加え、最近ではデジタル記録の導入が進んでおり、クラウド保存やグラフ表示によるデータ分析も可能です。
記録の精度と保存期間にも配慮し、信頼性ある運用を心がけましょう。
HACCP導入による3つのメリット
メリット1:食品事故の予防
HACCPは、「起こってから対応する」従来の衛生管理とは異なり、「起こる前に防ぐ」ことを目的とした予防型の衛生管理システムです。
製造工程の各段階で潜在的なリスクを洗い出し、あらかじめ対策を講じることで、食品事故の発生を未然に防ぎます。
例えば、加熱工程では中心温度が十分に上がっているかを継続的に記録し、冷却工程では適切な温度で迅速に冷却されているかを確認します。
これにより、食中毒菌の繁殖や異物混入といったリスクを抑えることが可能です。
さらに、従来の抜き取り検査では見逃されていた製品の異常や工程の変化も、HACCPの運用により迅速に検知できます。
このように、継続的な監視体制と記録の積み重ねによって、企業は常に「安全な製品」を出荷できる状態を保つことができるのです。
メリット2:従業員の衛生意識が高まる
HACCPの導入には、現場の従業員が手順を理解し、日々の管理に主体的に取り組むことが求められます。
そのため、自然と食の安全に対する意識や責任感が育まれ、現場全体の衛生意識向上にもつながります。
また、定期的な教育訓練を通じて、衛生管理の知識やスキルが習得され、従業員のスキルアップにも貢献します。
衛生的な職場環境が維持されることで、従業員自身の安全意識も強化されます。
その結果ミスや事故の発生率を大幅に低減する効果が期待できます。
メリット3:トラブル発生時に迅速対応できる
万が一、製品に異常や問題が発生しても、HACCPの運用により迅速な対応が可能です。
モニタリング記録や工程データが整備されているため、どの工程で問題が発生したのかをすぐに特定できます。
記録が残っていることで、原因の追跡が容易になり、不適合品の回収や再発防止策の立案もスムーズに進みます。
また、HACCPは「検証」と「記録」を含むサイクルが組み込まれています。
一度の対応で終わらず、継続的な見直しと改善が自然に行える仕組みになっています。
これにより、衛生管理の質を保ちながら、現場全体の品質向上にもつながります。
まとめ
ここまで、HACCPの概要から「7原則12手順」の進め方、導入による現場の変化までを解説してきました。
最後に、この記事のポイントを簡単に振り返っておきましょう。
・HACCPは、食品の安全を守るための国際的な衛生管理手法です。
製造工程の中で危険を見つけ出し、重要な工程を継続的に管理します。
・この仕組みは、もともとアメリカで宇宙食のために開発されました。
現在はCodex委員会によって国際基準として広く普及しています。
・日本では2021年6月から、すべての食品事業者に導入が義務化されています。
・HACCPは「7原則12手順」で構成されています。
準備から危害分析、管理基準の設定、監視、改善、検証、記録までを体系的に行います。
・導入によって、食品事故の予防や衛生意識の向上、トラブルへの迅速対応が可能になります。
HACCPの理解が深まることで、衛生管理は「やらされるもの」から「現場を守る武器」へと変わっていきます。
まずは自社の実践状況を見直すところから始めてみましょう。
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
ERPとは?解決できる課題と選び方をわかりやすく解説
2025年2月27日
-
生産性を上げる方法を2つの視点で解説|製造業での取り組み事例も紹介
2024年5月7日
-
生産工学とは?初心者向けに3つのポイントで徹底解説|日本大学生産工学部で学べることも紹介
2024年2月20日
-
生産の4Mとは?初心者向けに基本・重要性・フレームワークなどを解説
2024年3月4日
-
仕事を効率化するのに大切な考え方3つ【意外な方法】
2023年2月27日
-
改善のフレームワーク7選|ECRSやKPTなど役立つアイデアを初心者向けに徹底解説
2023年4月17日
-
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?
2025年9月29日
-
業務改善の事例7個【進めるときの注意点や気づきの重要性】
2022年9月26日
-
7つのムダを初心者向けに徹底解説|それぞれの対処法や改善事例も紹介
2024年4月5日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
-
2025年9月29日
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?