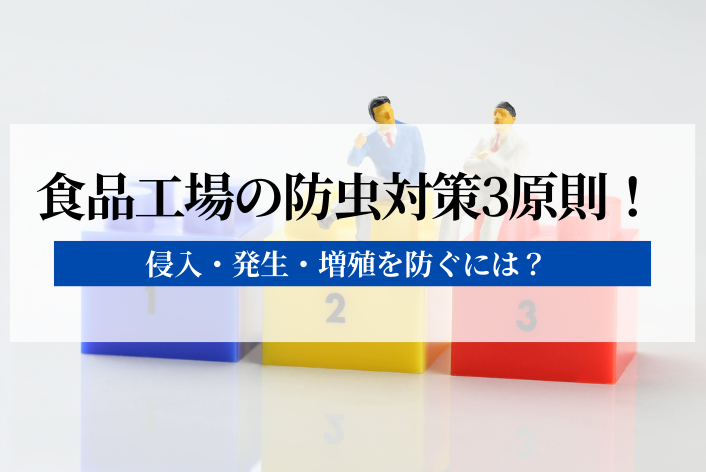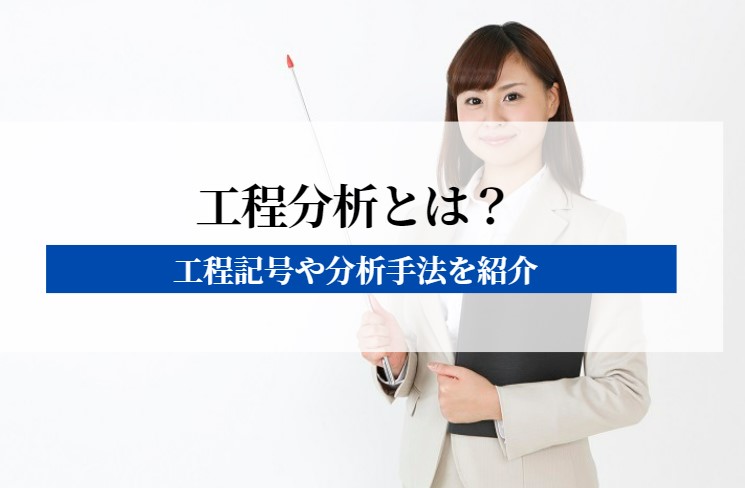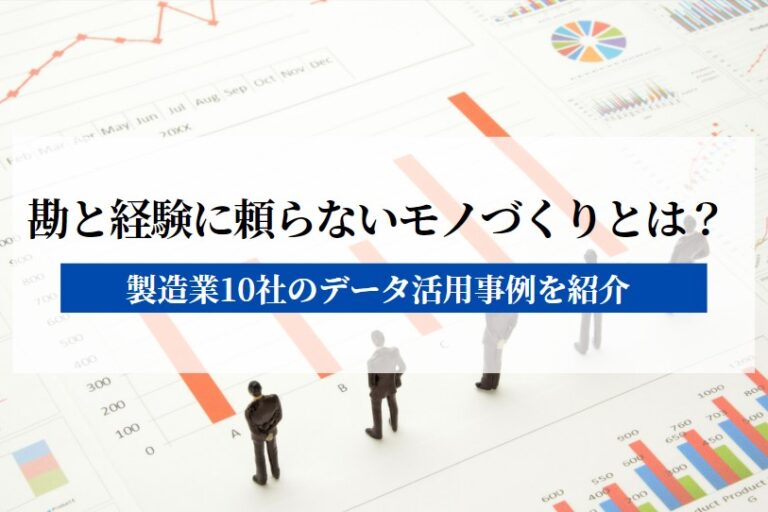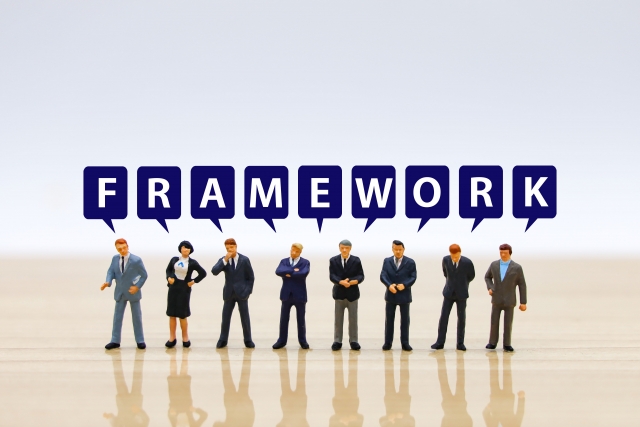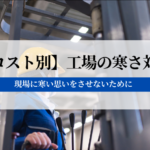工場の5S活動とは?生産性と安全性を高める改善の進め方

「工場 5S」とは、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの頭文字を取った、製造業の現場改善に欠かせない基本活動です。
単なる掃除や片付けではなく、作業効率の向上、事故の予防、品質管理の強化など、工場の生産性と安全性を高めるための実践的な仕組みといえます。
しかし、表面的な取り組みだけでは定着せず、継続的な改善と社内文化としての定着が求められます。
本記事では、5S活動の基本から導入効果、そして社内への定着方法を解説します。
コンテンツ
5S活動とは?
5S活動とは、工場の現場改善の基本として広く知られる取り組みです。
「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つの頭文字Sを取ったもので、職場環境を整備し、働きやすい状態を維持するための活動です。
以下に5Sそれぞれの内容を簡単にまとめました。
| 区分 | 内容 |
| 整理 | 必要なものと不要なものを分別し、不要なものは処分する |
| 整頓 | 必要なものを誰でも分かるように定位置に保管する |
| 清掃 | 汚れやゴミを取り除き、設備の不具合にも気づく |
| 清潔 | 清掃の習慣を仕組み化し、きれいな状態を保つ |
| しつけ | ルールを守る習慣づけを行い、継続的改善の文化を根付かせる |
5S活動の目的
5S活動の目的は、大きく分けて生産性と安全性の向上です。
工場現場では、作業の流れや工程が複雑になりがちで、ムダや危険が潜んでいるケースも少なくありません。
5Sを実践することで、必要なモノがすぐに見つかる環境が整い、探し物の時間を削減できるため、作業効率が大幅に改善されます。
つまり、5S活動は単なる環境整備にとどまらず、製造現場の生産性・安全性・品質を高める改善手法なのです。
工場で5S活動が重要なのか?
工場での5S活動は、ただの掃除や片付けではありません。
現場を整えることで、作業のムダが減り、安全性や品質も向上します。
ここからは、5Sが工場でなぜ重要なのかを3つに分けて解説します。
業務効率と生産性の向上
5S活動のうち「整理」と「整頓」は、業務効率につながる要素です。
不要なものを処分し、必要なものを取り出しやすく配置することで、「探す」「移動する」といったムダな作業がなくなります。
これにより、作業者は本来の業務に集中できるようになり、生産性が向上します。
また、整然とした職場では作業の流れが明確になり、新人や派遣社員でもすぐに業務を把握できます。
結果として教育時間の短縮にもつながり、人材の即戦力化を後押しします。
5Sによる効率化は、現場の「当たり前」を高い水準で維持する仕組みとなるのです。
職場環境の安全性向上
工場の安全管理においても、5Sは重要な役割を果たします。
散乱した工具や床に置かれた部材が原因で転倒やケガが発生するリスクは、日常的にあります。
ケガのリスクは「整理」や「整頓」によって物の定位置を明確にし、「清掃」を習慣化することで低減可能です。
さらに、機械の周辺を常に清潔に保つことで、オイル漏れやボルトの緩みといった初期の異常を早期に発見しやすくなります。
5S活動は、作業者の安全を守る土台であり、労働災害を未然に防ぐ仕組みとも言えます。
安全な環境が整えば、作業者の心理的負担も軽減され、安心して作業に集中できるようになるでしょう。
製品の品質(QCD)向上と維持
QCDとは、「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「納期(Delivery)」の頭文字をとった生産性の3指標です。
5S活動はこのQCDすべてに好影響を与えます。
例えば、「清潔」が保たれている職場では、異物混入や部品の取り間違いなどのミスが減り、結果として製品の品質が安定します。
また、ムダな在庫や重複作業がなくなることでコスト削減にもつながります。
さらに、作業の効率化が進むことで納期の短縮も可能になり、取引先からの信頼性も向上します。
このように、5Sの地道な積み重ねが、最終的に高品質・低コスト・迅速納品という理想のものづくり体制を築く鍵となるのです。
社内に5Sを浸透させるためにやるべきこと
5S活動は、単発的な取り組みでは効果が限定的になってしまいます。
持続的に成果を出すには、現場に根付いた文化として5Sを定着させることが大切です。
以下では、5Sを社内に定着させるために取り組むべき3つのポイントを紹介します。
目的や目標を社員に定期的に共有する
5S活動の継続には、目的や目標を明確にし、それを全社員と共有することが大切です。
ただ「整理整頓をしよう」と呼びかけるだけでは、なぜそれをやるのかが伝わらず、行動にはつながりません。
重要なのは、「なぜ今、5Sが必要なのか」「これをやることで現場にどんな変化が起こるのか」を具体的に説明することです。
例えば、「不良品を減らして顧客満足度を高めたい」「ケガのない安全な職場を作りたい」といった目的を言語化し、掲示板や朝礼で定期的に共有します。
その上で、「今月は○○の整頓を完了させる」といった具体的な目標を立て、達成度を見える形で示すことがポイントです。
チェックシートなどで管理する
5S活動を継続的に管理するうえで有効なのが「チェックシート」の導入です。
整理整頓や清掃の状況を定期的に点検し、視覚的に管理できるため、維持・改善のサイクルを確立しやすくなります。
チェックシートでは、例えば「工具は所定の位置に戻されているか」「床にゴミや油は落ちていないか」などの具体的な確認項目を設けます。
具体的な確認項目を設けることにより、判断基準が明確になり、誰が見ても同じ評価ができるようになります。
評価は部署ごとに行うと、内部の意識が高まりやすく、5Sに対する責任感も強くなります。
定期的に点検を実施して改善点をフィードバックすれば、マンネリ化を防ぎながら、5S活動を社内文化として根付かせることが可能です。
また、優れた取り組みには表彰制度を設けることで、さらに意欲向上につなげることもできます。
改善を続ける
5S活動は、一度整った状態を維持するだけでなく、常に「より良くする」という視点で改善を重ねていくことが大切です。
整理整頓のルールが形骸化したり、チェックリストが機械的になってしまうと、活動の意味が薄れてしまいます。
そのためにも、改善提案制度の導入や現場ミーティングの定期開催など、現場の声を反映する仕組みづくりが必要です。
小さな不満や気づきを放置せず、「もっと効率よくできる方法はないか?」といった前向きな問いかけを習慣化しましょう。
また、5S活動の成果を「見える化」することも重要です。
ビフォーアフターの写真掲示や改善事例の共有を行うことで、達成感を感じやすくなり、継続するモチベーションの維持につながります。
まとめ
5S活動は、工場の生産性・安全性・品質を高めるための土台となる取り組みです。
「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」を徹底することで、ムダの削減、作業効率の向上、事故の予防、そしてQCDの改善にもつながります。
重要なのは、5Sを一時的な作業にせず、社内文化として定着させることです。
明確な目的と目標の共有、チェックシートによる可視化、継続的な改善を通じて、強い現場づくりを進めていきましょう。
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?
2025年9月29日
-
工場の暑さ対策を徹底解説!2025年義務化対応と効果的な対策とは?
2025年7月30日
-
工程分析とは?使われる記号や手法、改善ポイントを解説
2025年3月24日
-
HACCP 7原則12手順で守る「食の安全」!
2025年8月27日
-
生産性を上げる方法を2つの視点で解説|製造業での取り組み事例も紹介
2024年5月7日
-
勘と経験に頼らないモノづくりとは?製造業10社のデータ活用事例を紹介
2025年4月25日
-
ボトルネック工程の解消ステップ5つ|見つけ方と注意点も
2022年1月17日
-
改善のフレームワーク7選|ECRSやKPTなど役立つアイデアを初心者向けに徹底解説
2023年4月17日
-
業務効率化の成功事例7つを参考にアイデア出しをしよう!業務の無駄の見つけ方も解説
2023年12月12日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2026年1月29日
工場の寒さ対策をコスト別に紹介!現場に寒い思いをさせないために
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則