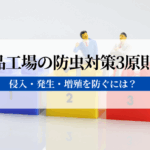多品種少量生産で顧客ニーズに応える!量よりバラエティの時代

スマートフォンやECサイトの普及により、消費者はいつでも欲しい商品を調べ、比較し、購入できます。
そこにトレンドの移り変わりの速さも加わり、商品サイクルはどんどん短くなっています。
こうした背景から、製造業は「多品種少量生産」への対応を迫られるようになりました。
本来なら、大量生産で効率を重視したい。
しかし、多様化する顧客ニーズに応えるためには、多少非効率でも「多くの品種」を「少量で生産」する必要があるのです。
本記事では、そんな多品種少量生産の基本からメリット・デメリット、現場改善の具体策までを解説します。
コンテンツ
多品種少量生産とは何か?
多品種少量生産の定義
多品種少量生産とは、多くの種類の製品を、それぞれ少量ずつ製造する生産方式です。
例えば、10種類の異なる製品を各100個ずつ生産するケースがこれに該当します。
この方式の目的は、顧客ごとの細かなニーズや、市場のトレンド変化に柔軟かつ迅速に対応することにあります。
本来、製造現場としては「少品種大量生産」で効率よく回したいというのが本音です。
それでも、多様化する顧客ニーズや市場変化に対応するには、多品種少量生産をやむを得ず選ばざるを得ないというケースが多くなっているのです。
少品種大量生産との違い
多品種少量生産とよく比較されるのが、「少品種大量生産」という生産方式です。
少品種大量生産は、製品の種類を限定し、大量に作ることで生産性を高める生産方法です。
生産ラインを効率化しやすく、同じ部品や材料を大量に使うことで調達コストも削減でき、安定した大量供給に向いているのが特徴です。
ここでは、よく比較される少品種大量生産と多品種少量生産の違いを表で整理してみます。
| 項目 | 少品種大量生産 | 多品種少量生産 |
|---|---|---|
| 生産のスタイル | 少ない種類の製品を大量に作る | 多くの種類の製品を少量ずつ作る |
| 生産効率 | 高い(ラインが効率化しやすい) | 低くなりがち(段取り替えが多い) |
| コスト面 | まとめて作ることでコストを抑えやすい | 1個あたりのコストが高くなりやすい |
| 市場対応力 | 安定需要には強いが変化に弱い | トレンドや個別ニーズに対応可能 |
| 対応できる市場 | マス向け・標準製品 | ニッチ市場・短サイクル商品・個別対応品 |
| 在庫リスク | 高め(売れ残りのリスクあり) | 低め(各多品種の在庫が残るリスクあり) |
なぜ今「多品種少量生産」が求められているのか
多品種少量生産が避けて通れない選択肢になりつつある背景には、消費者ニーズの多様化と市場環境の変化があります。
かつては「安くて良いもの」が重視されていましたが、近年はライフスタイルや価値観の多様化により、「自分にとって価値のあるもの」を選ぶ時代へと変化しています。
たとえば、健康志向やサステナブル志向、デザイン性重視など、選ばれる基準は人それぞれです。
その結果、「誰にでも合う製品」よりも、「自分に合った製品」が求められる傾向が強まっています。
さらに、SNSやECサイトの普及も影響しています。
インターネットを通じて多様な商品情報にアクセスしやすくなったことで、消費者の選択肢は格段に広がりました。
SNSでは個人の好みや価値観に合った商品がシェアされやすく、ECでは個別ニーズに対応した製品が簡単に購入できるようになっています。
加えて、季節やトレンドに合わせた短サイクルの商品投入も増加。
こうした環境の中で、企業側にはより細やかな商品展開が求められるようになっています。
多様化する顧客ニーズや市場の変化にスピーディーに対応する手段として、「多品種少量生産」が選ばれているのです。
多品種少量生産に向いている業界とその特徴
多品種少量生産は、製品のバリエーションが多く、需要の変動が激しい業界に適しています。
こうした業界では、消費者の細かいニーズに応える柔軟性が求められ、製品の差別化が競争力につながります。
多品種少量生産が取り入れられている主な業界は、以下のとおりです。
アパレル業界
アパレル業界は、多品種少量生産が定着している業界の一つです。
季節ごとのトレンド変化やファッション性、さらにサイズ・カラー展開など、商品バリエーションが多岐にわたります。
大量生産だとトレンドを逃して売れ残るリスクが高いため、小ロットで多品種を生産する体制が基本となっています。
少量ずつ市場に投入し、反応を見ながら柔軟に生産調整を行うことで、在庫リスクを抑えることができます。
食品業界
食品業界でも多品種少量生産のニーズは高まっています。
健康志向、アレルギー対応、地域・季節限定のフレーバーなど、消費者の好みが多様化していることが背景です。
こうした中、小ロットで多様な製品を製造できる体制があれば、新商品の試験展開から本格投入までをスピーディーに実施することが可能です。
また、食の安全性や賞味期限管理においても、小ロットでの生産は売れ残りや廃棄のリスクを抑え、ロスを減らす手段として有効です。
自動車や産業機械業界
自動車業界は量販車では見込み生産が中心である一方、商用車や産業機械では受注生産の比率が高く、顧客の要求に応じた柔軟な設計や製造が必要とされます。
特にBtoB向け製品では、用途・設置環境・スペックなどが案件ごとに異なるため、一律の大量生産には向いていません。
そのため、多品種少量生産のように、仕様変更に柔軟に対応できる体制が求められます。
また、個別受注での製造であっても、生産性や納期を両立させるためには、効率的な生産管理や工程調整が必要です。
多品種少量生産のメリット
製造の効率性は落ちてしまう多品種少量生産。
しかし、それでも採用される理由には何があるのでしょうか?
多品種少量生産のメリットを3つ紹介します。
顧客ニーズに柔軟に対応できる
顧客の価値観やライフスタイルが多様化する現代では、「誰にでも合う製品を大量に作る」よりも、「個別のニーズに合った製品を提供する」ことが重要になっています。
多品種少量生産は小ロットで製品を展開するため、素材・色・デザイン・機能などに幅を持たせた細かな対応がしやすいという点がメリットです。
その結果、顧客満足度の向上やブランドへの信頼感、リピーター獲得といった効果が期待できます。
在庫リスクをコントロールしやすい
大量生産では、もし需要予測を外してしまうと在庫が余って値下げや廃棄につながるリスクがあります。
その点、多品種少量生産は少量ずつ段階的に投入できるため、市場の動きを見ながら調整できる柔軟さがあります。
とくにトレンドの変化が早い製品分野では、必要に応じて小ロットで増産することで過剰在庫のリスクを軽減できます。
ここで注意したいのは、製品のバリエーションが増えるということは在庫の数量も増えるということ。
極端な話、あまりに多くの品種を製造してしまうと、バリエーション豊かな在庫で倉庫がいっぱいに。
そうなると過剰在庫のリスクは当然あるため、生産する種類と量のバランスが大事です。
ニッチ市場へのアプローチが可能になる
多品種少量生産には、一般的な大量生産ではカバーしきれないニッチな市場に対応できるというメリットもあります。
たとえば、特定の地域・年齢層・用途向けの製品や、マニア向けの限定アイテムなど、ニーズはあるけど大量には売れない、そんな商品にも小ロットで対応できます。
こうした細かい市場は競合が少ない場合も多く、上手く対応すれば高付加価値なビジネスチャンスにつながる可能性があります。
従来なら見過ごされがちだったニーズにも、多品種少量生産を活用すれば着実にアプローチできるのです。
多品種少量生産の課題
多品種少量生産は柔軟性や市場適応力に優れる一方で、運用面ではいくつかの課題を抱えています。
これらの課題を正しく理解し、適切な対応を取らなければ、生産効率や収益性の低下につながる恐れがあります。
ここでは代表的な4つの課題を紹介します。
製造コストがかかる
多品種少量生産では、製品ごとに原材料や部品が異なります。
そのため、まとめ買いによるコスト削減効果を得にくい傾向があります。
製造ラインの切り替えや金型・治具の交換が頻繁に発生し、そのたびに段取り時間と人件費がかかります。
また、製品ごとの設計・検査・品質管理にも個別対応が必要なため、管理コストも増加します。
結果として、少品種大量生産と比べて製造原価が上がりやすい構造になっています。
生産計画が煩雑になる
多品種少量生産では、製品種類が多い分、生産計画の立案が複雑になります。
製品ごとに納期や工程が異なるため、設備や人員の割り当て、資材の手配などを細かく調整しなければなりません。
さらに、急な仕様変更や追加注文が入ると計画全体を組み直す必要があり、現場への影響も大きくなります。
生産計画の精度が低いと、納期遅延や余剰在庫の発生につながりやすくなります。
多能工化の教育に時間がかかる
多品種少量生産では、作業員が複数の製品や工程に対応できる「多能工化」が求められます。
しかし、製品ごとに工程や作業内容が異なるため、必要なスキルや知識の習得には時間がかかります。
OJTや座学研修だけでなく、実際の生産現場での経験も必要で、教育コストやトレーナーの負担が増大します。
また、熟練者のノウハウが属人化している場合、技能継承がスムーズに進まないという問題も発生します。
ヒューマンエラーが起きやすい
多品種少量生産では、作業内容や手順が頻繁に変わるため、ヒューマンエラーの発生リスクが高まります。
特に、3H(初めて・変更・久しぶり)に該当する作業はミスが発生しやすく、品質不良や安全事故につながる可能性があります。
作業者が混乱しやすい状況や、標準作業手順が整備されていない現場では、この傾向が顕著になります。
多品種少量生産を効率化するための改善策
多品種少量生産のメリットを活かすためには、課題ごとに適切な改善策を実行することが重要です。
ここでは、課題に対応する施策を解説します。
共通化と自動化で製造コスト削減
製造コストを削減するには、部品や工程の共通化と自動化がポイントです。
たとえば、複数の製品で共通の部品を使うようにすれば、調達コストの削減が期待できます。
また、工程の標準化を進めることで、段取り替えの手間や製造ラインの切り替え時間の短縮にもつながります。
さらに、組立・検査・出荷などの工程に自動化設備やロボットを導入すれば、人件費削減と品質安定化の両立につながります。
設備の稼働状況をIoTで見える化すれば、ムダな停止や非効率な稼働を防ぎ、生産性の向上にもつながります。
管理システム導入する
製品数が多くなるほど、生産計画の立案と調整が煩雑になります。
この課題には、生産管理システムの導入が効果的です。
受注から資材手配、スケジュール管理、進捗確認までをシステムで一元管理することで、部門間の情報共有がスムーズに。
計画変更にも迅速に対応でき、現場の混乱を防ぐことができます。
また、生産スケジューラ機能を活用すれば、設備や人員の負荷を考慮した生産計画の自動立案が可能になり、納期遵守と担当者の負担軽減につながります。
スキルの見える化と動画活用
多品種少量生産では、現場作業者が複数の工程に対応できる「多能工化」が求められます。
そのためには、スキルマップと動画マニュアルの活用が効果的です。
スキルマップを使えば、各作業者の習熟度や資格を一覧で把握でき、教育計画や人員配置を効率化できます。
また、動画マニュアルなら、言葉だけでは伝わりづらい作業の動きや注意点を視覚的に伝えられるため、教育期間の短縮にもつながります。
加えて、動画は内容の更新がしやすいため、新製品や工程変更にも柔軟に対応できます。
標準化とチェックでヒューマンエラー防止
ヒューマンエラーを防ぐためには、作業の標準化とチェック体制の整備がポイントです。
たとえば、図や写真を使った手順書や動画マニュアルを用意して、全員が同じやり方で作業できるようにします。
さらに、指差呼称やダブルチェック、バーコード・QRコードによる資材確認など、チェックの仕組みを組み込むのも効果的です。
ミスが起きたときは「なぜ起きたか」をきちんと振り返り、手順書やマニュアルに改善内容を反映することで、再発を防げます。
まとめ
多品種少量生産は、変化の激しい市場環境で生き残るための戦略のひとつ。
少量ずつ多様な製品を生産することで、多様化する顧客ニーズやトレンドに迅速に対応できるのがメリットです。
しかし、その柔軟性の裏側では、製造コストや計画立案の難しさ、人材育成や品質管理といった課題も。
また、大量に生産しないぶん過剰在庫のリスクを抑えやすいとはいえ、品種それぞれの在庫を抱えてしまうリスクはあります。
これらを克服するためには、製品設計や工程を共通化し、必要に応じて自動化を進めることで効率を高めることが重要です。
また、現場の情報や人材のスキルを見える化し、教育や作業手順の標準化を徹底することで、安定した品質と生産性を両立につながります。
多品種少量生産は、単なる生産方式ではなく、改善と工夫を重ねながら企業の競争力を育てる長期的な取り組みといえるでしょう。
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
業務改革プロジェクトを成功に導くコンサルタントの役割と活用ポイント
2021年6月28日
-
工場の5S活動とは?生産性と安全性を高める改善の進め方
2025年7月30日
-
HACCP 7原則12手順で守る「食の安全」!
2025年8月27日
-
工場の暑さ対策を徹底解説!2025年義務化対応と効果的な対策とは?
2025年7月30日
-
在庫管理を見える化する方法3つ|メリットとExcelの活用事例も
2022年4月1日
-
改善点とは?製造業における意味と洗い出すときに必要な7つの視点
2023年5月23日
-
在庫管理をバーコードでするメリット3つ!デメリットやエクセルで自作する方法も解説
2023年11月6日
-
業務改善で問題点の洗い出しをする方法3つ!重要な理由と注意点もご解説
2022年3月3日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
-
2025年9月29日
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?