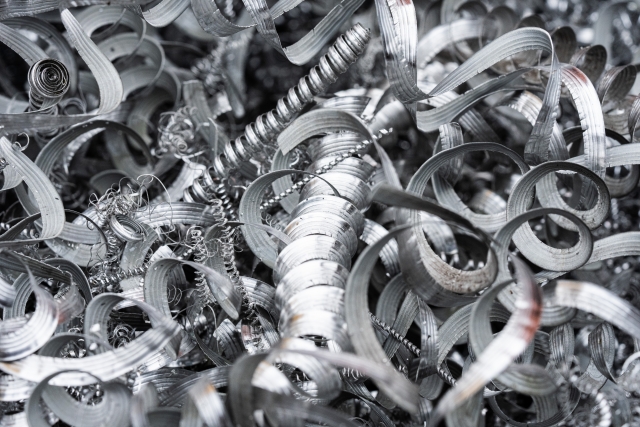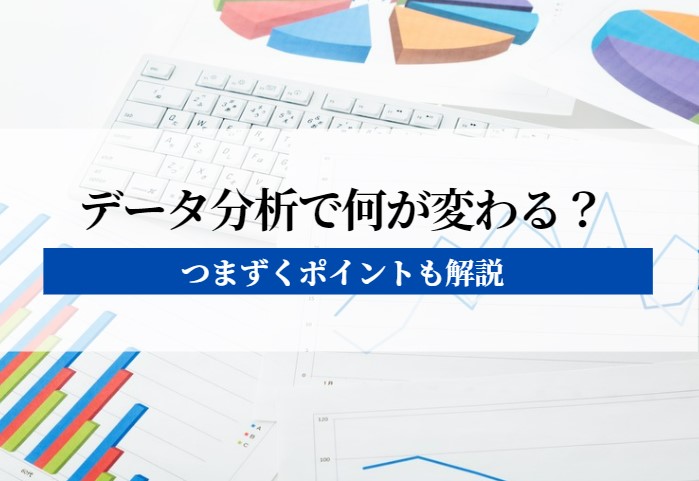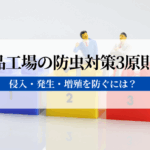課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
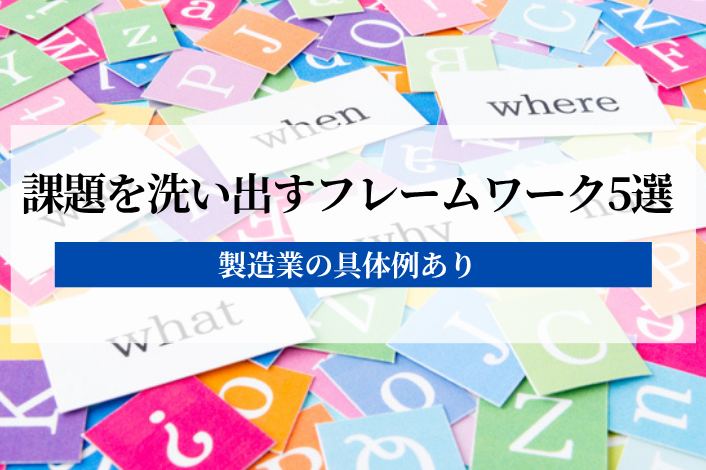
「現状に問題があるのはわかっている」
「ただ、何をするべきかがわからない」
それは、問題解決のための「課題」が設定できていない状態かもしれません。
課題を洗い出して設定することは、問題を解決する過程の一部。
【問題発見から解決までのStep】
①現状を把握する
②現状にある問題を発見する
➌問題の原因を分析して、課題を設定する
④課題解消のためのアクションを実行する
⑤アクションの効果を検証する
⑥検証した結果、問題が解決するor解決しない場合は①に戻る
本記事では、上記の「➌問題の原因を分析して、課題を設定する」ステップに特化したフレームワークを紹介します。
コンテンツ
課題を洗い出すためのフレームワーク5選
問題の原因から課題を洗い出すためのフレームワークを紹介します。
1. 問題の「根本」を知りたい→ なぜなぜ分析
トヨタ式の問題解決として有名なフレームワークです。発生した問題に対して「なぜ?」を繰り返し問い続けることで、真の原因を掘り下げていくシンプルな分析手法。
最初に見えるのはあくまで表面的な原因であり、本当に対処すべき課題はもっと深い場所にある可能性が高いです。
そこで「なぜ?」を何度も問いかけることで、思い込みや当たり前を疑いながら、本質に近づいていきます。
考え方のポイント
・「5回」という数字はあくまでも目安であって、回数に縛られる必要はない
・「なるほど、だから問題が起きたのか」と全員が納得できる原因にたどり着くことが大切
・最終的な原因を人や部署の責任にするのはNG、「仕組み」や「ルール」に目を向ける
どういう時に使うか
・問題が繰り返し起きている
・対症療法だけでは解決できない
・原因が曖昧で、何から手をつけるべきかわからない
具体例
問題 → 製品に傷がついて出荷できなかった
なぜ?→ 検品で不良品が見つかったから
なぜ?→ 組立工程で部品に傷が入ったから
なぜ?→ 作業者が部品を素手で扱っていたから
なぜ?→ 手袋の着用ルールが守られていなかったから
なぜ?→ 手袋の着用チェックを義務付けていなかったから
課題 → 作業前のチェックルールが未整備だったこと(=問題解決のために取り組むべきこと)
2. 理想と現実の差を見たい → As-Is/To-Be(アズイズ・トゥービー)
As-Is/To-Be分析は、現状(As-Is)と理想の状態(To-Be)を対比して、そこにあるギャップ(=課題)をあぶり出すフレームワークです。まずは「今どうなっているか?」を客観的に整理し、その上で「どうなっていたら理想的か?」を描きます。この差を埋めるために、必要な改善や施策を考えていくのが基本の流れです。
考え方のポイント
・ぼんやりとした理想像を描くのではなく、数値・状態・仕組みを具体的に言語化する
・現状とのギャップが大きいほど課題も複雑になるため、段階的にTo-Beへ近づけるステップを設計する
どういう時に使うか
・理想の状態はあるが、そこに到達できていない
・現状と理想のギャップを客観的に整理したい
・関係者と共通認識をつくって動き出す土台がほしい
具体例
【現状と理想】
・As-Is(現状):検査不良率が3.5%
・To-Be(理想):検査不良率を1%未満に抑えたい
【ギャップの要因】
・マニュアルが古く更新されていない
・ベテラン作業員による属人的な判断が多い
・新人への教育体制が整っていない
【洗い出された課題】
・作業標準の見直し
・判断基準の明文化
・教育プログラムの再構築
3. 構造的に整理したい → ロジックツリー
ロジックツリーは、問題や目標を「なにが原因か?」「なにが構成要素か?」という視点で枝分かれさせながら、論理的に分解していくフレームワークです。
「Whyツリー(原因分析)」や「Howツリー(施策検討)」など、目的に応じて使い分けができるのも特徴。
考え方のポイント
・要素同士が漏れなく、ダブりなく(MECE)整理されていること
・各分岐が「だから何?」「それで何が起きている?」に答えられること
・どこに課題が集中しているかを、構造的に「見える化」できるのが強み
どういう時に使うか
・問題の構造を図解で整理したい
・原因が複雑に絡み合っている
・施策の選択肢を洗い出したい
・チームで共通認識を持ちたい
・「結局どこから手をつけるべき?」を明確にしたい
具体例
★問題:製品の納期遅延が発生している
┗ 原因①:部品調達の遅れ
┗ 発注ミス
┗ 仕入先の納期遅れ
┗ 原因②:組立工程でのトラブル
┗ 人員不足
┗ 設備の故障
┗ 原因③:出荷直前の検品で不良品が見つかる
┗ 作業ミス
┗ 基準のばらつき
例えば、原因①の「部品調達の遅れ」の観点で見た際に「発注ミスは毎月1件程度だが、仕入先の納期遅れは毎週発生している」なら対策すべきは仕入先の納期遅れを防ぐこと。
構造化することで「最も影響が大きいのはどこか?」を見極めやすくなります。
4. 現場の業務改善をしたい → ECRS(イクルス)
ECRSは、業務を見直すときに使える4つの視点で構成されたフレームワーク。「そもそも必要?」「まとめられないか?」「順番を変えられないか?」「シンプルにできないか?」と問いかけながら、現場のムダ・ムラ・ムリを削ぎ落としていくアプローチです。頭文字は、以下の英単語から取られています。
・E:Eliminate(排除)
・C:Combine(結合)
・R:Rearrange(順序変更)
・S:Simplify(簡素化)
考え方のポイント
・順番は「E → C → R → S」の優先度(まず「なくせるか」を考える)
・改善=増やすことではなく、「減らす・やめる」が基本
・細かい手順やルールにも目を向けて、「当たり前」を疑う視点が大事
・現場の人の声(実務での気づき)をヒントにすると精度が上がる
どういう時に使うか
・業務のムダが多くて効率が悪い
・新しく仕組みを整える余裕はないが、今あるものを見直したい
・新人や他部署に引き継ぎにくい属人化業務がある
具体例
★問題:出荷前チェックに毎回時間がかかっている
・E(排除):必要のない二重チェック項目をなくす
・C(結合):最終チェックと出荷準備を同じ作業ステーションで実施
・R(順序変更):工程の最後ではなく、組立直後に一部チェックを先行して実施
・S(簡素化):チェックリストを紙からタブレットに統一して記入の手間を削減
5. 市場や競合を含めて考えたい → 3C分析
ビジネスの外部・内部環境を「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から整理し、自社の戦略や課題を明らかにするフレームワークです。
特定の問題にフォーカスするというより、まず全体を俯瞰して「どこにチャンスやリスクがあるか?」を見極めるのに使えます。
考え方のポイント
・3つのCは、「誰に」「どんな価値を」「どう勝つか」を整理する枠組み
・それぞれのCをバラバラに見るのではなく、3つの関係性(ズレや一致)に注目する
・「自分たちがやりたいこと」より、「市場で求められていること」を軸に考える
・外部(顧客や競合)から見て、自社の立ち位置はどう映るか?という視点が大事
どういう時に使うか
・自社サービスの強みと弱みを整理したい
・市場の変化や競合の動きを受けて、戦略を見直したい
・商品やサービスを「誰に向けてどう売るか」を再定義したい
具体例
【部品製造メーカーの場合】
Customer(顧客):高品質・短納期を重視する国内大手企業がメイン
Competitor(競合):価格重視で大量生産できる海外メーカーが台頭中
Company(自社):一品一様の対応力や、小ロット生産に強みがある
→ 「価格競争では勝てないが、柔軟性×高品質」でニッチ市場を狙う戦略が有効
→ 逆に「競合と同じ土俵で戦っていないか?」の見直しが課題になることも
まとめ
問題に対して、何から手をつけるべきかわからない。
そんなときに使える、課題の「洗い出し」に特化したフレームワークを5つ紹介しました。フレームワークを使うことで、思考の抜け漏れを防ぎつつ、関係者との共通認識もつくりやすくなります。それぞれ特徴があるので、目的や状況に応じて使い分けましょう。
■なぜなぜ分析:原因を掘り下げて真の課題を見つける
■As-Is/To-Be:理想と現状のギャップを明確にする
■ロジックツリー:複雑な問題を構造的に整理する
■ECRS:現場のムダを減らして効率化する
■3C分析:外部環境を含めて戦略的に課題を捉える
課題を正しく設定できれば、解決の道筋は必ず見えてきます。
とはいえ、現場では「どこに課題があるのか」が掴みにくいもの。
そんなときは、製造業専門のコンサルティング会社「あおい技研」にご相談ください。
長年の現場改善ノウハウとデータ分析力を活かし、工程・品質・生産性など、複雑に絡み合う問題を構造的に「見える化」いたします。お気軽にご相談ください。
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
製造業の見える化とは?意味と目指すメリット・実行する方法・事例をご紹介
2021年10月20日
-
工場を見える化する目的とメリット4つ!具体的な方法や事例・課題も解説
2022年7月1日
-
業務改善の方法を6ステップでご紹介|具体例やフレームワークも
2022年2月7日
-
QC7つ道具を初心者向けに解説!覚え方や使い方を5ステップで紹介
2022年7月4日
-
7つのムダを初心者向けに徹底解説|それぞれの対処法や改善事例も紹介
2024年4月5日
-
データ分析で製造業の何が変わる?つまずくポイントも解説
2025年3月24日
-
業務管理の基本6つを初心者向けに解説!理由や進め方・役立つツールも紹介
2022年8月30日
-
在庫管理を見える化する方法3つ|メリットとExcelの活用事例も
2022年4月1日
-
作業の効率化が進まない理由5つ!製造業における向上の事例も紹介
2023年9月12日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
-
2025年9月29日
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?