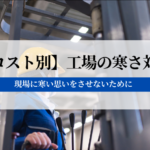工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
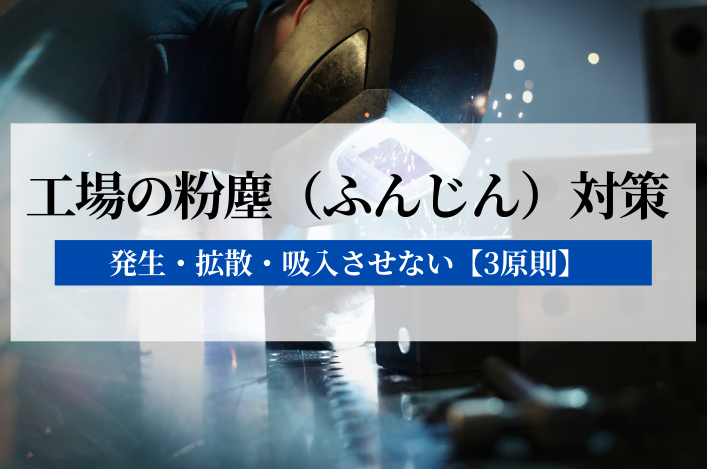
工場の日常業務で発生する「粉塵」。
長年吸い続けることで「じん肺」を引き起こしたり、「粉塵爆発」の原因になったりするため、取り扱いに対策が必要な存在です。
本記事では、従業員と会社の未来を守るために不可欠な粉塵対策について、基礎知識や「発生させない・拡散させない・吸入させない」の3原則を解説します。
コンテンツ
粉塵(ふんじん)の基礎知識
そもそも、粉塵とは?そんな疑問に回答します。
粉塵とは?
粉塵(ふんじん)とは、物を加工したり燃やしたりすることで空気中に舞い上がる「細かい粒子」のことです。
工場では、切削・研磨・粉砕・搬送・燃焼など様々な工程で粉塵が発生します。
目に見える大きな粒子もあれば、肉眼では見えにくい微細なものもあり、吸い込むと「じん肺」という呼吸器系の健康被害につながります。
粉塵は、その元となる材料によっていくつかの種類に分けられます。
| 鉱物性粉塵 | 石材、金属、セメント、ガラスなどを加工するときに出る粉塵 長期的に吸入するとじん肺や肺がんのリスクがある |
| 有機物粉塵 | 木材や穀物、紙、綿などの有機物を扱うときに出る粉塵 アレルギー性鼻炎や喘息の原因になるリスクがある |
| 化学性粉塵 | プラスチックや化学薬品を扱う過程で発生する粉塵 吸入すると中毒や化学的な炎症を引き起こす危険性がある |
| 金属粉塵 | 鉄、アルミ、マグネシウムなど金属を削ったり研磨したりすると発生する粉塵 種類によっては発火性・爆発性があり、作業環境管理が重要 |
| その他特殊粉塵 | 石綿(アスベスト)などの有害性が強いもの 現在は使用に関する規制があるが、古い建材や機械設備で問題になることも |
粉塵はどのように発生する?
粉塵は「固体を細かく砕く作業」があれば、どこでも発生します。原理としては、料理でゴマをすったり、スパイスを砕いたりするのと同じです。
ただし、工場や建設現場では、その規模が非常に大きくなります。
具体的には、以下のような現場や作業で多くの粉塵が発生しています。
1. 削る・磨く
製品の形を整えたり、表面を滑らかにしたりする作業です。ヤスリがけをイメージすると分かりやすいでしょう。
■金属工場:グラインダーという機械で金属部品を削る、磨く作業
■家具工場:機械(サンダー)で木材の表面をツルツルに磨く作業
2. 砕く・壊す
大きな塊を、重機や道具を使って小さくしていく作業です。
■建設現場:古いコンクリートのビルを重機で壊す解体作業
■トンネル工事:硬い岩盤をドリルなどで砕いて掘り進める作業
■採石場:大きな岩石を砕いて、砂利や砂をつくる作業
3. 切る・穴をあける
材料を必要なサイズにカットする作業です。ノコギリで木を切ると木くずが出るのと同じです。
■建材の加工:壁や床に使うボードなどを、丸ノコで切断する作業
■石材の加工:石の板をダイヤモンドカッターで切断する作業
4. 混ぜる・袋に入れる
粉状のものを扱う作業では、どうしても粉が空気中に舞ってしまいます。
■食品工場:小麦粉や砂糖、スパイスなどを機械で混ぜ合わせる工程
■化学工場:粉末状の薬品やプラスチック原料を、袋に詰めたり、タンクに投入したりする作業
このように、ものづくりや建設の現場では、製品や建物が完成するまでの様々な工程で、意識しないうちに多くの粉塵が発生し続けているのです。
なぜ、粉塵は「対策すべきリスク」なのか
工場では避けて通れない粉塵ですが、対策しなければならない理由は何なのでしょうか?
人体の健康のため
粉塵による健康への影響は、ケガのようにすぐには現れません。
しかし、気づかないうちに体の中で静かに進行し、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
代表的な病気が「じん肺」です。
これは、目に見えない小さな粉塵を長年吸い続けることで、肺がそのダメージに耐えきれなくなり、スポンジのように柔らかいはずの肺が硬い組織に変わってしまう病気。
肺が硬くなると、風船のようにうまく膨らんだり縮んだりできなくなるため、酸素を十分に取り込めなくなり、軽い運動でも息切れするようになります。
恐ろしいことに、この病気は一度なってしまうと完全に元に戻す治療法がありません。
他にも、気管支炎やぜんそく、アレルギーの原因になったり、扱う物質によっては、がんや中毒症状を引き起こしたりするケースもあります。
会社には、法律によって「従業員の安全と健康を守る責任」が定められています。粉塵対策は、そこで働く人々への最低限の責任でもあるのです。
粉塵爆発の恐れがあるため
「粉が爆発する」と聞いても、ピンとこないかもしれません。しかし、これは現実として起こり得る事故です。
粉塵爆発とは、可燃性の粉(小麦粉や砂糖、金属の粉など)が空気中に濃く漂っている状態で、静電気のような小さな火花に触れることで発生します。スプレー缶のガスに引火して爆発するのをイメージすると近いかもしれません。
細かい粒子が一斉に燃え上がることで、凄まじいエネルギーを発生させるのです。
この爆発の恐ろしい点は、連鎖反応を起こしやすいこと。
最初の小さな爆発が、床や棚に積もっていた粉塵を舞い上がらせ、それがさらに大きな第二、第三の爆発を引き起こします。その威力は、工場の壁や屋根を吹き飛ばすほど強力で、一瞬にして人の命を奪い、会社そのものを失いかねない大惨事につながります。
結論として、粉塵対策は単なる「職場をキレイにする活動」にとどまりません。
従業員のための「健康管理」であり、会社の財産と信用を守る「安全管理」そのもの。事業を続ける上での、根幹に関わる重要な取り組みなのです。
工場の粉塵対策
工場の粉塵対策は、「発生させない」「拡散させない」「吸入しない」という3つの原則に基づいて行われます。
粉塵を発生させない
まず大事なのは、粉塵をできるだけ発生させないことです。
粉塵が出にくい原材料に切り替える、作業工程を見直して湿式化(水を使って粉じんを舞いにくくする)を取り入れる、発生源を密閉・隔離するなど作業環境そのものを改善します。
■湿式化
・水や油を使い、作業場所を湿らせることで粉塵の飛散を防ぐ
・材料の切断時に注水、床への散水など
■材料や工法の変更
・粉塵が出にくい材料に変える
・発じんの少ない作業方法(手作業から自動化された密閉型機械へ変更)を検討する
粉塵を拡散させない
次に、発生してしまった粉塵が、作業エリア全体に広がるのを防ぐための対策です。
代表的なのは発生源のすぐ近くで吸い込む局所排気装置や集塵機、作業場全体の空気を入れ替える全体換気装置などがあります。
■局所排気装置
・粉塵の発生源のすぐ近くにフードを設け、粉塵が広がる前に吸い込んで外部へ排出する設備
・グラインダー作業用のフードや、作業台全体を囲うブースなど
■集塵機
・局所排気装置などで吸引した空気から、フィルターなどを使って粉塵を分離・回収する装置
■全体換気装置
・工場や作業場全体の空気を入れ替えるための換気システム
・局所排気装置とは違い、作業場全体の空気を循環・入れ替えするのが目的
■作業場の隔離
・作業場所を壁やカーテンで囲い、他のエリアと隔離する
粉塵を吸入させない
発生・拡散という2つの対策を行っても、粉塵はゼロにできません。
そのため、作業者が粉塵を吸い込まないための防塵対策も必須です。
■防塵マスク
・作業内容や粉塵の種類に応じて、国が定めた検定に合格した適切な防塵マスクを正しく着用する
・作業者の顔にフィットしているかを確認することが非常に重要
■清掃
・粉塵が飛散しないように業務用の真空掃除機や水を使った清掃を定期的に行う
・床に堆積した粉塵をエアーブローで吹き飛ばすのは、粉塵を再飛散させるため原則禁止
まとめ
工場の安全と従業員の健康を守るための粉塵対策について解説しました。
この記事のポイントを振り返りましょう。
■粉塵は「健康」と「安全」に関わる
・粉塵は、治療困難な病気である「じん肺」や、工場を破壊するほどの威力を持つ「粉塵爆発」を引き起こすリスクがある
・事業継続に関わる「リスク」として捉えて対策する
■対策の基本は「3つの原則」
・発生させない:湿式化や工法変更で、そもそも粉塵を出さない工夫をする
・拡散させない:局所排気装置や集塵機で、発生した粉塵を広げない
・吸入させない:防塵マスクの着用や正しい清掃で、作業者を守る
どれか一つだけではなく、組み合わせて行うことが重要。
粉塵対策は、従業員の健康、そして会社の財産と信頼を守るために行われる取り組みです。
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
業務標準化の事例5選!目的・進め方・メリット・デメリットを徹底解説
2024年9月2日
-
QC7つ道具を初心者向けに解説!覚え方や使い方を5ステップで紹介
2022年7月4日
-
生産管理システムを製造業の中小企業が自作する方法3つとメリット・デメリット
2022年2月14日
-
工程管理の基本を3つの項目で徹底解説【工程管理表の作成方法も】
2022年3月28日
-
製造業のサプライチェーンの課題4つ【対応策】
2024年3月4日
-
工場を見える化する目的とメリット4つ!具体的な方法や事例・課題も解説
2022年7月1日
-
在庫管理をバーコードでするメリット3つ!デメリットやエクセルで自作する方法も解説
2023年11月6日
-
DXで業務効率化できる理由4つを徹底解説|製造業での事例
2022年4月28日
-
工場のヒヤリハットの原因4つ!対策と改善案のネタ切れに役立つ事例も紹介
2024年4月5日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2026年1月29日
工場の寒さ対策をコスト別に紹介!現場に寒い思いをさせないために
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則