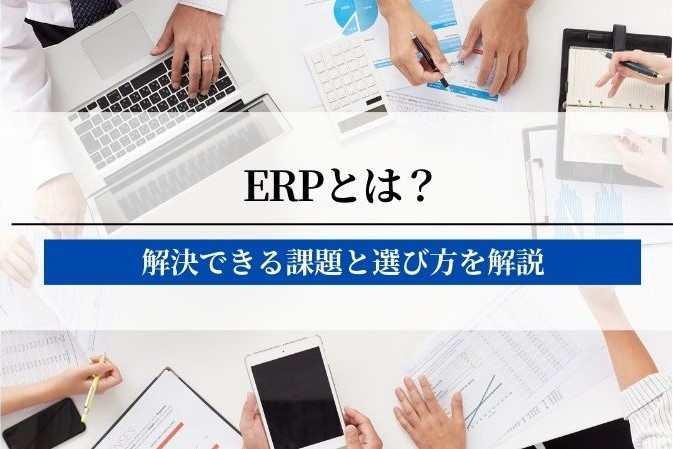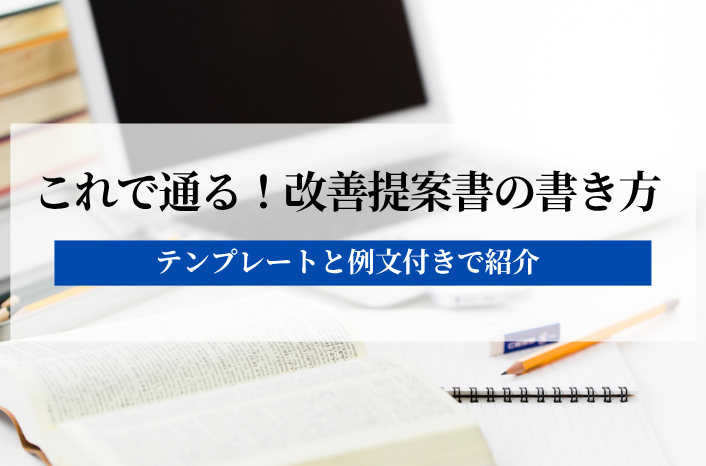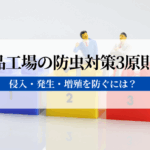工場の暑さ対策を徹底解説!2025年義務化対応と効果的な対策とは?

工場の暑さ対策を徹底解説!2025年義務化対応と効果的な対策とは?
夏場の工場は、建物の構造や機械からの熱、通気性の悪さなどが重なり、過酷な高温環境となりやすく、作業者の熱中症リスクが高まります。
2025年6月からは、厚生労働省による熱中症対策の義務化も始まり、企業は明確な対応を求められるようになりました。
本記事では、工場で暑さが発生する原因を解説し、実際に効果のある暑さ対策や設備導入例、さらに補助金の活用方法までをわかりやすく解説します。
なぜ「工場の暑さ対策」が重要なのか?
工場は夏になると高温多湿になりやすく、熱中症のリスクが非常に高まります。
工場では屋内での作業にも関わらず、令和5年7月24日~7月30日のデータで搬送人員11,765人のうち、10.7%の1,253名が仕事場① (道路工事現場、工場、作業所等)で熱中症になったというデータもあります。
構造的な要因だけでなく、作業環境や労働管理の在り方にも起因しています。
適切な対策が講じられていない職場では、従業員のモチベーションが下がり、早期離職の要因にもなりかねません。
これらのリスクを防ぐためにも、暑さ対策は経営課題として真剣に取り組む必要があります。
参照元:全国の熱中症による救急搬送状況 令和5年7月24日~7月30日(速報値) | 総務省消防庁
工場で熱中症が多発する理由
工場で熱中症が多発する理由は、「屋内であっても高温多湿な環境にさらされている」ことにあります。
工場の建物は鉄やコンクリートで造られていることが多く、外部からの輻射熱が屋内に伝わりやすい構造です。
また、機械設備からの排熱や換気が不十分な空間では熱がこもりやすく、作業者は常に暑さにさらされます。
こうした環境で働き続けると、知らぬ間に体内の水分や塩分が失われ、熱中症につながってしまいます。
暑さが与える作業効率と製品品質への影響
暑さは作業効率にも大きな悪影響を与えます。気温が高い環境では、集中力や注意力が低下し、作業ミスや事故のリスクが高まります。
さらに、製品の品質にも悪影響が及ぶケースがあり、例えば、高温によって材料が変形したり、測定器の誤差が生じることがあります。
暑さは単に従業員の健康を脅かすだけでなく、生産性や品質管理の観点からも重大な影響を及ぼす可能性があることを念頭に置きましょう。
従業員の健康リスクと離職防止
暑さによる健康被害は一時的な体調不良だけでなく、長期的な職場への不満や離職にもつながります。
特に中小企業では、一人あたりの業務負担が大きいため、一人でも体調を崩せば現場全体に影響が出る可能性があります。
働きやすい環境を整えることは、従業員の定着率を高め、長期的な人材確保にもつながります。
今後の労働力不足を見据えても、暑さ対策は経営課題として捉えるべきではないでしょうか。
法改正により義務化された熱中症対策とは?
2025年6月から、厚生労働省により工場や倉庫などの職場における熱中症対策が義務化されました。
これまでは「推奨」に留まっていた対策が、罰則を伴う「義務」となったことで、企業に求められる対応は大きく変わります。
これを受け、企業は早急に体制を見直し、現場での具体的な対応が求められています。
2025年6月からの義務化概要
義務化の背景には、近年増加傾向にある職場での熱中症による労働災害があります。
特に製造業は建設業に次いで被害が多く、重大な事故に至るケースも報告されています。
2025年6月1日からは、暑さ指数(WBGT値)が28℃以上、または気温31℃以上の環境で連続1時間以上、または1日4時間を超える作業を行う場合に、事業者に対策が義務付けられます。
これにより、現場の安全管理体制の再構築が求められるようになりました。
以下は、身体作業強度に応じたWBGT基準値の一覧です。
| 区分 | 身体作業強度(代謝率レベル)の例 | 暑熱順化者のWBGT基準値(℃) | 暑熱非順化者のWBGT基準値(℃) |
| 0 安静 | 安静、軽作業(座位) | 33 | 32 |
| 1 低代謝率 | 軽い手作業(書く、タイピングなど) 立って行う軽作業(検品など) |
30 | 29 |
| 2 中程度代謝率 | 軽機械や手工具の取り扱い作業(くぎ打ち、打ち直しなど) | 28 | 26 |
| 3 高代謝率 | 強度の高い反復作業や 持続的なパワー作業(大型工具の使用、重い荷物の搬送など) |
26 | 25 |
| 4 極高代謝率 | 極めて重い作業(つるはし作業、ふいごの操作など) | 25 | 20 |
罰則や対象条件の確認
新制度では、熱中症対策を怠った企業に対し、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
対象となるのは、「WBGT値28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
つまり、夏季の製造業や倉庫業など、多くの事業所が該当する可能性があります。
このように法的な強制力が伴うことで、単なる注意喚起ではなく、具体的な管理体制の導入が必要になります。
参照元:職場における熱中症対策の強化について | 厚生労働省
企業に求められる具体的な対策
厚生労働省が公表した資料(PDF)では、「現場における対応」として、以下の3つの体制整備が企業に義務付けられています。
1. 体制整備(報告体制)
作業者が熱中症の初期症状や異変を感じた際に、すぐに報告できる体制を構築する必要があります。
具体的には、各職場に担当者と連絡体制を明確に定め、異常を感じたときに迅速に報告できるようにしておくことが求められます。
2. 手順書の事前作成
熱中症が疑われる場合に備えて、応急処置や冷却方法、医療機関への搬送方法などを記載した手順書の作成が必要です。
この手順書は、誰が見ても即座に対応できるよう明確かつ簡潔に記述することが望まれます。
3. 関係者への周知と教育
上記の体制整備および手順書の内容については、現場の作業者全員に確実に周知しなければなりません。
特に、日常的に作業を行う現場リーダーや管理者には、内容を深く理解させるとともに、従業員同士で注意し合える環境づくりも推奨されます。
工場の暑さの主な原因
工場は構造的な特徴や運用環境により、暑さがこもりやすい場所です。
夏には屋外と同等、あるいはそれ以上の高温環境になることも珍しくありません。
ここでは、工場内の温度上昇を招く主な原因について解説します。
構造上の問題(屋根・壁・天井の高さ)
多くの工場では鉄やコンクリート製の屋根や壁が使用されており、太陽からの輻射熱を吸収しやすく、建物内部に熱を伝えやすい素材です。
また、工場は周囲に日陰が少ない立地にあることも多く、屋根や壁が直射日光に晒され続ける環境にあります。
さらに、天井が高く開放的な造りである為、空調が効きづらくなり、上部に熱が溜まりやすくなるという構造的課題も抱えています。
機械熱・搬出入口の開放による熱気流入
工場内では、製造設備や電力装置などから常に「機械熱」が発生しています。この機械熱が空間全体の温度上昇に大きく影響を与えます。
加えて、フォークリフトやトラックによる搬出入が頻繁に行われる現場では、出入り口を長時間開放していることが多く、冷気が逃げるだけでなく外の熱気が流れ込む原因になります。
冷房設備が設置されていても、効果が大きく損なわれる原因となります。
空調の効きづらさと空気の滞留
工場は面積が広く、空調の風が作業エリア全体に行き渡りにくいという特性があります。
機械や棚などが多く配置されていると、空気の流れが阻害され、熱がこもりやすくなります。
特に角部や天井付近は換気が行き届きにくく、熱が溜まります。「空気の滞留」が、局所的な高温状態を生み出し、作業者にとって過酷な環境を生み出します。
効果的な暑さ対策の具体例
前述した通り、工場の暑さ対策には、構造的な問題や機械熱など複数の要因に対応する必要があります。
ただ単に空調機器を追加しても効果は限定的です。
ここでは、コストと効果のバランスの取れた対策を4つご紹介します。
現場の条件に合わせて、組み合わせて導入することで、効果的な暑さ対策が可能となります
ビニールカーテン・ブースで空調の効率化
広い工場内全体を冷やすのは非常に効率が悪いため、作業エリアを部分的に区切ることが効果的です。
ビニールカーテンやビニールブースは、簡易的に空間を仕切ることができるため、冷気が逃げにくくなり空調効率が向上します。
また、透明タイプを選べば視界を遮らず採光性も確保できます。
設置が簡単で比較的低コストな点もメリットで、設備投資を抑えつつ効果が期待できます。
遮熱塗料や遮熱シートの導入
屋根や外壁からの熱の侵入を防ぐには、遮熱塗料や遮熱シートの施工が効果的です。
遮熱塗料は太陽光に含まれる赤外線を反射する性質を持ち、屋根の表面温度の上昇を抑えます。
一方、遮熱シートは輻射熱を大幅にカットする高反射性のアルミ素材などを使用しており、屋根裏や機械の囲いなどにも活用可能です。
いずれもエアコンへの負荷を軽減し、省エネ効果も見込めます。
屋根用スプリンクラーの設置
屋根に散水して直接温度を下げる方法として、屋根用スプリンクラーの導入があります。
水が蒸発する際の気化熱によって屋根の表面温度を下げ、工場内部の温度上昇を抑える効果があります。
この方法は、遮熱塗料との併用でより高い効果を発揮します。
ただし、設置には配管や水源の確保が必要であり、導入後は水道代や設備メンテナンスの費用も考慮する必要があります。
自動空調制御システムの導入
温度センサーやIoT技術を活用した自動空調制御システムの導入が進んでいます。
室内の温度や湿度をリアルタイムで監視し、自動的に空調設備を制御することで、無駄な運転を抑えつつ快適な室温を維持できます。
初期投資は必要ですが、長期的には電力消費の抑制や空調機器の寿命延長にもつながります。
省エネと快適性を両立した、将来的な暑さ対策の有効手段といえるでしょう。
暑さ対策に活用できる補助金・助成金
工場の暑さ対策には一定の設備投資が必要ですが、国や自治体の補助金・助成金を活用することで、コスト負担を軽減できます。
ここでは、活用しやすい3つの制度をご紹介します。
エイジフレンドリー補助金
高年齢労働者の職場環境を改善するための補助制度です。
暑さ対策を含む設備導入が対象となります。
・対象:60歳以上の高年齢労働者を常時1人以上雇用する中小企業事業者
・上限額:100万円(補助率 1/2)
・対象経費:
スポットクーラーの購入
休憩所の空調設備設置
WBGT測定器の導入
遮熱シートや空調服などの環境改善備品
・受付期間:年度内で随時(予算がなくなり次第終了)
・所管省庁:厚生労働省(申請相談・サポートあり)
業務改善助成金
賃金引き上げと併せて、生産性向上につながる設備投資を支援する制度です。
・対象:事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業
・上限額:最大600万円(補助率は事業場規模により最大9/10)
・対象経費:
空調設備の導入・更新
遮熱対策(塗料・シート)
自動空調システム
ビニールブースやパーテーションなどの環境整備機器
・受付期間:年度ごとに公募(通常は4月~2月頃)
・所管省庁:厚生労働省(申請マニュアル・相談窓口あり)
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
エネルギー効率向上を目的に、省エネ設備への投資を支援する制度です。
工場の空調効率化や断熱対策に活用できます。
・対象:省エネ化に取り組む中小企業・大企業(法人)
・上限額:プロジェクト規模によって異なる(例:1億円未満~数億円)
対象経費:
・高効率空調機器
・自動空調制御システム
・遮熱・断熱塗装や屋根対策
・エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
・受付期間:年度内に数回の公募(2025年度は補正予算に基づき随時)
・所管省庁:経済産業省・資源エネルギー庁(申請書類テンプレートやサポート体制あり)
参照元:省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の公募について | 資源エネルギー庁
まとめ
2025年6月から義務化された熱中症対策により、工場では法令遵守とともに従業員の安全確保が強く求められるようになりました。
構造上の暑さ要因を把握し、ビニールカーテンや遮熱材、スプリンクラー、自動制御システムなどの実用的な対策を組み合わせて導入を検討しましょう。
また、国の補助金制度を活用すれば、費用負担を抑えながら環境改善が可能です。
現場の安全と快適性の両立に向けて、対策を始めましょう。
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
制約理論を初心者向けにわかりやすく解説【業務改善手順の5ステップ】
2023年11月6日
-
生産工学とは?初心者向けに3つのポイントで徹底解説|日本大学生産工学部で学べることも紹介
2024年2月20日
-
工程管理の基本を3つの項目で徹底解説【工程管理表の作成方法も】
2022年3月28日
-
性能稼働率の求め方を初心者向けに解説【影響するロス3つ】
2023年10月13日
-
GMP認定で支える「安全性」!製造の信頼は工程から始まる
2025年8月27日
-
ERPとは?解決できる課題と選び方をわかりやすく解説
2025年2月27日
-
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
2025年11月28日
-
部分最適とは?メリット3つとデメリットを徹底解説!進めるポイントも
2024年10月3日
-
労働生産性を上げるには労働環境の見直しが大切【向上させる4つの方法と低い理由】
2023年9月12日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
-
2025年9月29日
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?