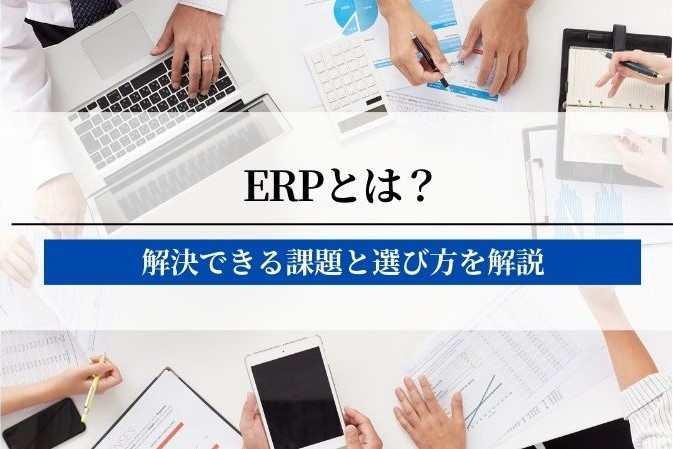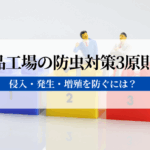GMP認定で支える「安全性」!製造の信頼は工程から始まる

製品の安全性や品質は、消費者からの信頼を得るうえで非常に大切です。
特に医薬品や化粧品、健康食品のように直接人体に影響を及ぼす製品では、製造工程そのものが品質保証の土台となります。
その「製品が安全に製造される体制が整っている」ことを示す基準が「GMP」です。
本記事では、GMP認定の基礎知識から取得の流れ、医薬品・化粧品・健康食品ごとの基準の違い、さらにはメリットや注意点まで詳しく解説します。
コンテンツ
GMP認定とは?
GMPの定義
GMPは、「Good Manufacturing Practice(適正製造規範)」の略称です。
製造工程における製品の品質と安全性を確保するための基本的な管理基準を意味します。
対象となるのは、医薬品(および医薬部外品)で、化粧品や健康食品は関連するガイドラインや任意GMPが運用されています。
GMPの目的は、製品が常に一定の品質を持ち、安全に消費者へ届けられる体制を整えることです。
そのため、製造設備の構造や作業員の衛生管理、製造工程の記録保存など、あらゆる工程が厳密に管理されます。
GMPの3原則
GMPには、以下の「3原則」があります。
1:人為的なミスの防止
作業手順の標準化や従業員教育、ダブルチェック体制などにより、作業中のミスを最小限に抑える
2:汚染・品質劣化の防止
清潔な製造環境を保ち、異物や細菌などの混入を防ぎ、製品の品質低下を防止する
3:高品質を保証するシステムの構築
記録の保管、トレーサビリティ、バリデーションの徹底など、常に品質が維持されるための仕組みを設計・運用する
この原則に基づいた管理体制が整備されているかどうかが、GMP認定の審査において重要なポイントとなります。
GMPが求められる背景
GMPが求められる最大の理由は、製品の安全性が人々の健康につながるためです。
特に医薬品や健康食品、化粧品といった製品は、体内に取り込まれたり肌に直接使われたりするため、製造過程におけるわずかなミスや異物混入が深刻な被害を引き起こす可能性があります。
こうしたリスクを未然に防ぐためには、製造から出荷までの全工程を厳格に管理する仕組みが大切です。
そこで導入されるのがGMPであり、品質と安全性を確保するためのガイドラインとして機能しています。
GMPは1968年、世界保健機関(WHO)により決議され、その後、各国で導入が進みました。
日本でも1980年に「医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(GMP省令)」が施行され、法的な枠組みとして位置づけられています。
また、現代の製造業はグローバル化や外部委託の拡大により、工程が複雑化しています。
原材料の調達先や製造所が国内外に分散する中で、一定の品質を保つためには、国際的に通用する共通の基準が必要です。
GMPは、まさにそうした背景から、信頼される製造体制を築くために非常に大切な基準となっているのです。
GMP取得の流れ
GMPの取得は、単に書類を提出するだけではありません。
例として、医薬品でGMPを取得するには「GMP適合性調査」を受ける必要があります。
以下でその流れを説明します。
事前相談から申請までの流れ
GMP適合を目指すには、まず調査機関との「事前相談」を行います。
申請の1〜2ヶ月前が目安で、対象品目や調査日程の確認、必要書類の内容などをあらかじめ調整する機会です。
その後、正式な申請書類を提出します。
提出書類には、申請書のほか、組織体制図や製造所の構造設備一覧、過去の調査結果の写しなど、多くの資料が必要です。
不備があると調査の遅延や再提出を求められることがあるため、事前にチェックリストを使って丁寧に準備しましょう。
実地調査または書面調査
申請が受理されると、調査機関による審査が始まります。
この審査には「実地調査」または「書面調査」のいずれかが実施され、製造体制や品質管理の状況が評価されます。
実地調査では、審査員が製造現場に直接訪問し、設備や製造工程、記録、作業員の対応などを確認します。
実際の運用状況が適切かどうかを現場レベルで詳細にチェックされるため、十分な準備が必要です。
一方、書面調査では提出書類をもとに審査が進められます。
現場訪問はありませんが、記載内容に不備や疑義がある場合は、追加資料の提出や再確認を求められることもあります。
どちらの調査方式であっても、指摘事項があれば改善計画書や報告書を期限内に提出し、速やかな対応が求められます。
審査結果と適合の流れ
調査が完了すると、審査結果が通知されます。
問題がなければ「適合」と判定され、結果通知書が交付されます。
ただし、調査の結果、重大な不備や改善が必要な点が確認された場合は、改善対応後に再調査等が行われる場合もあります。
審査結果の通知までには、調査終了から数週間〜数か月程度かかることが一般的です。
適合判定をスムーズに受けるためには、指摘事項への対応を速やかに行い、記録や報告の正確性を確保しておくことが重要です。
取得後の対応
適合判定後も、管理体制の維持と改善が求められます。
医薬品GMPでは、原則5年ごとに定期GMP適合性調査が行われ、引き続き適正な管理がなされているかどうかが確認されます。
工程や製品内容に変更があった場合も、その都度報告し、必要に応じて追加調査を受けなければなりません。
適合性調査は一度で終わりではなく、常に「適正な製造と品質管理」が保たれているかが見られています。
そのため、認定後も社内体制を維持・強化し続けることが、信頼のある製造体制を築く鍵となります。
医薬品・化粧品・健康食品におけるGMP基準の違い
GMPは共通の理念を持っていますが、実際には製品の性質や法的な位置づけに応じて運用基準が大きく異なります。
ここでは、医薬品・化粧品・健康食品それぞれに適用されるGMPの特徴を解説します。
医薬品GMP:法令による厳格な基準
医薬品におけるGMPは、薬機法に基づく「法的義務」として位置づけられています。
厚生労働省が定める「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」に準拠しなければ、そもそも製造や販売の許可が下りません。
この基準は非常に厳格であり、製造設備の設計や構造、作業手順の標準化、記録の保存体制、作業員の教育体制など、多岐にわたる要件をクリアする必要があります。
また、新規製品の製造時や製造施設の変更時には、PMDA(医薬品医療機器総合機構)による適合性調査も実施されます。
命に関わる製品である以上、GMP遵守は絶対条件であり、その重要性は他の分野と比べても群を抜いています。
参照元:e-GOV法令検索|医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
化粧品GMP:ISO22716に基づく自主基準
化粧品に関するGMPは、法的義務ではなく、ISO22716という国際ガイドラインに基づいた「自主基準」として運用されています。
あくまでも取得は任意ですが、品質の安定性や消費者からの信頼を高めるために、取得を目指す企業が年々増加しています。
ISO22716では、製造工程の記録、清掃管理、従業員の衛生管理、苦情処理や製品の追跡性など、品質と安全性を確保するための一連のルールが体系化されています。
特に化粧品は肌に直接触れる製品であり、安全性に対する消費者の意識が高い分野です。
GMPを導入することで、クレームの低減や流通先からの評価向上にもつながるため、ブランド価値の向上策として活用されています。
健康食品GMP:第三者機関による任意認証
健康食品分野では、GMP認定は法的義務ではなく「任意の制度」として運用されています。
現在、日本国内では「公益財団法人 日本健康・栄養食品協会」や「一般社団法人 日本健康食品規格協会」が、GMPの第三者認証を行っています。
この分野におけるGMPは、製品のばらつき防止、異物混入の防止、衛生管理体制の確保など、食品としての品質と安全性を高めるためのガイドラインに基づいています。
特にサプリメントや機能性表示食品などは、消費者が安全性を重視する傾向があるため、GMP認定の有無が商品選びの判断材料になるケースも少なくありません。
メーカーにとっても、流通業者や取引先に対するアピール材料として有効です。
GMP認定のメリット
GMP認定を取得することは、単なる「品質の証明」にとどまりません。
製造業者にとっては、企業の信頼性向上やビジネスチャンスの拡大にもつながる取り組みです。
ここでは、GMP認定によって得られるメリットを3つ紹介します。
品質と信頼性の向上
GMPの特徴は、製品が常に一定の品質で、安全に製造されていることを保証できる点にあります。
原材料の受け入れから製造、出荷までの各工程は、あらかじめ標準化されています。
業務はすべて手順書に基づいて進められるため、人為的なミスや品質のばらつきを抑えることが可能です。
こうした体制が整っていることで、消費者や取引先からの信頼を得やすくなります。
さらに、クレームやリコールのリスクを軽減できれば、結果としてブランド価値の維持にもつながります。
単に「製品が良い」だけではなく、「適切に管理されている製品である」ことが、企業の信用を支える要素になるのです。
海外輸出への対応力強化
GMP認定を取得することで、製品の海外展開における対応力が向上します。
GMPは「製品の安全性・衛生・品質が適切に管理された製造体制であること」を示す国際的な基準であり、多くの国や地域で重要視されています。
特に医薬品や健康食品などでは、輸出先の規制当局がGMP基準の適合性を確認するため、認定取得の有無が輸出の可否を左右する場合があります。
また、国際的に調和されたGMP基準として「PIC/S(医薬品査察協定・医薬品査察共同スキーム)」に対応していることも、取引をスムーズに進めるうえで有利に働きます。
海外展開を視野に入れている企業であれば、GMP認定の早期取得は競争力強化につながる大切な施策といえるでしょう。
競合他社との差別化
製品の質に加えて、製造プロセスの透明性や管理体制が問われる今、GMP認定は他社との差別化要因としても有効です。
たとえば、同じような製品を扱っている企業が複数ある中で、「GMP認定工場で製造された製品」という事実は、消費者に安心感を与える大きな要素になります。
また、取引先にとっても、認定の有無は選定基準の一つです。
特に大手企業や海外バイヤーほど、取引の前提条件として品質保証体制を重視する傾向があります。
GMP認定は、こうした市場や取引における信頼を獲得するための、確かな「証明書」となるのです。
まとめ
GMP認定は、製品の品質と安全性を確保するための基準で、医薬品・化粧品・健康食品など人体に関わる製品が対象です。
医薬品では取得が法的義務ですが、化粧品や健康食品では自主基準や任意認証として運用されています。
取得までには、事前相談、申請、実地または書面による調査、必要に応じた改善対応など、複数のステップを踏む必要があります。
さらに、認定後も継続的な管理体制の維持が求められることから、単なる一時的な対応ではなく、長期的な品質管理の取り組みが大切です。
GMP認定を取得することで、製品の信頼性向上や海外輸出への対応力の強化、さらには競合との差別化といった多くのメリットが得られます。
製造体制をより強化し、市場での信頼を高めたいと考えているなら、GMP認定の取得は、信頼される製造体制を築くための有効な手段のひとつです。
まずは、自社の製品がどのGMPに該当するのかをチェックするところから始めてみませんか?
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
業務改善の事例7個【進めるときの注意点や気づきの重要性】
2022年9月26日
-
製造業の効率化を妨げている原因5つ!それぞれの改善法も紹介
2023年1月25日
-
効率アップに欠かせない5つの方法!作業効率をアップさせる改善事例
2023年2月27日
-
製造管理システムとしてMESを導入するメリット4つ|生産管理システムとの違いも解説
2024年1月15日
-
業務改革プロジェクトを成功に導くコンサルタントの役割と活用ポイント
2021年6月28日
-
ERPとは?解決できる課題と選び方をわかりやすく解説
2025年2月27日
-
工程管理の基本を3つの項目で徹底解説【工程管理表の作成方法も】
2022年3月28日
-
業務改善で問題点の洗い出しをする方法3つ!重要な理由と注意点もご解説
2022年3月3日
-
仕事を効率化するのに大切な考え方3つ【意外な方法】
2023年2月27日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
-
2025年9月29日
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?