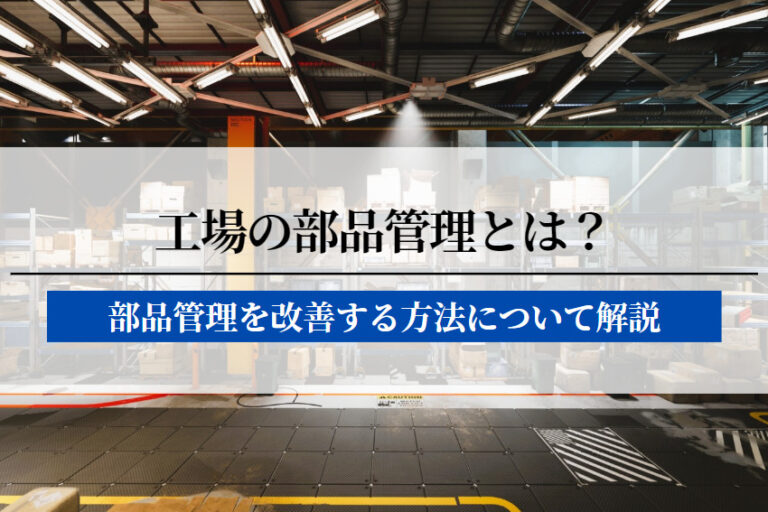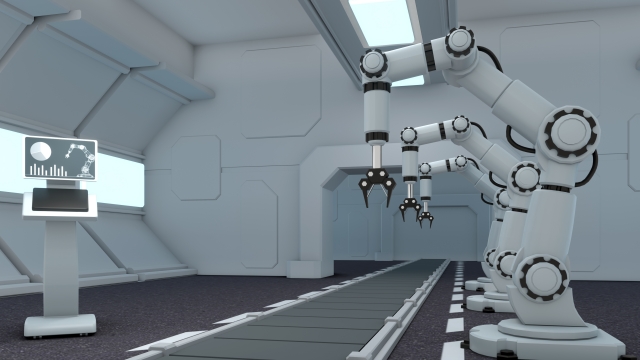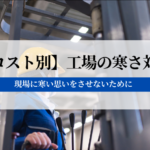生産工学とは?初心者向けに3つのポイントで徹底解説|日本大学生産工学部で学べることも紹介

生産工学とは、生産性の向上や品質の向上を目的とした工学分野です。製造業における、生産量と質に関わる技術であるともいえます。生産工学は経営工学(インダストリアルエンジニアリング)と混合されがちですが、厳密には違いがあります。
生産工学は、デザインや製造のための工程や装置の開発など、新しいものを作り出すことを主眼にしているのが特徴です。一方、経営工学は、既存の工程・設備を詳細に分析して改善することを主に対象としています。今回は、生産工学とは何か、初心者向けに3つのポイントで徹底解説します。
日本で唯一の生産工学部がある大学「日本大学生産工学部」で学べることも紹介するので、興味のある方はご参考にしてみてください。
コンテンツ
生産工学とは生産の質と量に関わる技術のこと
生産工学とは、主に製造プロセスや生産システムの設計・改善・管理に焦点を当てた工学の分野です。わかりやすくいうと、生産の質と量に関わる技術のことで、デザインや製造のための工程や装置の開発など、新しいものを作り出すことを主眼にしている特徴があります。
生産工学では、以下のような技術や知識が研究されています。
- 効率的な生産方法
- 製造プロセスを最適化する方法
- 生産設備の設計や運用
- 生産ラインの管理
- 品質管理 など
生産工学の主な目的は、「生産性と品質の向上」や「コスト削減」であるといえます。
生産工学を初心者向けに3つのポイントで徹底解説
生産工学は、「基本」「学び」「重要性」で考えると理解しやすくなります。生産工学を初心者向けに3つのポイントで徹底解説します。
生産工学の「基本」は生産ラインの仕組みについての理解を深める。
生産工学の「基本」は、生産ラインの仕組みを理解したうえで、生産ラインの最適化を図り、生産性向上を目指すことです。まずは生産ラインの仕組みを理解するために、以下の項目を中心に理解を深める必要があります。
- 製品開発のプロセスを理解する。
- 管理技術と固有技術について理解する。
- 生産現場の実務内容について理解する。
生産ラインの仕組みを理解することで、取り組むべき課題を抽出し、生産ラインにおける改善の方向性を明確にすることで、生産性の向上および品質の向上を目指します。
生産工学の「学び」は工学的知識をベースに経営・管理技術などを目指す
生産工学の「学び」は、工学的知識をベースに経営・管理技術やデザイン思考、情報工学、機械工学などを学ぶことで、生産工学の生かした生産ラインの構築を行います。
生産の質と量を維持したまま、どうすればより効率的に生産活動ができるかを考え研究し、管理・マネジメントする方法や多様な工学的知識を生かして、機械や建築、化学、情報処理など多角的な視点での実践方法を学ぶ学問であるともいえるでしょう。
生産工学の学びを行うことで、装置の開発や新たな工程を追加など多様なアプローチを実践することが可能となります。
生産工学の「重要性」は製造業の競争が激化する現代社会が背景にある
製造業の競争が激化している現代社会では、従来の生産活動のままでは、生産の質と量を維持できません。また市場のニーズ変化スピードも加速しており、迅速かつ柔軟な生産活動の対応が求められます。
生産工学の活用は製造コストの削減や製品品質の向上、出荷納期のリードタイム短縮などの効果が見込まれるため、激化する製造業の競争に対応する必要があり、今後は「重要性」が特に高まっています。
また、生産工学は熾烈な競争に製造業が勝ち残るために、多様な工学分野の知識を活用することで、製造業における生産ラインの強化などに力を発揮することが期待できるため、製造業において必要不可欠な分野になることが見込まれます。
日本大学生産工学部で学べること|唯一の生産工学部がある大学
「日本大学」は、日本で唯一の生産工学部がある大学です。
生産工学部には、以下の9つの学科が設置されています。
- 機械工学科
- 電気電子工学科
- 土木工学科
- 建築工学科
- 応用分子化学科
- マネジメント工学科
- 数理情報工学科
- 環境安全工学科
- 創生デザイン学科
工学の専門知識に加えて、経営・管理の能力が身に付くカリキュラムが用意されています。就職先や取得できる資格も多様で、生産工学の学問をさまざまな分野で活用できるでしょう。
生産工学を専門的に学びたい人、体系的に理解してキャリアに活かしたい人に特におすすめしたい学部です。
参考出典:https://www.cit.nihon-u.ac.jp/
生産工学は生産性や品質の向上を目的とした工学分野(まとめ)
生産工学は、製造業における、生産の質と量に関わる技術のことです。経営工学(インダストリアルエンジニアリング)と混合されがちですが、生産工学はデザインや製造のための工程や装置の開発など、新しいものを作り出すことを主眼にしています。
具体的には、効率的な生産方法や製造プロセスを最適化する方法、生産設備の設計や運用、生産ラインの管理、品質管理などを行います。生産工学は、工学的知識をベースに経営・管理技術の習得を目指しているのも特徴です。
生産の質と量を維持したまま、どうすればより効率的に生産活動ができるかを考え研究し、実践する学問であるともいえます。
今日のポイント
- 生産工学とは生産性の向上や品質の向上を目的とした工学分野であり生産の質と量に関わる技術のこと
- 生産工学は「基本」「学び」「重要性」の3つのポイントで考えると理解しやすい
- 日本大学生産工学部は日本で唯一の生産工学部がある大学
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
工場の部品管理とは?部品管理を改善する方法について解説
2024年12月24日
-
工場の自動化に成功した企業の事例5つ【導入メリットやデメリット】
2022年6月27日
-
スマートファクトリーとは?簡単に5つの事例を交えながら紹介|ロードマップも解説
2023年7月3日
-
仕事を効率化するのに大切な考え方3つ【意外な方法】
2023年2月27日
-
3S活動とは整理・整頓・清掃のこと【進め方や事例】
2023年12月12日
-
労働生産性を上げるには労働環境の見直しが大切【向上させる4つの方法と低い理由】
2023年9月12日
-
製造業の利益率の目安とは?計算方法5つや向上させる方法を解説!
2024年10月3日
-
労働生産性とは?計算式や向上させるメリット3つをわかりやすく解説
2022年9月29日
-
合理化と効率化の違いをわかりやすく解説|それぞれの取り組み例5つ
2024年4月5日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2026年1月29日
工場の寒さ対策をコスト別に紹介!現場に寒い思いをさせないために
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則