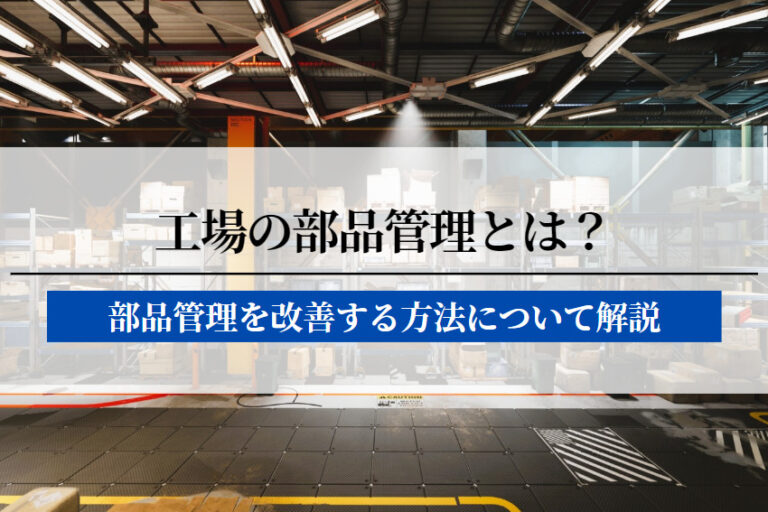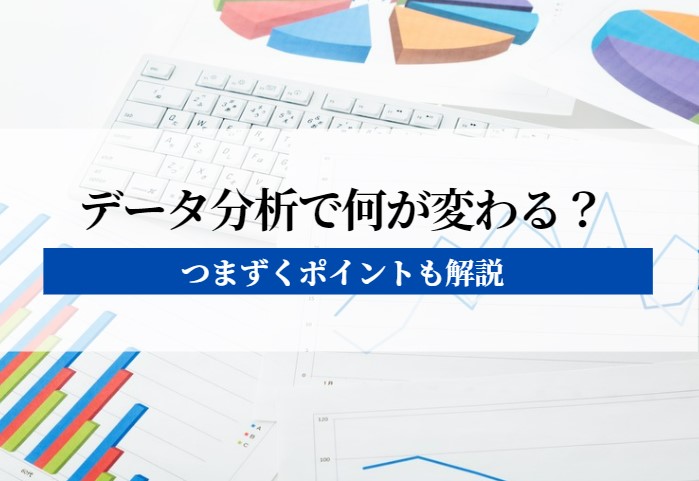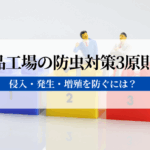個別最適と全体最適とは?両方のバランスを上手くとる方法4つとそれぞれの特徴を解説!

個別最適と全体最適は、相反する概念です。個別最適は特定の部門、工程、個人などに着目し、最適化を目指します。全体最適は組織全体をひとつとして考え、全体にとっての最適化を目標とします。個別最適は一部の最適化、全体最適は組織全体の最適化を目指す考え方です。
個別最適と全体最適は単に相反するのではなく、両方のバランスを上手くとれば、相互補完し合える関係性でもあります。今回は、個別最適と全体最適についてわかりやすく解説します。個別最適と全体最適のバランスを上手くとる方法4つも紹介するので、ご参考にしてみてください。
コンテンツ
個別最適とは
個別最適とは、組織の一部分だけに焦点をあてて最適化を目指すことです。部分的な改善を目指すため、短期間で成果が出やすい特徴があります。ここでは個別最適が求められるケースとメリット・デメリットを紹介します。
個別最適が求められるケース
製造業において個別最適が求められるケースは、組織全体を最適化する前に、まずは部分的な改善から着手する必要がある場合です。特定の工程や業務において明らかな課題や問題がみられる場合などは、業務プロセスのボトルネックと考え、まずは個別最適化を目指しましょう。
変化の激しい市場ニーズに対して、迅速な対応が求められる場合なども、個別最適のメリットであるスピード感をもって進めたほうがいいケースといえます。全体最適を目指すまえに、まずは個別最適を目指し、最終的に調整を図る手段もあります。
個別最適と全体最適のどちらを優先するか、最終的な目標が全体最適であることに変わりはありませんが、状況に応じて、臨機応変に判断することが大切です。
個別最適のメリット・デメリット
個別最適のメリットは、目の前のやるべきことを明確化しやすいことです。全体最適を目指すときによくある「何からしたらいいのかわからない…」という問題が起きにくく、小さな改善活動としてスピーディーに取り組めます。
成果が出るのも早いため、PDCAサイクルを短期間で回しながら、個別最適の精度を短い期間で高めていけます。個別最適のデメリットは、焦点をあてた部分以外に悪影響や歪みが生じる可能性があることです。
個別最適では特定の項目が最適化されることを目指すため、周りや全体への影響まで考慮しにくい懸念点があります。ミクロ視点でみれば課題や問題を解決できていても、マクロ視点でみると全体の生産性を低下させてしまっているケースが多く見受けられるため要注意です。
全体最適とは
全体最適とは、組織全体の最適化を目指すことです。全体的な改善を目指すため、成果が出るまでに時間がかかりますが、企業が最終的に目指すべき概念であるといえます。全体最適が求められるケースとメリット・デメリットを紹介します。
全体最適が求められるケース
製造業において全体最適が求められるケースは、個別最適だけでは達成できない、大きな問題や課題を解決する必要がある場合です。企業の経営状況悪化により大きな改革を迫られているような場合も、全体最適を目指す必要があります。
全体最適ではさまざまなことに配慮しながら、複数の改善活動を並行しておこなわなくてはなりません。成果が出るまでに時間と手間がかかるため、企業は個別最適を優先してしまいがちです。
しかし、個別最適だけを優先していては、一時的かつ表面的な課題や問題の解決はできても、根本的に生産性を向上させるのは難しくなってしまいます。企業が最終的に目指すべきは、全体最適です。個別最適に取り組むことも大切ですが、全体最適とのバランスをみながら進めていくことが必要不可欠であるといえます。
全体最適のメリット・デメリット
全体最適のメリットは、企業利益の向上や発展、存続に直結することです。すぐに成果を出すことは難しいかもしれませんが、全体最適が実現すれば企業全体の生産性が大きく向上します。全体を俯瞰的視点で把握しながら最適化をおこなうため、どこかに歪みが生じたり、新たな問題が発生したりするのを最低限に阻止できます。
全体最適のデメリットは、時間とコストがかかることです。長期的視点をもって、粘り強く取り組み続ける必要があります。他にも、個人間や部門間の調整の難しさや、短期的な利益とのバランスなども、デメリットとして挙げられます。
しかし、全体最適を目指すことは、企業経営にとって必要不可欠です。経営層は全体最適を目指す重要性をしっかりと理解し、積極的に推進していくことが求められます。
個別最適と全体最適のバランスを上手くとる方法4つ
個別最適と全体最適は相反する概念ですが、相互補完的な関係性でもあります。全体最適の手段の一つが個別最適であり、両方のバランスを上手くとることで、組織が最終的に目指すべき目標を効率的に達成できるようになるでしょう。
個別最適と全体最適のバランスを上手くとる方法4つを紹介します。
共通の目標を掲げる
個別最適と全体最適のバランスを上手くとるためには、共通の目標を達成する事が必要不可欠です。共通の目標は、全体最適の目標であるともいえます。個別目標は、全体最適を達成するための手段であるからです。
共通の目標は忘れず常に意識できるように、可視化し共有する機会を大切にしましょう。最終的に共通の目標に向かって進むことができれば、個別最適によって全体最適が大きく阻害されることはなくなるでしょう。
情報共有を強化する
個別最適を進めるときは、個人と部門、経営層と従業員の間での情報共有の意識を高く持つことが大切です。情報共有が適切におこなわれていれば、個別最適の取り組みが暴走してしまうことを防ぎ、全体最適を達成するために調整ができます。「なぜ、その改善活動が良くないのか」の理由もお互いに理解しやすくなるため、トラブルなども防げるでしょう。
個別最適と全体最適それぞれのKPIを設定する
KPIとは、ビジネスにおける目標に対する達成度合いを評価するための指標のことです。目標の達成度合いを、数値で定量的に算出できるメリットがあります。KPIは個別最適と全体最適、それぞれで設定することが大切です。
個別最適のKPIを設定するときは、周りに悪影響や歪みを与えないか、全体最適を阻害しないかを考慮しながら、無理のない現実的な数値にするようにしましょう。全体最適のKPIは、個別最適が及ぼす影響まで考慮し、企業にとって成果が高いといえる目標の数値を設定することが重要です。
組織文化の醸成を目指す
個別最適と全体最適のバランスを上手くとるためには、経営層と従業員が全体最適の重要性を理解できるような、組織文化の醸成を目指すことが大切です。組織文化が醸成されていないと、従業員は個別最適を優先してしまい、全体最適のために調整をしないといけない理由がわからなくなってしまいます。
経営層も個別最適の改善活動対応に追われ、全体最適という最終目的を見失ってしまうかもしれません。経営層も従業員も個別最適と全体最適の違いを理解し、共通の最終目的・目標に向けて進んでいけるような組織を目指しましょう。
個別最適と全体最適は相互補完の関係性(まとめ)
個別最適と全体最適は相反する概念ですが、相互補完の関係性でもあります。企業が最終的に目指すべきは、全体最適の実現です。個別最適は、その手段として機能していなくてはなりません。
個別最適を進めるときは、周りや全体最適への影響を考えることが大切です。ただし、急な対応が求められる場合などは、個別最適を優先したほうがいいケースもあります。重要なのは個別最適と全体最適、両方の違いと関係性を理解し、臨機応変に対応することです。
組織内では経営層と従業員が共通の認識と目標意識をもって、最終的には全体最適を目指せるよう、バランスをとりながら改善活動をおこなっていきましょう。
今日のポイント
- 個別最適と全体最適は相反する概念であり、相互補完の関係性もある
- 個別最適とは組織の一部分だけに焦点をあてて最適化を目指すこと
- 全体最適とは組織全体の最適化を目指すこと
- 個別最適と全体最適のバランスを上手くとる方法4つは「共通の目標を掲げる」、「情報共有を強化する」、「個別最適と全体最適それぞれのKPIを設定する」、「組織文化の醸成を目指す」こと
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
稼働率と可動率の違い|計算式と数値を上げる方法4つ
2023年11月6日
-
工場の部品管理とは?部品管理を改善する方法について解説
2024年12月24日
-
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
2025年12月16日
-
労働生産性を上げるには労働環境の見直しが大切【向上させる4つの方法と低い理由】
2023年9月12日
-
データ分析で製造業の何が変わる?つまずくポイントも解説
2025年3月24日
-
QC7つ道具を初心者向けに解説!覚え方や使い方を5ステップで紹介
2022年7月4日
-
設備管理が製造業において重要な理由3つ|工場での仕事内容や保全管理の基本
2022年7月15日
-
工程管理システム導入で期待できる2つのこと|工程管理の基本と主な機能
2022年1月17日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
-
2025年9月29日
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?