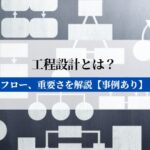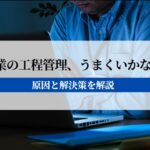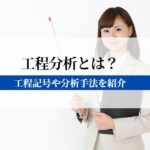工程管理と進捗管理の違いは2つ!基本的な流れと方法を解説

工程管理と進捗管理は混合されがちですが、実は内容や役割に大きな違いがあります。どちらも製造現場に欠かせない必要不可欠な管理項目でありますが、意味を混合してしまうと業務に支障が出てしまいます。工程管理と進捗管理、それぞれの違いを理解したうえで、きちんと製造現場をコントロールしていくことが大切です。今回は、工程管理と進捗管理の違い2つについて解説します。
工程管理と進捗管理の違いがわかれば、製造現場の課題や問題の改善を目指すときに、適切な取り組みができるようになります。製造現場を管理する立場や状況になったときに、自身の管轄を明確にできることもメリットです。それぞれの基本的な流れも紹介するため、ご参考にしてみてください。
コンテンツ
工程管理と進捗管理の違い2つ
工程管理と進捗管理が混合されがちな理由は、どちらも納期内に生産目標を達成することを重視している点にあります。共通の目的があるのは事実ですが、その管理方法や内容には少し違いがあります。ここでは工程管理と進捗管理の違いについて2つ紹介します。
管理している範囲
工程管理と進捗管理の最大の違いは、管理している範囲にあります。工程管理とは、効率的に生産目標を達成できるように、労働力・設備・資材などを幅広く管理することです。生産工程全般を管理範囲とするため、生産計画の立案から実施、評価、改善案の作成まで幅広く行います。
一方、進捗管理とは、業務が滞りなく計画通りに進んでいるかを管理することです。主にスケジュール管理がメインの役割で、作業の遅れなどが生じていないかを常に把握する必要があります。具体的には工程管理の方が管理する範囲が広く、進捗管理はその中に含まれている、狭義の管理方法であるともいえます。
業務内容や役割
工程管理も進捗管理も、計画立案や実施をしながら、生産工程の調整をする点は同じです。しかし、それぞれを細かく見てみると、業務内容や役割に違いがあることがわかります。特に工程管理で重視しているのは、各工程が問題なく進行しているかどうかや、過不足なく生産されているかという点です。
トラブルがあれば、原因究明や改善案の立案・実施まで行います。それに比べて進捗管理はスケジュール通りに生産が進んでいるか、納期遅れの可能性がないかを、主に管理することが目的です。
生産工程の見直しや改善案の立案まで深く踏み込むことは少なく、スケジュール管理とタスク配分の見直しに重点をおいていることが特徴です。
工程管理の基本的な流れ
工程管理では、生産工程における広い範囲を管轄します。計画の立案と実施に終わらず、評価や改善案の作成、新たな計画実施にまで取り組む点がポイントです。ここでは工程管理の基本的な流れを紹介します。
計画立案
ここでの計画立案とは、データを活用して生産前の計画を練ることです。会社の状況、顧客のニーズ、納期などさまざまなデータを基に、工場でいつ何をどれくらい生産するのか計画を立てます。計画に無理があったり曖昧な内容であったりすると、製造工程で何らかのトラブルや問題が生じる可能性が高くなります。
最初のステップである計画立案は、客観的なデータを採用して、慎重に取り組まなければなりません。
計画実施
計画実施の段階で大切なのは、前提条件として全てが計画通りに上手くいくことはありえないという考え方です。想定外のトラブルや問題が生じるのは当然のことであり、その都度対処や改善につなげることが、工程管理の役割でもあるからです。改善案の立案に役立つように、普段から問題を種類ごとに整理して記録しておくようにしましょう。
評価と改善案の作成
計画に対してどのくらい予定通り進められたか、何が問題となったのかを分析・評価します。ポイントは、生じた課題や問題を誰でも理解できるように、可視化して共有することです。課題や問題の原因まで可視化することで、効果的な改善案の立案が現場でできるようになります。
また、重要なのはスケジュール以外の観点でも、評価を行う必要があることです。スケジュール通りに生産工程が進んでいたとしても、不良品の発生率が高いなど品質が安定していなければ、意味がありません。計画通りに実施できたかどうかだけでなく、品質や作業者の労働環境などにも幅広い視点で目を向けるようにしましょう。
新たな計画実施
評価の結果を参考にしながら改善案を取り入れて、新たな計画を立案・実施していきます。工程管理の流れで重要なのは、計画から改善までを繰り返し実践することです。そのためPDCAサイクルを回し続けることが、工程管理の精度を上げ、納期内に生産目標を達成するという目的遵守につながります。
工程管理のポイントまとめ
- 最初のステップである計画立案では客観的なデータを採用して、現実的な計画を慎重に立てる
- 全てが計画通りに上手くいくことはありえないため、その都度対処や改善につなげることが重要
- 評価と改善案の作成では、スケジュール以外の観点(品質や労働環境)にも目を向けること
- 工程管理の流れで重要なのは、PDCAサイクルを回しながら実践し継続していくこと

進捗管理の基本的な流れ
進捗管理では、主にスケジュール管理を行います。現状把握と目標設定の後に作業時間と必要期間を推定し、タスクの割り当て、スケジュール調整をしていきます。ここでは進捗管理の基本的な流れを紹介します。
現状把握と目標設定
まずは業務がどこまで完了しているのか、納期に対してどのくらいの余裕がありそうなのかなど、スケジュールについての現状把握を行います。現状のどこに何の問題があるのかを浮き彫りにすることで、明確な目標設定ができるようになります。目標設定をするときは曖昧な表現ではなく、日時や目標生産量などを数値で定義し、可視化するように心掛けましょう。
作業時間と必要期間の推定
目標設定が完了したら、作業時間と必要期間を推定します。ポイントは、工程毎に細かく洗い出して計画を立てることです。各工程におけるタスクを細かく書き出し、起こりうるトラブルについてのリスクを事前に考慮できると、余裕のあるスケジュール設定が可能になります。
タスクの割り当て
スケジュール通りに計画を進めていくために、タスクの割り当てを行います。従業員の能力や労働時間に合わせて、効率的なタスク配分を実施しましょう。
ただし、効率だけを重視すると、特定の従業員に負荷がかかりすぎたり、想定外のトラブルが発生したときに、対処ができなくなったりする可能性があります。
タスクの割り当てはバランスを見ながら、無理のないように進めることが重要です。
定期的なスケジュール調整
進捗管理では、状況に応じて定期的なスケジュール調整も大切な役割です。こまめに進捗状況を確認してスケジュール調整を行うことで、トラブルや問題を最小限に抑え、軌道修正ができるようになります。進捗管理担当者は、1週間毎や1ヶ月毎に定期報告ができると理想的です。
進捗管理のポイントまとめ
- 現状把握と目標設定は主観的に曖昧に行うのではなく、日時や目標生産量などを数値で定義し、可視化すること
- 作業時間と必要期間の推定は工程まで洗い出して余裕を持ったものにする
- タスクを割り当てるときは効率だけを重視せず、特定の従業員に負荷がかかりすぎないよう注意する
- 進捗管理では定期的に進捗状況を確認してスケジュール調整を行うことで、トラブルや問題を最小限に抑えられる効果がある
工程管理と進捗管理は管理する範囲と役割が違う(まとめ)
工程管理と進捗管理は、同じ意味を持つものとして誤解されているケースが、多く見受けられます。どちらも納期内に生産目標を達成するという、共通の目的があることは事実です。
工程管理と進捗管理の違いは、管理している範囲と重きをおいている業務内容や役割にあります。工程管理では効率的に生産目標を達成できるように、労働力・設備・資材などを管理しますが、進捗管理はもう少し管轄が狭くなります。
進捗管理ではスケジュール通りに生産が進んでいるか、納期遅れの可能性がないかを主に管理することが目的であり、生産工程の見直しや改善案の立案まで深く踏み込むことはあまりありません。工程管理の方が管理する範囲が広く、進捗管理はその中に含まれている、狭義の管理方法でもあります。
今日のポイント
- 工程管理と進捗管理の違い2つは「管理している範囲」と「業務内容や役割」
- 工程管理の基本的な流れは生産計画の立案と実施→評価と改善案の作成→新たな計画実施
- 進捗管理の基本的な流れは現状把握と目標設定→作業時間と必要期間の推定→タスクの割り当て→定期的なスケジュール調整
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
生産性を上げるために個人が取り組める3つのこと|経営者目線での施策も紹介
2022年11月9日
-
製造業の仕事はAI導入でなくなる?今後の動きと活用事例6選
2024年3月4日
-
工場の稼働率を上げるには?有効な方法3つと計算式の求め方や目安を解説
2023年10月13日
-
稼働率と可動率の違い|計算式と数値を上げる方法4つ
2023年11月6日
-
業務改革(BPR)の進め方と成功のポイント3つ【業務改善との違い】
2024年1月15日
-
改善点とは?製造業における意味と洗い出すときに必要な7つの視点
2023年5月23日
-
生産性を改善する方法5つ【取り組むべき理由や進めるうえでの注意点】
2022年12月1日
-
業務改善のためのコンサルティングとは?製造業の経営課題の解決はあおい技研へ
2021年6月28日
-
コスト削減の事例10選!製造業でのネタ出しにもおすすめ
2023年6月30日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年6月30日
産業用ロボットとは?サービスロボットとの違いや種類、導入するメリットを解説
-
2025年6月30日
工場の省人化に取り組むメリットを解説!具体的なステップと事例をご紹介
-
2025年6月30日
【産業用ロボット】主要メーカーの市場シェアはどれぐらい?市場規模などわかりやすく解説
-
2025年5月28日
事例から学ぶ工場の安全対策!製造業の労災件数も紹介
-
2025年5月28日
ベンダーコントロールとは?定義やToDoを解説
-
2025年5月28日
外部コンサルタントとは?内部との違いやメリット・デメリット
-
2025年4月25日
勘と経験に頼らないモノづくりとは?製造業10社のデータ活用事例を紹介
-
2025年4月25日
工程設計とは?フロー、重要さを解説【事例あり】
-
2025年4月25日
製造業の工程管理、うまくいかない?原因と解決策を解説
-
2025年3月24日
工程分析とは?使われる記号や手法、改善ポイントを解説