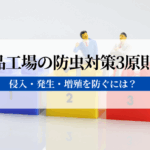工場の生産性、どうやって測る?指標や向上するための方法を解説
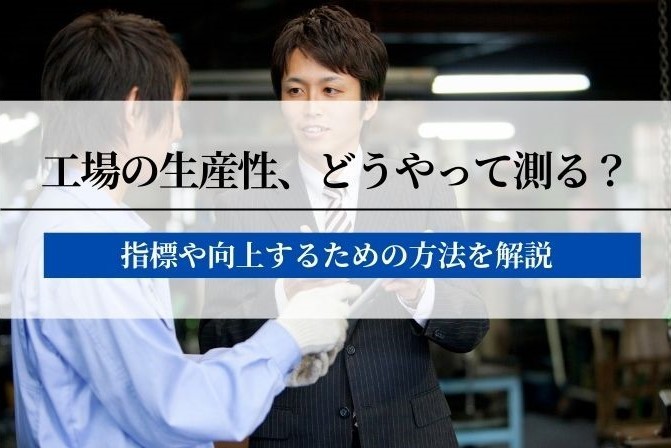
限られた人員と高騰するコストの中で、いかに効率的にモノを作るかは工場にとって切実な課題です。
生産性を高めることのメリットはわかっていても、実際に向上させるのはなかなかに難しいもの。
今回の記事では、工場の生産性を向上するために、その背景や測り方、手法などを解説します。
コンテンツ
工場の生産性向上が求められる背景
工場における「生産性向上」は、利益を増やし、競争力を維持するために欠かせない要素です。
製造業を取り巻く環境は年々厳しくなり、人手不足や原材料費の高騰、エネルギーコストの上昇などの課題が山積みです。
こうした状況の中で、従来と同じやり方では利益を確保するのが難しくなっています。
そのため、「より少ない資源でより多くの価値を生み出す」ことが求められているのです。
生産性が高い工場とは、無駄が少なく、限られたリソースを最大限に活用できる工場のことです。
例えば、同じ人員と設備で生産量を増やしたり、同じコストで品質を向上させたりできれば、生産性が向上したと言えます。
利益の増加だけでなく、納期の短縮や従業員の負担軽減など、多くのメリットを得られます。
逆に生産性が低い工場は、余計なコストがかかり、競争力を失う原因となります。
例えば、作業の非効率さが原因で納期が遅れると、顧客の信頼を失うリスクが高まります。
また、不良品の発生が多ければ、手直しや廃棄に余分な時間とコストがかかり、利益が圧迫されます。結果として、従業員の負担が増し、労働環境の悪化にもつながるでしょう。
このように、工場における生産性向上は、単なる利益の拡大だけでなく、企業の持続的な成長や従業員の働きやすさにも影響を与える重要な取り組みです。
では、そもそも「生産性」とはどのような概念なのでしょうか?
次の章では、生産性の定義とその指標について見ていきます。
生産性とは? 指標と基本の考え方
生産性とは、投入したコスト(人件費・設備・時間など)に対して、どれだけの生産成果を得られたかを測る指標です。
工場の生産効率を向上させるためには、現状の生産性を正しく把握し、どの部分に無駄があるのかを明確にすることが重要です。
そのために、以下のような代表的な指標が活用されます。
生産量を基にした生産効率
生産効率 = 実際の生産量 ÷ 理論上の最大生産量 × 100(%)
この指標では「本来の能力に対して、どれだけ効率よく生産が行われたのか」を評価できます。
※実際の生産量:工場で実際に生産できた製品の数量
※理論上の最大生産量:設備や作業時間をフル活用した場合に達成可能な生産量の最大値
稼働時間を基にした生産効率(可動率)
生産効率(可動率) = 実際の稼働時間 ÷ 本来稼働すべき時間 × 100(%)
機械や設備の生産効率を、稼働時間という軸で評価する指標です。
本来稼働すべき時間が8時間だった場合、実際の稼働時間が6時間なら、可動率は75%になります。
1人あたりの生産効率
生産効率(1人あたりの出来高)= 出来高数 ÷ 人数
従業員の作業効率を測る際に用いる指標です。
例えば、10人の作業員で1日100個の製品を生産した場合、1人あたりの生産効率は10個/人となります。
特に手作業が多い工場や組立工程では、1人あたりの生産量を最大化することが全体の生産効率向上につながります。
工場の生産性を上げるための手法
ムダを削減する
ムダをなくし、生産ラインの効率を最大化することは、生産性向上の基本です。
代表的な手法を紹介します。
トヨタ生産方式(TPS)
【ジャストインタイム(JIT)】
トヨタ生産方式の中核となる概念で、「必要なものを、必要な時に、必要な量だけ生産する」ことを徹底する手法です。
過剰な在庫を持たず、部品調達や生産を最適化することで、コスト削減と生産性向上を実現します。
【7つのムダ】
トヨタ生産方式では、生産工程の中に潜む「ムダ」を徹底的に排除することが重要視されています。
「7つのムダ」と呼ばれる以下の要素を削減することで、効率的な生産が可能になるという考えです。
1. 在庫のムダ → 余計な在庫はコストでしかない。要らないものは仕入れない。
2. 動作のムダ → 何回も同じ場所に行ったり来たりしてるなら、動線を変えたほうがいい。
3. 待ち時間のムダ → 部品待ち、前工程の遅れ。これが減れば作業がスムーズになる。
4. 加工のムダ → 必要以上の手間をかけてないか?そもそもその作業、必要?
5. 運搬のムダ → 物の移動が多いと時間を浪費する。配置を最適化すべき。
6. 作りすぎのムダ → 「とりあえず多めに作る」はリスクでしかない。
7. 不良品のムダ → 不良品が出る時点で、それまでの工程が無駄になる。
5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
作業環境の改善は、生産効率の向上に直結します。
5S活動を実践することで、工場内のムダを減らし、作業の流れがスムーズになります。
1. 整理:要らないものを捨てる
2. 整頓:必要なものをすぐに取れるように配置する(探す時間=無駄)
3. 清掃:機械の故障を防ぎ、作業効率を上げる(掃除すれば異常に気づく)
4. 清潔:綺麗な状態を維持する
5. しつけ:ルールを定め、継続的に実施する
デジタル技術を活用する
工場の生産性を上げるためには、「人がやるべきこと」と「人がやらなくてもいいこと」を分けることが大切。
デジタル技術を導入する最大の目的は、「人がやらなくてもいいこと」を機械に任せることにあります。
IoT(モノのインターネット)
IoTを活用すれば、工場の設備がどの程度稼働しているか、どこに異常があるのかをリアルタイムで把握できます。
設備の停止時間の減少、予知保全(故障する前に対応できる)、作業効率の可視化といったメリットがあります。
ロボットによる自動化
ロボットやAGV(無人搬送車)を導入すると、人手不足の中でも生産ラインを維持しやすくなります。
もちろん導入コストは安くはありませんが、将来的に見れば人材にかかるコストやリスクを考えると決して高い買い物ではないかもしれません。
現場を見つめた「カイゼン」ならあおい技研
私たち「あおい技研」は、製造業に特化した業務改善コンサルティング会社です。
製鉄や組立て系産業、食品、医療機器、化学系素材など携わってきた現場は80以上。
今回ご紹介した生産性向上の手法はもちろん大切ですが、ものづくりの現場では、それぞれに違った課題や難しさがあるもの。
それなのに一律の方法だけを提案するのでは、本質的な「カイゼン」にはなりません。
あおい技研なら「現場・現物・現実」を踏まえて、データ分析を基にした仮説、そこから施策を打ち出せます。
貴社の現場ならではのお悩みを、ぜひご相談ください。
【実績例】
・労働生産性の向上
・工場構内の物流改善
・各種工程の分析、作業改善のご提案
・熟練作業者のノウハウ可視化、システム要件への落し込み
・製造ライン増設や工場リプレースにかかるレイアウト検討、シミュレーション
まとめ
★人手不足やコスト高騰の中で、利益確保と競争力維持には生産性の向上は必要不可欠
★生産量・稼働時間・1人あたりの出来高などの指標で現状の課題を把握できる
★改善手法には、ムダの削減(トヨタ生産方式、5S活動)やデジタル技術の活用(IoT、ロボット導入)がある
★一律の手法ではなく、現場に応じた改善策のご提案なら「あおい技研」へお任せ
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
製造業の利益率の目安とは?計算方法5つや向上させる方法を解説!
2024年10月3日
-
業務効率化でシステム導入するメリット3つ!デメリットも掲載
2023年3月20日
-
「生産性」の使い方は?低くなる原因3つと対策を徹底解説!
2022年12月19日
-
制約理論を初心者向けにわかりやすく解説【業務改善手順の5ステップ】
2023年11月6日
-
作業の効率化が進まない理由5つ!製造業における向上の事例も紹介
2023年9月12日
-
業務の見直しをする方法5つと注意点【改善ネタ・アイデア出しの参考になる】
2024年7月9日
-
3S活動とは整理・整頓・清掃のこと【進め方や事例】
2023年12月12日
-
多能工化とは?導入メリット4つと推進するうえで気をつけたいポイント
2022年6月16日
-
工場の自動化に成功した企業の事例5つ【導入メリットやデメリット】
2022年6月27日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
-
2025年9月29日
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?