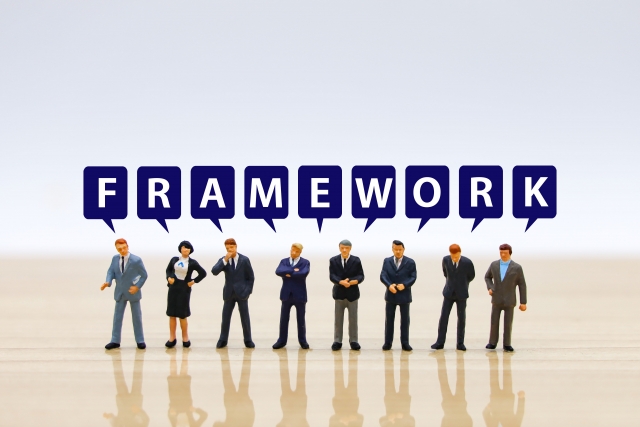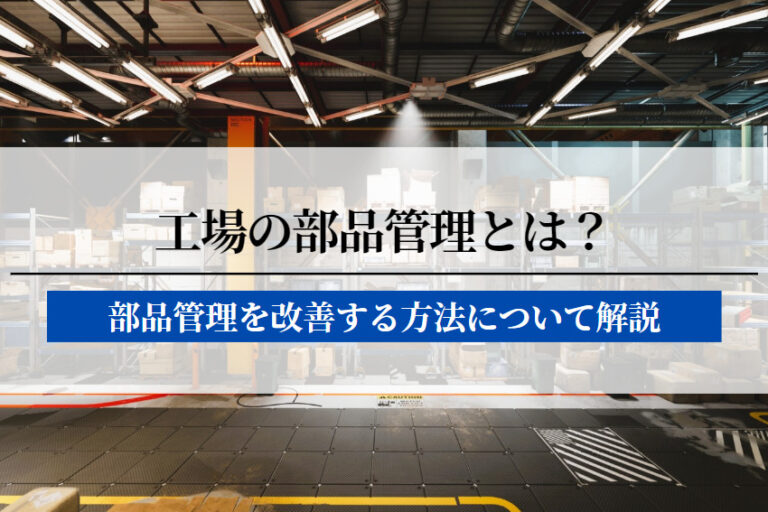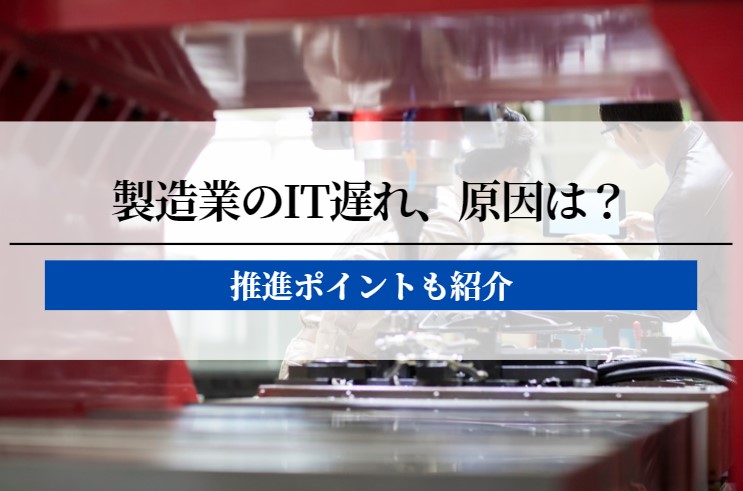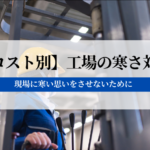製造業の利益率の目安とは?計算方法5つや向上させる方法を解説!

製造業の利益率の目安は、指標によって変わってきます。一般的に利益率というと、「売上高総利益率(粗利益率)」や「売上高営業利益率」のことを指します。売上高総利益率(粗利益率)とは、売上高から製造原価を差し引いた売上総利益のことです。最もシンプルに大まかな企業の利益率をあらわすことができます。
売上高営業利益率とは、売上高に対する営業利益を算出できる指標のことです。主に企業の主力業務の収益をあらわすことができます。利益率の目安は用いる指標によって異なるため、目的に応じて目標とする数値を設定することが大切です。
今回は、製造業の利益率の目安を解説します。製造業の利益率の計算方法5つや向上させる方法も解説するので、ご参考にしてみてください。
コンテンツ
利益率とは
利益率とは、企業がどれだけの利益を上げているかを示す割合のことです。企業の利益率を導き出すことで、経営状況を客観的に判断することができます。ただし、利益率の指標はひとつではなく、複数あります。
どの指標を参考にするべきかは、把握したい収益性によって異なるため、一概に「利益率」と考えるのは適切ではありません。自社の経営状況をどの観点から知り分析したいのか、するべきか、まずはそこから考えることが大切です。
製造業の利益率の目安
日本の製造業の利益率の目安は、「政府統計の実態窓口 中小企業実態基本調査 令和2年情報」によると21.9%となっています。ただし、この数値は利益率の「売上高総利益率(粗利益率)」の指標を用いる場合のものです。
売上高総利益率は粗利益率とも呼ばれており、売上高ー経費で総利益を算出するシンプルな指標です。製造業の利益率は全体的に、他の業種と比較すると低い傾向にあります。
製造業の利益率が低い要因としては、原材料費の高騰、人件費の増加、設備投資の必要性、市場の競争激化、技術革新の必要性などが挙げられます。
製造業が利益率を向上させるためには、コストを削減しながら技術革新などによって生産性向上を目指し、売上高を伸ばすことが大切です。
製造業の利益率の計算方法5つ
製造業の利益率の計算方法は、大きく分けて5つあります。それぞれ目的や管理点が異なるため、得たい情報を明確にしたうえで、活用する指標を判断することが大切です。製造業の利益率の計算方法5つを詳しく紹介します。
売上高総利益率(粗利益率)
売上高総利益率(粗利益率)は、売上高から製造原価を差し引く指標です。計算式は、以下のとおりです。
売上高総利益率=売上総利益÷売上高×100
売上高総利益率の指標で判断できるのは、商品やサービスの利益の規模感です。
純粋な粗利益がどれほどあるのか、大まかに把握できます。ただし、売上高総利益率は景気の影響を受けやすいため、特に前年比などと比較する場合は注意が必要です。景気の動向なども考慮し、分析するようにしましょう。
売上高営業利益率
売上高営業利益率は、営業利益から売上総利益を割る指標です。営業利益とは、企業が本業で得た利益のことを指します。計算式は、以下のとおりです。
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
売上高営業利益率の指標で判断できるのは、企業が本業でどれくらいの利益を得ているかです。企業の本業の収益性が高いかどうかを分析できます。
売上高経常利益率
売上高経常利益率は、売上高に対する経常利益の割合を示す指標です。経常利益とは、企業が通常おこなっているすべての業務で得た利益のことを指します。計算式は、以下のとおりです。
売上高経常利益率=経常利益÷売上高×100
売上高経常利益率の指標で判断できるのは、企業の通常の経営活動からどれくらいの利益を得られているかです。本業以外の経営活動からの収益性も含めて、利益率を把握・分析できます。
自己資本経常利益率
自己資本経常利益率は、企業の自己資本がどれだけの純利益を生み出したかを示す指標です。計算式は、以下のとおりです。
自己資本経常利益率=当期純利益÷自己資本×100
当期純利益とは、事業年度の最終的な利益のことです。自己資本経常利益率の指標で判断できるのは、企業が自己資本を効率良く活かして収益を得られているかです。
総資本経常利益率
総資本経常利益率は、企業の総資本に対する経常利益の割合を示す指標です。
計算式は、以下のとおりです。
総資本経常利益率=経常利益÷総資本×100
総資本経常利益率の指標で判断できるのは、企業が総資本を効率良く活かして収益を得られているかです。
製造業の利益率を向上させる方法
製造業の利益率を向上させる方法には、さまざまな観点からのアプローチがあります。自社の課題や問題を明らかにし、優先度の高い項目から着手することも大切です。製造業の利益率を向上させる方法を解説します。
売上高を増加させる
売上高の増加は、言葉のとおり利益率向上に直結します。既存製品を改良したり、市場ニーズに合った新製品を開発したり、新たな層への営業に力を入れたり、売上高の増加を試みる方法はさまざまです。
商品やサービスの価格見直し、Eコマースの活用なども検討しましょう。売上高が増加すると、特に売上高総利益率や売上高経常利益率などの数値が向上します。
ルールを作成する
3S活動を定着化させるためには、ルールの作成が欠かせません。明確なルールがないと、整理・整頓・清掃の基準が、各従業員に委ねられてしまいます。具体的には、工具や資材の定位置や清掃の手順をルール化することから始めましょう。
コストを削減する
コストの削減も、利益率向上に貢献します。新たに何かを始めるのではなく、現状のコストを見直し、改善することで利益率向上が見込めるため、売上高の増加を目指すより取り組みやすいといえるかもしれません。
具体的には原材料の仕入れ先を変更したり、人員配置を見直したりすることで、資材コストや人件費などを削減できる可能性があります。コストを削減すると、売上高総利益率などの数値が向上します。
イノベーションを推進する
イノベーションを推進すると、企業の競争力が高くなり、利益率向上が期待できます。具体的には、最新のロボット、IoT、AIの技術を導入したり、異業種とのコラボレーションに挑戦したり、既存の製造業のやり方に捉われず試みることが大切です。
イノベーションを推進すると、現状抱えている課題や問題の解決が進み、思わぬ利益につながることがあります。イノベーションの推進は、企業力を高め、あらゆる利益率の指標の向上に貢献するでしょう。
製造業の利益率の目安は指標にとって異なる(まとめ)
製造業の利益率の目安は、一概に明示できません。なぜなら、利益率の指標は複数あり、どの指標を用いるかによって目安が異なるからです。利益率の代表的な指標には、売上高総利益率(粗利益率)、売上高営業利益率、売上高経常利益率などがあります。
どれも企業が経営活動で得た利益率を示す指標ですが、使い分けることでより詳しく分析することが可能です。他にも利益率を示す指標として、自己資本経常利益率や総資本経常利益率があります。
これらは企業の資本に対する利益率を示す指標で、資本の活用度や生み出している収益を把握できることがポイントです。製造業の利益率を分析するときは、知りたい情報に合わせて指標を選ぶ必要があります。複数の指標を用いて分析することで多面的な判断と分析ができるようになるため、全体の利益率向上に活かせるようひとつひとつ確認してみてくださいね。
今日のポイント
- 利益率とは企業がどれだけの利益を上げているかを示す割合のこと
- 製造業の利益率の目安は指標によって異なるため目的に合わせて参考にする
- 製造業の利益率の計算方法5つは「売上高総利益率(粗利益率)」、「売上高営業利益率」、「売上高経常利益率」、「自己資本経常利益率」、「総資本経常利益率」
- 製造業の利益率を向上させる方法には、売上高の増加、コストの削減、イノベーションの推進などがある
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
制約理論を初心者向けにわかりやすく解説【業務改善手順の5ステップ】
2023年11月6日
-
業務効率化でシステム導入するメリット3つ!デメリットも掲載
2023年3月20日
-
改善のフレームワーク7選|ECRSやKPTなど役立つアイデアを初心者向けに徹底解説
2023年4月17日
-
工場の部品管理とは?部品管理を改善する方法について解説
2024年12月24日
-
【産業用ロボット】主要メーカーの市場シェアはどれぐらい?市場規模などわかりやすく解説
2025年6月30日
-
業務改革(BPR)の進め方と成功のポイント3つ【業務改善との違い】
2024年1月15日
-
製造業における教育計画を立案するときの手順6ステップ!重要性と具体例
2024年9月2日
-
工場にIoTを導入してスマートファクトリー化すると解決できる課題5つ
2022年4月28日
-
製造業のIT遅れ、原因は?推進ポイントも紹介
2025年1月29日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2026年1月29日
工場の寒さ対策をコスト別に紹介!現場に寒い思いをさせないために
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則