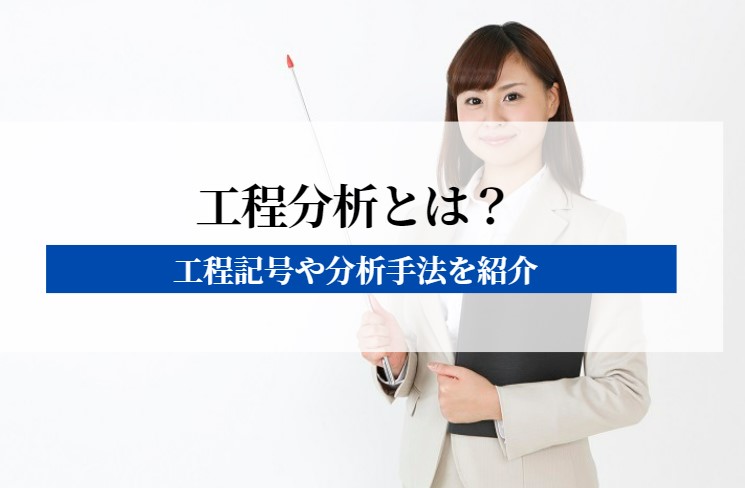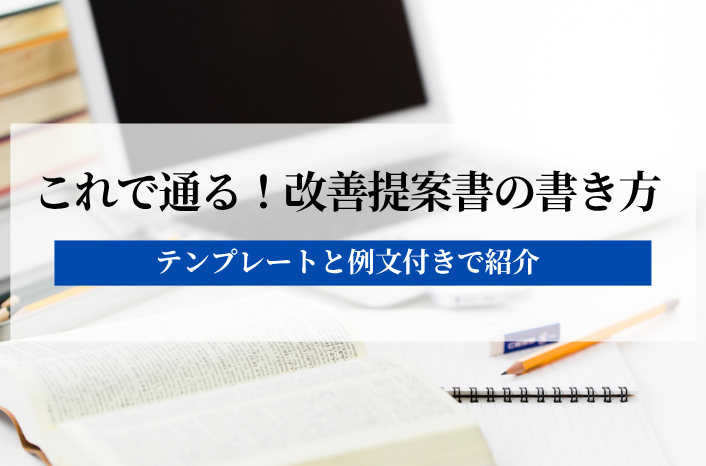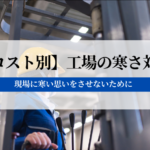食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?
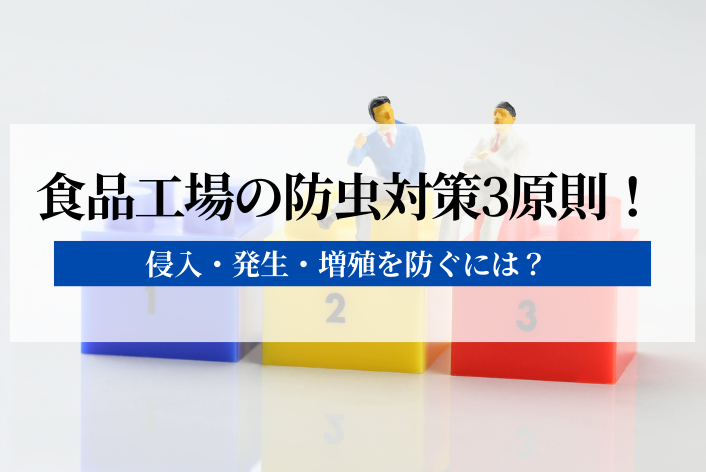
食品工場にとって、「虫対策」は永遠の課題ではないでしょうか。
たった1匹の虫が製品に混入するだけで、消費者の健康被害リスクがあるだけでなく、SNSで情報拡散をされてしまうと信頼を一夜にして失う可能性すらあります。
「うちはしっかりやっているから大丈夫」と思っていても、虫はほんのわずかな隙間から侵入し、気づかない場所で発生・繁殖するもの。
この記事で防虫対策にまつわる知識を取り上げます。
コンテンツ
食品工場における防虫対策の重要性
食品工場での防虫対策は、「食の安全」と「会社の信用」を守るためにあります。
まずは、その重要性について再認識しましょう。
健康被害を防ぐため
虫は見た目が不快なだけじゃなく、細菌やウイルスを運ぶ存在でもあります。
例えば、ハエやゴキブリは、サルモネラ菌や大腸菌などの病原菌を媒介することで知られています。汚水やごみ置き場、動物の排泄物などを経由して、汚染物質を体に付着させてやってくるのです。
そうした虫が、加熱前の食材や包装資材に触れてしまったらどうなるか。
最悪の場合、消費者がその食品を口にして食中毒を起こすリスクがあります。
特に、サラダやお菓子など「そのまま食べる」前提の製品を扱う工場では、衛生管理が命。
虫の侵入を防ぐことは、製品の品質保持ではなく、消費者の健康を守ることに直結しているのです。
品質と信頼を守るため
虫が1匹でも製品に混入すれば、それはもう「不良品」扱いです。「見た目の問題」だけで片付けられず、消費者からのクレームや、自主回収といった事態につながることも。
さらに怖いのが、今の時代の拡散力。
異物混入の投稿がSNSで拡散されれば、たった一度のミスで企業の信用はガタ落ち。
一度失った信頼を取り戻すのは、非常に困難です。「虫が出た」というだけで工場全体の管理レベルを疑われ、取引先からの信頼も揺らぐリスクがあります。
つまり、防虫対策は単なる衛生管理ではなく、会社全体の信用を守る防波堤だということです。
法令・監査対応のため
食品工場にはHACCP(ハサップ)に基づく衛生管理が義務付けられています。HACCPの項目には、「虫やネズミなどの害虫・害獣の管理」も含まれています。
つまり、防虫対策は「やっておいた方がいい」ではなく、「やらなければならないこと」なのです。
さらに、食品安全マネジメントシステムの国際規格である「ISO22000」やさらに厳しい「FSSC22000」といった食品安全規格を取得している工場では、より厳しい管理が求められます。
防虫対策が不十分だと、認証の取り消しや取引停止のリスクもあるのです。
防虫管理の「3原則」とは?
食品工場における防虫管理には、以下の3原則があります。
★侵入させない
★発生させない
★持ち込ませない・増やさない
1. 侵入させない
虫はどのように入ってくるのか?
虫の侵入経路は意外と多く、すべてを目視で管理するのは困難です。
以下のような小さな隙間から、あっという間に工場内へ入り込んでしまいます。
【侵入経路】
・開けっ放しのドアや窓
・人や物の出入り(衣服や段ボールに付着)
・通気口や排水溝などの隙間
・納品物に紛れての侵入
どうしたら入ってこないのか?
侵入を防ぐには、物理的な遮断+ルールの徹底が大事です。
虫が入り込む余地をできる限りゼロに近づける、これに尽きます。
【対策】
・ドアや窓は常時閉めるルールを徹底(自動ドアやエアカーテンの導入も有効)
・搬入口や通用口には防虫カーテン・網戸・隙間テープを設置
・排水溝や排気口にはメッシュフィルターをつけ、開口部を最小限に
・納品物(特に段ボール)は一時検品エリアを設けてチェック
2. 発生させない
虫はどんな場所が好きなのか?
虫は「エサ」「水分」「適度な温度」がそろった場所を好みます。
食品工場では以下のような場所が発生源になりがちです。
「掃除が行き届いていない場所」や「湿気がこもる場所」は虫にとって最高の繁殖地になってしまうのです。
【虫が好む場所】
・食品残渣(くず、液だれ、ゴミ)
・清掃が不十分な床や機械の裏側
・結露が発生する壁や天井まわり
・放置された段ボールや雑貨
どうしたら発生しないのか?
ここで大切なのは、清掃の習慣化と環境管理です。
「見える場所だけきれいにする」のではなく、機械の裏や天井なども定期的に点検することが発生防止には不可欠です。
【対策】
・清掃マニュアルを整備し、担当者を明確にする
・食品残渣はこまめに処理し、床や排水溝も毎日洗浄
・温湿度を適切に保つ(湿度60%以下が理想)
・不要な資材は置かない・すぐ処分する
・専門業者に頼んで定期的に点検
3. 持ち込ませない・増やさない
どのようにして持ち込んでしまうのか?増やしてしまうのか?
虫は外からだけでなく、人や物を介して工場に持ち込まれることもあります。
侵入した「1匹」をそのまま放置すると、あっという間に繁殖して、大量発生へとつながってしまいます。
【虫が持ち込まれるケース】
・作業員の衣類や靴に付着
・段ボールやパレットに虫が紛れている
・外気を吸い込む空調や換気設備を通じて侵入
・一度侵入した虫が工場内で繁殖して増える
どうしたら持ち込まない・増えないのか?
工場の入り口を「バリアゾーン」にすることが大切。
「1匹見つけたら、すでに10匹いる」と考えるぐらいでちょうど良いです。
増やさないためには、初期対応の早さと継続的な点検が大事になります。
【対策】
・出入口に粘着マットやエアシャワーを設置
・作業員の衣類や帽子は必ず指定の更衣室で着用
・段ボールは工場内に持ち込まず、内容物だけを清潔な容器に移す
・侵入が疑われる場合は、早期にトラップ・ライトで捕獲&モニタリング
食品工場によくでる虫とその対策
先ほど防虫管理の3原則をお伝えしましたが、ここではより具体的に虫の種類別の対策を紹介します。
食品工場で問題になる虫は、その行動や発生場所によって分けられます。
飛ぶ虫(飛翔性昆虫)、這う虫(歩行性昆虫)、そして原材料から持ち込まれる虫(貯穀害虫)の3つのグループに分けて紹介します。
1. 飛ぶ虫(飛翔性昆虫)
外部から光やニオイに誘われて侵入してくるタイプです。
活動範囲が広く、一度侵入されると広範囲を汚染するリスクがあります。
■ハエ類(イエバエ、クロバエなど)
・ゴミや動物のフンなど不衛生な場所を好む
・O-157やサルモラ菌といった病原菌を運ぶ代表的な衛生害虫
■コバエ類(ショウジョウバエ、チョウバエ、ノミバエなど)
・ショウジョウバエ:熟した果物やアルコール臭に集まる
・チョウバエ:厨房や水回りでよく見られる
・ノミバエ:繁殖力が高く、動物性の腐敗物などを好み、素早く動き回る
■ガ類(メイガなど)
・夜間に工場の光に誘われて侵入する
・幼虫が穀物や菓子を食害することもある
飛ぶ虫の対策
活動範囲が広く、混入リスクが高い飛翔性昆虫には「光・ニオイ・侵入経路」を意識した対策が効果的。
ポイントは「寄せつけない」「中で動き回らせない」ことです。
【対策】
・エアカーテンやビニールカーテンを出入口に設置して侵入を防ぐ
・捕虫器(UVライトトラップ)を適切な場所に配置し、誘引して捕獲する
・夜間は照明を工夫(波長を虫が寄りにくいタイプに変更、光の漏れを減らす)
・原料や製品の保管エリアでアルコール臭・果実臭を発生させない(残渣の即時廃棄、蓋つき容器の利用)
2. 這う虫(歩行性昆虫)
床や壁の隙間、配管などを通って侵入・移動し、暗く湿った場所や暖かい場所を好みます。
繁殖力が高く、気づかないうちに工場内に巣を作ってしまう危険があります。
■ゴキブリ類(チャバネゴキブリ、クロゴキブリなど)
・最も警戒すべき害虫の一つ
・あらゆる病原菌を媒介し、フンや死骸がアレルゲンにもなる
・非常に繁殖力が強く、設備の裏やわずかな隙間に潜んでいるため、根絶が難しいのが特徴
■アリ類
・砂糖やタンパク質を求めて行列を作って侵入する
・食品に群がるだけでなく、電気設備に入り込んで故障の原因になることも
■クモ、ムカデ、ダンゴムシなど
・建物の外周や壁の隙間から侵入する
・直接食品を害することは少ないが、工場内に巣を張ったり、従業員に不快感を与えたりするため衛生的な指標にもなる
這う虫の対策
ゴキブリやアリのように床や隙間から侵入するタイプには、「侵入路を塞ぐ」「巣を作らせない」こと。
「隠れ家」と「餌場」をつぶすことで、根付かせない環境づくりが大切です。
【対策】
・ドアや窓の隙間、配管周囲をシーリング材で封鎖
・排水溝には防虫トラップや蓋を設置し、常に清掃してヌメリを防ぐ
・機械や棚の下を定期的に清掃し、食品残渣を残さない
・ゴキブリ用ベイト剤やモニタリングトラップを設置して早期発見・駆除
・アリ対策としては、屋外の巣の除去や地面の割れ目の補修
3. 原材料から持ち込まれる虫(貯穀害虫)
その名の通り、小麦粉、豆類、香辛料といった貯蔵された穀物や乾燥食品に発生する虫です。
原材料の入荷時に、段ボールや原料そのものに付着して工場内に持ち込まれます。
■メイガ類(ノシメマダラメイガなど)
・幼虫が穀粉や乾燥果実、チョコレートなどを食べ、糸を吐いて巣を作る
・製品に直接混入するリスクが非常に高い虫
■甲虫類(コクゾウムシ、シバンムシ、コクヌストモドキなど)
・コクゾウムシ:米や麦などの穀粒の中に卵を産み付け、内部から食害する
・シバンムシ:小麦粉やビスケット、乾燥麺、畳など非常に広食性で、繁殖力が高い害虫
・コクヌストモドキ:製粉工場などで問題になりやすく、粉の中にまぎれて発生する
貯穀害虫の対策
貯穀害虫は原料そのものに付着して入ってくるため、持ち込ませない工夫が必要。
ポイントとなる場所は「入口」や「倉庫」です。
【対策】
・原料や資材の入荷時チェックを徹底する
・ダンボールや木製パレットは工場内に持ち込まない(専用の容器に移し替える)
・原材料は温湿度管理された倉庫で保管し、先入れ先出しを徹底
・定期的に在庫を確認し、古い原料を溜め込まない
・捕虫器やフェロモントラップで発生をモニタリングし、異常があれば早めに業者に依頼
まとめ
この記事では、食品工場における防虫対策の重要性から、管理の3原則、そして虫の種類別の具体的な対策について説明しました。重要なポイントを振り返りましょう。
★防虫対策は「安全」と「信頼」を守っている
消費者の健康被害を防ぎ、製品の品質と企業の社会的信用を守るために防虫対策は不可欠
HACCPの認証基準を遵守する上でも必須の取り組み
★防虫管理の「3原則」
・侵入させない:ドアの開閉ルール徹底、隙間を物理的に塞ぐ
・発生させない:清掃・整理整頓を徹底し、虫が好む環境をつくらない
・持ち込ませない・増やさない:人や資材に付着した虫を工場内に入れない、早期発見・駆除で繁殖を防ぐ
★虫の特性に合わせた対策
・「飛ぶ虫」「這う虫」「貯穀害虫」では、侵入経路や好む場所が異なる
・捕虫器やベイト剤、モニタリングトラップなどを適切に使い分け、それぞれの弱点を突いた対策を講じる
防虫対策に「これで完璧」という終わりはありません。
日常的な習慣や仕組みを整えて「侵入・発生・繁殖」を防ぎましょう。
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
工程分析とは?使われる記号や手法、改善ポイントを解説
2025年3月24日
-
業務改革プロジェクトを成功に導くコンサルタントの役割と活用ポイント
2021年6月28日
-
業務改善で原因分析をする手法4つ|役立つフレームワークも紹介
2024年1月15日
-
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
2025年11月28日
-
改善点とは?製造業における意味と洗い出すときに必要な7つの視点
2023年5月23日
-
製造業の効率化を妨げている原因5つ!それぞれの改善法も紹介
2023年1月25日
-
労働生産性を上げるには労働環境の見直しが大切【向上させる4つの方法と低い理由】
2023年9月12日
-
仕事を効率化するのに大切な考え方3つ【意外な方法】
2023年2月27日
-
製造管理システムとしてMESを導入するメリット4つ|生産管理システムとの違いも解説
2024年1月15日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2026年1月29日
工場の寒さ対策をコスト別に紹介!現場に寒い思いをさせないために
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則