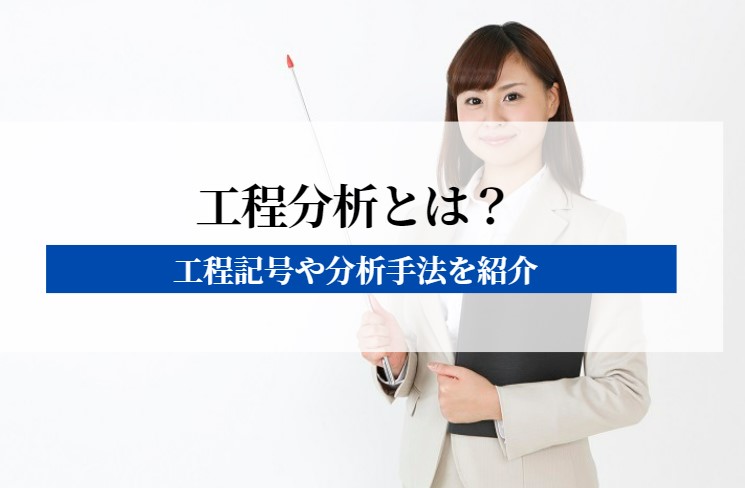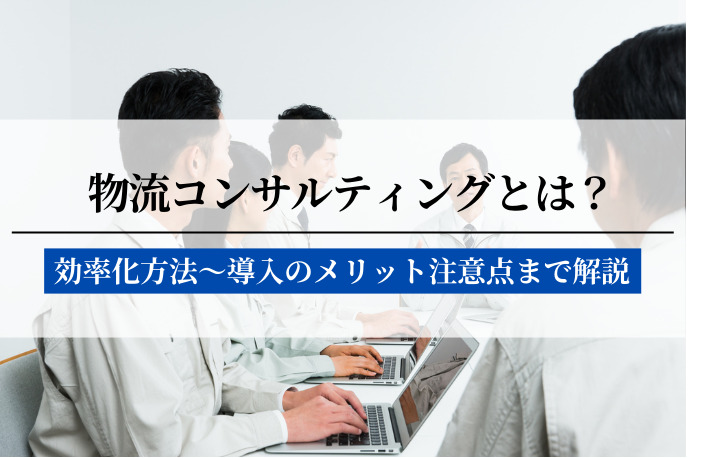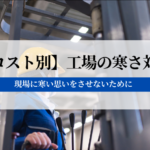効率化とは?4つのポイントで初心者向けに基本を徹底解説!

効率化とは、業務の進捗効率を向上させることです。わかりやすくいうと、同じ一定の時間内で、より多くの生産や成果を生み出せるように、工夫することとも言えます。効率化を行えば、生産性が高まり利益も大きくなるため、企業にとっては重要な取り組みの一つです。
業務が円滑に進むようになり、残業時間も削減できるため、従業員にとってもメリットがあります。今回は、効率化とは何なのか、初心者向けに4つのポイントで基本を解説します。
効率化という言葉の
- 使い方
- 高める方法
- メリット
- デメリット
をわかりやすく紹介するため、ご参考にしてみてください。
コンテンツ
効率化とは?
効率化は、多くの企業の課題となっています。少子高齢化の進む日本では、労働人口不足が深刻化しています。より少ない従業員で、より多くの生産を行うためには、効率化は欠かせない取り組みになります。
効率化の具体的な方法は、おもにムダを省いて、やり方を見直すことになります。業務に潜むムダを見つけて削減し、より合理的に作業ができるように、工夫を行います。
効率化と似た言葉に、「作業効率化」がありますが、違いはどこに特化しているかです。効率化は業務全体を対象の範囲として、複合的に非効率を解消していきます。
一方、作業効率化は「作業」の効率化に特化しており、全体像で俯瞰すると必ずしも合理的ではないケースもあるのが特徴です。作業効率化は、効率化の中に含まれている概念であり、より小さな範囲のことを指します。
効率化の基本を4つのポイントで徹底解説
効率化の有用性を知るためには、言葉の意味や高める方法、メリット・デメリットを知ることが大切です。基本を知れば、より効果的な効率化の改善案を、出せるようになります。今回は効率化の基本を初心者向けに4つのポイントで解説します。
1.効率化の使い方
効率化という言葉は、日常生活でも仕事の場でも使われます。例えば、日常生活では「家事を効率化する」ことで、手間と時間を削減し、余暇を充実させることができるようになります。
効率化は公私関わらず使われる言葉ですが、特に企業にとっては大きな意味を持ちます。なぜなら、企業の最大の目的は、顧客や市場から満足を獲得し、永続的に成長し続ける過程で社会的責任を果たすことだからです。そのためには、業務を効率的にムダなくできるよう、社内環境を整えなくてはいけません。
企業内で効率化という言葉が使われる場合の例文は、以下になります。
- 「効率化を図るために改善アイディア出しを行う」
- 「効率化を優先してノンコア業務への取り組みを一旦廃止する」
- 「業務を効率化するためにITツールの導入や新しい設備の購入を検討する」 など
主に経営層から従業員に伝えられることが多く、改善の取り組みの目的として使用されます。効率化によってムリを生じさせてしまっては意味がありません。業務内容にムリが生じている状況は、一時的には成果を高められても、長期的に見ると継続できる可能性が低くなります。
そのため効率化にて優先すべきは、企業と働く従業員が健全な状態で、生産性を高められるようにすることです。効率化によって歪が生じないように、きちんとPDCAサイクルを回しながら進めていきましょう。
2.効率化を高める方法
効率化を高める方法をステップ形式にすると、以下のようになります。
- 1.業務に潜む課題や問題を洗い出す
- 2.課題や問題(3M)を削減するための改善案を出す
- 3.改善案を実施する
- 4.改善案実施の効果検証を行う
- 5.PDCAサイクルを回しながら継続していく
大切なのは、効率化のための改善行動を一過性のものにしないことです。効率化の取り組みに成功しても、定着して継続的に維持できなければ、意味がありません。また、ある工程の効率化が実現することで、他の場所に非効率が発生する可能性もあります。効率化を高める方法を実施するときは、PDCAサイクルを回しながら、特に効果検証を意識することを忘れないようにしましょう。
3.効率化を高めるメリット
効率化を高める最大のメリットは、生産性が高くなり利益が大きくなることです。そのため企業成長と存続に直結します。効率化は企業にとってだけでなく、従業員にとってもメリットがあります。効率化が実現しているということは、結果的にムダがなく快適な作業環境であるともいえます。
業務に取り組むストレスが減り、残業時間も少なくなるなど、従業員のワークライフバランスが充実するのは大きなメリットです。企業にも従業員にも余裕が生まれ、コア業務へのリソースを増やせるため、これまでにはない新たな事業を展開させることもできるようになります。
4.効率化に取り組むデメリット
効率化に取り組むデメリットの一つに残業時間減少による従業員の収入減や、コストパフォーマンスが悪くなる可能性があることです。残業時間の減少によって従業員の収入が減ると、一般的にはモチベーションが低下してしまいます。
そのため高いパフォーマンスを維持できなかったり、離職の原因になったりすることがリスクとなります。コストパフォーマンスの悪化とは、システム導入などによる費用対効果を、十分に得られない可能性があることを指します。
システム導入などには大きな費用がかかりますが、効率化のために費用をかけるときは、費用対効果を含め、慎重に検討することが大切です。しかし、効率化を進めなければ、現状は悪くなる一方で、課題や問題は増えていきます。
残業時間減少による収入減は、効率化によって得られた利益の分配(基本支給額の増額や特別手当など)を企業が適切に行えばカバーできます。新規設備投資などによるコストパフォーマンスの悪化懸念も、効率化で得られた成果と比較すれば損失にはなっていないケースがほとんどです。
ノーリスクではありませんが、効率化に取り組むことは、長期的にみて価値の大きい試みとなります。
効率化とは業務が円滑かつ合理的に進むよう工夫すること(まとめ)
効率化とは、業務の非効率な点を洗い出して、解消していく取り組みのことです。業務や作業が円滑かつ合理的に進むように、改善案を出して実施していきます。効率化を高める方法はステップ形式で説明できますが、大切なのは一過性の取り組みにしないことです。
効率化のための工夫が定着して継続的に行われるよう、PDCAサイクルを回していくことが重要になります。効率化の取り組みによって、新たな非効率性が生じていないかにも気をつけましょう。
効率化には、残業時間減少による従業員の収入減や、コストパフォーマンスが悪くなる可能性があるなどのデメリットもあります。ただ、効率化は企業成長と存続のためには欠かせない取り組みです。得られるメリットや成果はとても大きいので、まずは小さなことから始めてみるのがおすすめです。
今日のポイント
- 効率化とは業務の進捗効率を向上させること
- 効率化を高める方法は
- 効率化という言葉は日常生活でも企業内でも使われる
- 効率化を高めるメリットは生産性が高くなり利益が大きくなること
- 効率化に取り組むデメリットは残業時間減少による従業員の収入減やコストパフォーマンスが悪くなる可能性があること
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
コスト削減の事例10選!製造業でのネタ出しにもおすすめ
2023年6月30日
-
設備管理が製造業において重要な理由3つ|工場での仕事内容や保全管理の基本
2022年7月15日
-
改善提案でネタ切れしたときの対処法3つ!参考になるトヨタの事例も紹介
2023年4月17日
-
製造業の生産管理システムの選び方|成功させるポイントもご解説
2021年12月13日
-
工程分析とは?使われる記号や手法、改善ポイントを解説
2025年3月24日
-
製造業の利益率の目安とは?計算方法5つや向上させる方法を解説!
2024年10月3日
-
生産性を改善する方法5つ【取り組むべき理由や進めるうえでの注意点】
2022年12月1日
-
物流コンサルティングとは?物流業務を効率化する方法から導入のメリット・注意点まで解説
2024年12月24日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2026年1月29日
工場の寒さ対策をコスト別に紹介!現場に寒い思いをさせないために
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則