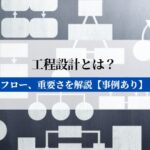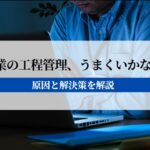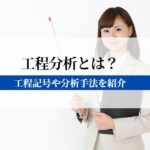労働効率とは?向上させて得られるメリット3つと計算方法・日本が低い理由を解説

労働効率とは、労働力に対してどれくらい効率良く、成果を生み出せているかを指す用語です。企業がより大きな利益を得るためには、少ない労働力で多くの成果を生み出す必要があります。労働効率は計算式で求めることができ、算出することで、自社の生産能力や課題などを浮き彫りにできるのがメリットです。
ただ、日本は労働時間が長いにも関わらず、労働効率が海外に比べて低い傾向にあります。今回は、労働効率を向上させて得られるメリット3つを紹介します。日本の労働効率が低い理由や、計算方法もわかりやすく解説するため、ご参考にしてみてください。
コンテンツ
労働効率とは?
労働効率は、「労働生産性」という言葉でも表されます。労働生産性とは、従業員1人もしくは労働時間1時間あたりが、成果を生み出すための効率を数値化したものです。
労働効率を計算すると、企業が投入している労働力に対して、どれくらい効率良く成果を生み出せているかがわかります。労働効率の良さは生産性の高さであるため、企業の利益追求や発展に直結することが特徴です。
労働効率の指標は、自社の生産能力を知りたいときや、競合他社との比較分析をしたいときなどに活用します。
日本の労働効率が低い理由
2021年の「労働生産性の国際比較」によると、日本は海外の先進国に比べて、労働効率が低い傾向にあります。
OECD加盟38ヵ国における日本の1時間あたりの労働生産性は23位、1人あたりの労働生産性は28位です。この結果は、主要先進7か国の中では最下位となっています。
参考出典:https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/report_2021.pdf
そもそも、労働効率が低い状態とは、従業員1人もしくは労働時間1時間あたりに生み出す成果が少なく、投入した労働力に対して、生産能力や利益が見合っていないことを指します。
労働効率が低いと、投資を回収できずに企業の経営状況が追い込まれたり、長時間労働によって、従業員のパフォーマンスが下がったりすることがデメリットです。日本の労働効率が、海外の先進国に比べて低い傾向にある主な理由は、次のようなものが挙げられます。
- 付加価値を生み出す力が弱い
- 一つの業務に携わる人員が多く時間をかけすぎている
アメリカやドイツと比較すると、同じ利益をあげるために投入する従業員数も労働時間も、日本は多いことがわかっています。
変化が目まぐるしいグローバル市場で、日本が労働効率を向上させるためには、付加価値を生み出すことに注力したり、最新のITツールや機械を積極的に導入して、業務の効率化を目指したりすることが課題となります。
労働効率を向上させて得られるメリット3つ
労働効率を向上させると、日本の企業が抱えているさまざまな問題や課題を解消できます。従業員の職場環境や働き方も改善できるため、企業価値も高くなることがメリットです。労働効率を向上させて得られるメリット3つを紹介します。
人員不足でも対応できる
日本では、少子高齢化による労働人口不足が深刻化しています。労働効率を向上させると、少ない従業員でも高い生産量や付加価値を生み出せるようになるため、人員不足に対応できるようになることがメリットです。
具体的には、ムダな業務をカットしたり、ITツールや機械の導入で作業を自動化したりして、労働効率を改善します。
新たに投資できる余裕が生まれる
労働効率が向上すれば、人件費を削減できるようになります。その結果、新たな投資や製品の開発が可能となるため、企業発展につながることがメリットです。労働効率の向上は、従業員にも経営陣にも余裕と恩恵を与えてくれます。
従業員のワークライフバランスが充実する
労働効率が向上すれば、従業員の労働時間も減らせます。日本では特に、労働人口不足による長時間労働が問題になっています。長時間労働が一時的に、高い生産量や付加価値を生むことはあっても、経営的には健全ではありません。
なぜなら、長時間労働は従業員の疲労蓄積によるパフォーマンス低下や、健康状態の悪化などを招くリスクが高くなるからです。これからの時代は、企業は工夫して、従業員のワークライフバランスを充実できるよう努めることが大切です。
結果的に従業員のワークライフバランスの充実は、高いパフォーマンスを発揮し、好循環を促すことにつながります。
労働効率の計算方法
労働効率には、次の2種類があります。
- 物的労働生産性
- 付加価値労働生産性
それぞれ計算式で求められるので、紹介します。
物的労働生産性
物的労働生産性とは、成果を「生産量」として算出する指標です。材料費や運送費などは考慮せず、従業員1人もしくは労働時間1時間あたりが、どれだけの生産量を生み出しているかを、シンプルに表現します。
計算式
物的労働生産性=生産量÷労働量(労働人数or労働時間)
物的労働生産性は客観的にわかりやすいため、労働効率を知りたいとき、一般的に使われる指標です。
付加価値労働生産性
付加価値労働生産性とは、成果を「付加価値(粗利)」として算出する指標です。材料費や運送費などを考慮して、従業員1人もしくは労働時間1時間あたりが、どれだけの付加価値(粗利)を生み出しているかを計算できます。
計算式
付加価値労働生産性=付加価値÷労働量(労働人数or労働時間)
生産量だけで判断するのではなく、どれだけ効率良く粗利益を生み出せているか、知りたいときに役立つ指標です。
労働効率を向上させることは企業の課題解消につながる(まとめ)
労働効率の向上は、企業の課題解消・利益追求・発展に欠かせない要素です。労働効率は計算式で算出でき、結果は自社の経営状況把握や課題、問題点の洗い出し、競合他社との比較分析に役立ちます。
日本は労働効率が海外の先進国に比べて低い傾向にありますが、付加価値の高い業務へのシフトや、最新のITツールや機械導入による業務効率化などを行えば、向上できる可能性は大いにあります。
労働効率を向上させると、労働人口不足問題に対応できたり、新たな投資をして新規事業に取り組んだりする余裕が生まれます。従業員のワークライフバランスが充実するメリットもあるため、企業価値も高くなることも大きなメリットです。
今日のポイント
- 労働効率とは労働力に対してどれくらい効率良く成果を生み出せているかを指す用語
- 日本の労働効率が海外の先進国に比べて低い理由は、付加価値を生み出す力が弱いことと、一つの業務に携わる人員が多く時間をかけすぎていること
- 労働効率を向上させて得られるメリット3つは「人員不足でも対応できる」「新たに投資できる余裕が生まれる」「従業員のワークライフバランスが充実する」こと
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
生産管理システムを製造業の中小企業が自作する方法3つとメリット・デメリット
2022年2月14日
-
業務の見直しをする方法5つと注意点【改善ネタ・アイデア出しの参考になる】
2024年7月9日
-
部分最適とは?メリット3つとデメリットを徹底解説!進めるポイントも
2024年10月3日
-
製造業で品質管理を行うときのポイント4つ【重要性と構成する要素も解説】
2022年2月14日
-
工場のヒヤリハットの原因4つ!対策と改善案のネタ切れに役立つ事例も紹介
2024年4月5日
-
工場にIoTを導入してスマートファクトリー化すると解決できる課題5つ
2022年4月28日
-
在庫管理とは?初心者向けに基礎と効率化する方法6つを解説!エクセルでのやり方も
2023年10月16日
-
工場を効率化する事例10個【製造業の小さな改善アイデア】
2022年4月28日
-
製造業の利益率の目安とは?計算方法5つや向上させる方法を解説!
2024年10月3日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年6月30日
産業用ロボットとは?サービスロボットとの違いや種類、導入するメリットを解説
-
2025年6月30日
工場の省人化に取り組むメリットを解説!具体的なステップと事例をご紹介
-
2025年6月30日
【産業用ロボット】主要メーカーの市場シェアはどれぐらい?市場規模などわかりやすく解説
-
2025年5月28日
事例から学ぶ工場の安全対策!製造業の労災件数も紹介
-
2025年5月28日
ベンダーコントロールとは?定義やToDoを解説
-
2025年5月28日
外部コンサルタントとは?内部との違いやメリット・デメリット
-
2025年4月25日
勘と経験に頼らないモノづくりとは?製造業10社のデータ活用事例を紹介
-
2025年4月25日
工程設計とは?フロー、重要さを解説【事例あり】
-
2025年4月25日
製造業の工程管理、うまくいかない?原因と解決策を解説
-
2025年3月24日
工程分析とは?使われる記号や手法、改善ポイントを解説