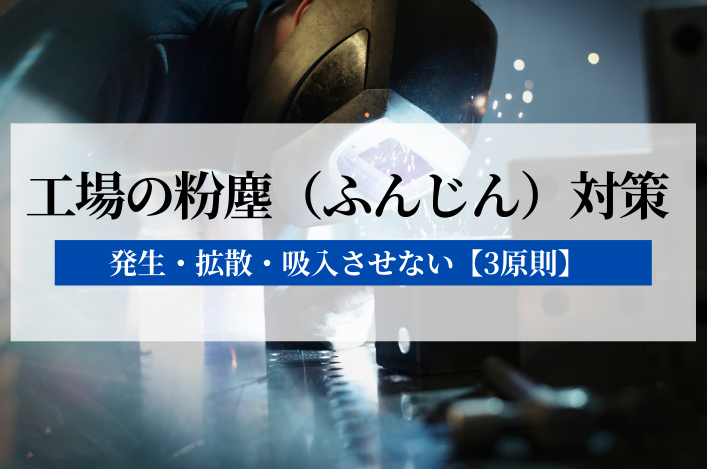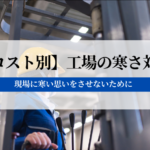「生産性」の使い方は?低くなる原因3つと対策を徹底解説!

「生産性」という用語の使い方は、シチュエーションによって変わってきます。製造業の企業において生産性は、特に重要な意味を持つ用語です。実際に製造業の現場でよく使われる用語ですが、正しい意味を理解できていない人も少なくありません。正しい意味を理解することではじめて、生産性を高めていくことの理解も深まります。
今回は、「生産性」という用語の使い方を解説します。生産性が低くなる原因3つと、高めるための対策も初心者向けにわかりやすく紹介するため、ご参考にしてみてください。
コンテンツ
「生産性」の使い方
「生産性」とは、生産活動に対しての成果を数値化したものです。企業が大きな利益を得るためには、少ない資源の投資で、多くの成果をあげる必要があります。
そのため製造業では、少ない労働資源(人や設備など)で、多くの成果(生産物)を生み出せるかどうかが、企業存続に直結するほど重要な要素になります。
具体的には、従業員1人もしくは労働時間1時間あたりに、どれだけの成果をあげられたかで計算をする、物的生産性という指標を用いるのが一般的です。
物的生産性の計算式
生産量÷従業員数or労働時間
「生産性」という用語は、企業の経営状況を把握したいときや、現場での成果を高めたいときによく使われます。
「生産性」という用語の例文
- 新しい設備の導入は生産性を大きく向上させた
- 休憩の回数を増やすことで従業員の生産性が上がった
- 生産性を高めるために必要な改善案を出す会議を行った など
生産性が低くなる原因3つ
生産性を高めるためには、まず原因や課題を洗い出すことが必要です。生産性が低下することは、ほとんどの場合で明確な原因がありますので、ここではまず生産性が低くなる原因3つを解説します。
長時間労働
長時間労働は、従業員の疲労による、パフォーマンス低下を招きます。1日あたりの生産量は高くなるかもしれませんが、長期目線でみると、疲労の蓄積による従業員の健康面への影響など、考えられるデメリットはたくさんあります。
また長時間労働により残業代など人件費も増えるため、コスト面でも生産性が低くなってしまうことも問題です。そのため短い労働時間で高いパフォーマンスを発揮し、効率的に業務をこなせる環境が理想的です。
マルチタスク
マルチタスクによる業務体制は、一般的には集中力低下を招きやすく、生産性が低くなる傾向にあります。
ただし、製造業においては、
- 単能工…一人で一つの業務を専門的に進めること
- 多能工…一人で複数の業務をマルチタスク的に進めること
という2種類の働き方があり、どちらが適切かは、現場の形態によって変わってきます。マルチタスク自体が生産性の低下を招いているとは言えませんが、従業員の動きをよく見極めて、働き方の調整を行ってみることがとても重要です。
個人決定のしにくさ
日本の企業では、従業員個人の責任領域が狭い特徴があります。
例
- 小さな判断や決定にも複数の上司の許可が必要
- 改善案を出してから経営陣に確認してもらうまで長い時間がかかる
こういった個人決定のしにくさは、業務がスピーディーに進まないため、生産性が低くなる要因の一つです。
生産性を高めるための対策
生産性を低下させている原因がわかったら、改善の対策に取り組みましょう。実際に生産性を高めるためには、経営陣と従業員の双方の協力と理解が大切です。ここでは生産性を高めるための対策を紹介します。
機械との協働を目指す
機械には、設備やロボットだけでなく、ITツールやデジタル化なども含まれます。機械に任せられることは任せて、人の労働時間を短くすることを目指せば、結果的に生産性は高くなります。
大切なのは、機会と人が「協働」していくという意識です。仕事を奪い奪われる関係性ではなく、互いにサポートし合いながら、より高い生産性を求めていく姿勢が重要になります。
従業員が能力を発揮できる人員配置見直し
生産性を高めたいとき、業務削減や設備投資ばかりが注目されがちですが、人員配置の見直しを行うだけでも、大きな成果を発揮することがあります。従業員が能力を最大限発揮できるような、人員配置の見直しを行ってみましょう。
単能工と多能工どちらが適しているかは、企業形態・業務内容・従業員によって変わってきます。どちらにしても、従業員が高いパフォーマンスを発揮できるような、業務形態と人員配置にすることがとても大切です。
個人の責任領域を広くして経営陣とスピーディーな連携を
従業員個人の責任領域を広くして、経営陣とスピーディーな連携を取れるようにすることも、生産性を高めるために大切な試みです。マニュアルの見直しや改訂を行い、判断基準を具体的な数値などで明記すれば、個人が判断や意思決定をスムーズできるようになります。
どうすれば業務全体がスピーディーに進むようになるのか、ムダを省けるのかを考えて、試行錯誤することが大切です。
「生産性」は製造業における重要な指標(まとめ)
「生産性」は誰もが知る慣れ親しんだ用語ですが、正しい意味を理解している人は意外と多くいません。生産性はシチュエーションによって使い方が変わってきますが、特に製造業においては、企業利益にも直結する重要な指標となっています。企業にとって生産性を高めていくことは、必要不可欠な課題です。
生産性が低下することには明確な原因がありますが、言い換えれば、対策も講じやすいということになります。特にこれからの時代は、市場競争やニーズの変化がますます激化していくため、生産性をどれだけ高めていけるかどうかが、企業存続の鍵となるのです。
そのため生産性を低下させているボトルネックを洗い出して、適切な対策を講じていくことが重要になります。
今日のポイント
- 「生産性」とは生産活動に対しての成果を数値化したもの
- 「生産性」という用語は企業の経営状況を把握したいときや現場での成果を高めたいときによく使われる
- 生産性が低くなる原因3つは「長時間労働」「マルチタスク」「個人決定のしにくさ」
- 生産性を高めるための対策は機械との協働を目指したり、従業員が能力を発揮できる人員配置見直しを行ったり個人の責任領域を広くして経営陣とスピーディーな連携をすること
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
2025年9月29日
-
製造業の生産管理システムの選び方|成功させるポイントもご解説
2021年12月13日
-
業務改善の事例7個【進めるときの注意点や気づきの重要性】
2022年9月26日
-
業務改善の方法を6ステップでご紹介|具体例やフレームワークも
2022年2月7日
-
製造業における教育計画を立案するときの手順6ステップ!重要性と具体例
2024年9月2日
-
工場にIoTを導入してスマートファクトリー化すると解決できる課題5つ
2022年4月28日
-
生産管理とは?7つの業務内容と向いている人の特徴
2022年3月3日
-
工程能力とは?基礎や工程能力指数の計算式を5つのステップでご解説!
2022年6月15日
-
工程管理システム導入で期待できる2つのこと|工程管理の基本と主な機能
2022年1月17日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2026年1月29日
工場の寒さ対策をコスト別に紹介!現場に寒い思いをさせないために
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則