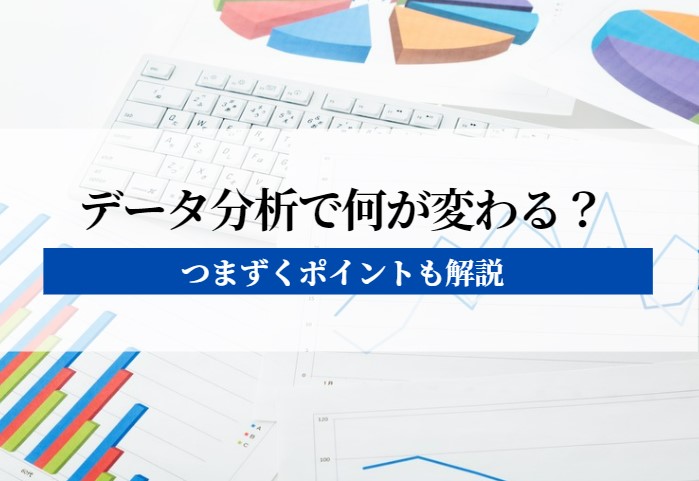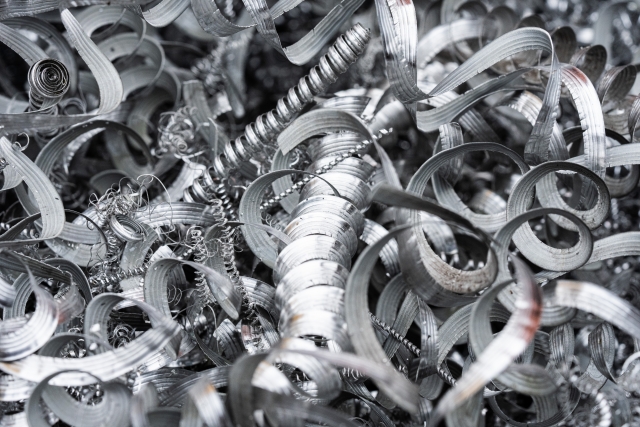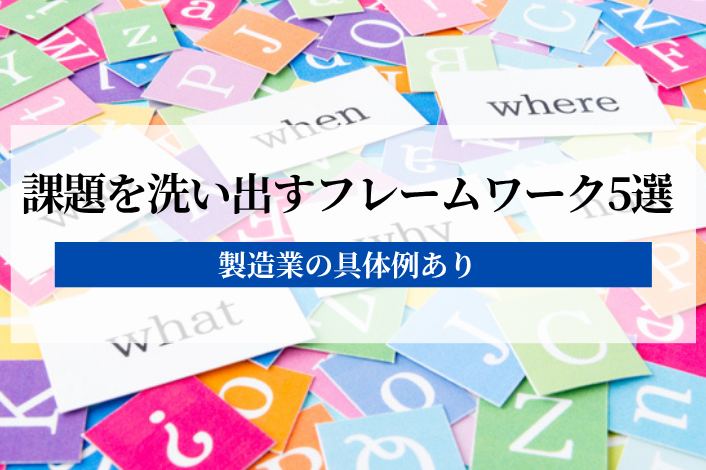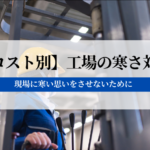製造業の見える化とは?意味と目指すメリット・実行する方法・事例をご紹介

見える化とは、企業の活動における判断材料に必要なものを、「目で見える」状態にすることです。
具体的には、
・定位置を決める
・正常と異常を明確にする
・計画と実績を文字や数値で形にする
などの試みを行います。問題を顕在化させ、改善活動へつなげやすくするのが目的の管理手法です。
見える化は、元々インダストリアル・エンジニアリング(IE、経営工学)における「目で見る管理」を、トヨタが「見える化」と呼ぶようになって広がりました。現在では製造の現場のみならず、事務や経営など、見える化の対象領域は全社的に広まっています。
この記事では、見える化によるメリットや実行するための、具体的な方法をご紹介します。
見える化を推進するうえでの注意点についても解説するので、ご参考にしてみてください。
見える化の意味
見える化は、目で見える状態にすることがゴールではありません。
顕在化した問題を現場で共有して、改善の取り組みとフィードバックを行い続ける必要があります。
可視化との違い
見える化と似た言葉に、可視化があります。
どちらも、今まで顕在化していなかったミスの原因や、非効率な生産状況などを浮き彫りにする点では同じですが、違うのは目的です。
「見える化」は課題が見えるようになることに重きを置いていますが、「可視化」は見えにくいものを見やすい状態にすることが目的となっています。
見える化は、現場の全員が共有できるように、工夫と改善を行うことまでがセット。可視化は、数字やグラフなどで目に見える状態にした時点で役目を終えます。
つまり、可視化だけで問題解決や業務改善に直結することはなく、その先の一手を打たなければあまり意味がありません。
製造業では、「見える化」と「可視化」の意味と目的を理解した上で、業務改善を推進する必要があります。
見える化を推進するメリット
製造現場において見える化を促進推進すると、今まで見えていなかった現場の3M(「ムリ・」「ムダ・」「ムラ」)が浮き彫りになります。
現場の作業者全員で共有もしやすくなるので、全体での業務改善が現場主体でスムーズに進みめやすくないのがメリットですがあります。
問題や課題がすぐにわかるようになる
見える化が実現すると、問題や課題が発生したとき、すぐに気づき対処できるようになります。
その結果として、
・機械の非稼働
・不良品の生産
・資材発注の遅れ
などの問題やトラブルを避けられるようになり、生産性が向上します。
ムダな業務が浮き彫りになる
業務内容が見える化される事で、今まで顕在化されていなかったムダな業務が発覚します。
不合理だった業務ルールを合理的なルールに置き換えられるので、無駄のない業務プロセスに改善できるのがメリットです。
業務内容が明確になり、業務の属人性がなくなる
見える化を促進すると、ブラックボックスだった工程や、特定の人の暗黙知とされてきた内容が明確になります。
結果、業務負荷の分配や、特定の人に依存した作業を減らせるので、業務の属人性がなくなり生産性向上が見込めます。
自発的な業務改善が行われやすくなる
見える化によって、課題や問題が目に見える状態で共有されると、現場が問題意識を持てるようになります。どこにどのような課題があるかがはっきりするので、自発的な改善促進が行われやすくなるメリットがあります。

見える化の事例
見える化は、業種を問わず多くの企業や現場で導入されています。
製造業での事例をいくつかご紹介します。
生産管理版
生産管理版とは、ラインの生産状況が分かる掲示板のことです。
一般的には、
・生産予定数と実績(差異)
・トラブルの原因
・改善対策
などを、一時間単位で記入できるようにします。
メリットは、計画に対して順調なのか遅れているのかが、リアルタイムで把握できること。遅れている場合は、遅れている原因を明確に共有できることです。
作業員は次の時間にどう動けばいいかを考えながら働けるので、生産性が安定しやすくなります。
あんどん
あんどんとは、生産ラインの異常を作業者や管理者に知らせるための報告システムです。各工程に設置されたあんどんの紐を引くと、ランプが光って異常事態が起こっていることを即時に把握できるようになっています。
一般的なランプの色の意味
・緑…通常運転時に点灯(問題なし)
・黄色…何らかの生産異常が発生しているときに点灯
・赤…ライン停止を要求するほどの緊急事態に点灯
あんどんも、有名なトヨタ生産方式の一つです。異常をすぐに共有するのが難しい、流れ作業の生産ラインに導入すると、大きな効果があります。
ペースメーカー
ペースメーカーとは、ライン作業を一定のペースで行えるよう整えるシステムです。製造業の現場では、生産作業が作業員のペースに委ねられているため、どうしても作業スピードにバラつきが生まれてしまいます。
ムラを見える化して、作業スピードを一定に保てるようにしてくれるのがペースメーカー。
コンベア上にテープを貼って、どこで作業完了をすればいいのか明確にしたり、ランプや音声で作業の遅れを知らせたりします。
中でも、一番効果的なのは「強制移動」によるペースメーカーの導入です。
作業場に自動で動くコンベアを導入して、一定の速度で流れるように設定すれば、作業者はペースに合わせて作業完了できます。
定位置管理
製造業の現場でムダなことの一つとして、ものを探す時間があります。ムダな時間をなくすためには、あらゆるものの定位置管理を徹底することです。
大切なのは、誰が見てもそこに置くと分かるように、定位置を明確にすること。テープで置く場所の枠を作ったり、棚には各部品の名称を書いたラベルを貼ったり、工夫をしましょう。
1個流し
1個流しとは、作業者と作業者の間の仕掛品を一つだけにすることです。
一般的な流れ作業では、一人の作業者が複数の工程を受け持っています。作業者と作業者の間には常に多くの仕掛品がある状態になりますが、それではどうしても作業能率のバランスが悪くなってしまいがちです。
1個流しでは、一つ作ったら次の作業者に渡していくので、仕掛品の在庫が減ってリードタイムが短くなる事がメリット。手持ちもよく見えるようになり、生産工程全体の作業バランスも整います。
拡大写真の掲示
小さな部品や細かい分別の見極め方法などは、拡大写真にして掲示する事がおすすめです。作業者の作業効率化と、ミスを防げるというメリットがあります。
見える化推進の注意点
見える化を促進するときに、誤った方法で進めてしまうと業務改善につながりません。新たにムダな作業を追加していることになり、本末転倒になってしまうことも。正しく見える化を導入するために、注意点をご解説します。
見せる化になっていないか注意する
正常と異常を見分けられるようにできるのが「見える化」ですが、なんでもラベルなどを張り付けて表示する事は、いわゆる「見せる化」です。
見える化のつもりのようで、見せた結果が改善活動につながらないのであれば、意味がありません。また、「見せる化」になってしまうと、情報量が多くなりすぎてしまうため、現場の混乱を招くことも。
見える化のアイディアを導入するときは、本当にその内容が改善活動につながるのか、しっかり考えながら取り入れるのが大切です。
見える化は製造業において大きな成長につながる(まとめ)
見える化の目的は、現場の問題を顕在化させ、改善活動へつなげやすくすること。トヨタ生産方式とも呼ばれていますが、製造業だけでなく多くの業種で活用されています。
見える化を促進するメリットは、現場の3M(ムリ・ムダ・ムラ)が浮き彫りになり、業務の属人性をなくしたり自発的な業務改善を促したりできることです。
具体的な見える化の事例は、生産管理版の設置や定位置管理の徹底などたくさんあります。ただし、気をつけたいのは「見える化」が「見せる化」になっていないかということ。
何でも数値化して掲示したりラベルを貼ったりするのは、「見せる化」で業務改善に直結しないので、却って新たなムダを生んでしまいます。
見える化の目的である、業務改善と生産性の向上につながるかを考えながら、自社に合った事例を導入するのが大切です。
今日のポイント
1.見える化と可視化は目的が違う
2.見える化のメリットは作業や工程の課題が明確になり業務改善につながること
3.見える化の事例は多く製造業の現場で導入がしやすい
4.見える化のつもりが「「見せる化」になっていないか、注意しながら推進する必要がある
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
QC7つ道具を初心者向けに解説!覚え方や使い方を5ステップで紹介
2022年7月4日
-
データ分析で製造業の何が変わる?つまずくポイントも解説
2025年3月24日
-
7つのムダを初心者向けに徹底解説|それぞれの対処法や改善事例も紹介
2024年4月5日
-
作業性を向上できる取り組み4つ|製造業における成功事例も紹介
2022年11月28日
-
作業の効率化が進まない理由5つ!製造業における向上の事例も紹介
2023年9月12日
-
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
2025年10月29日
-
業務管理の基本6つを初心者向けに解説!理由や進め方・役立つツールも紹介
2022年8月30日
-
工場を見える化する目的とメリット4つ!具体的な方法や事例・課題も解説
2022年7月1日
-
在庫管理を見える化する方法3つ|メリットとExcelの活用事例も
2022年4月1日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2026年1月29日
工場の寒さ対策をコスト別に紹介!現場に寒い思いをさせないために
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則