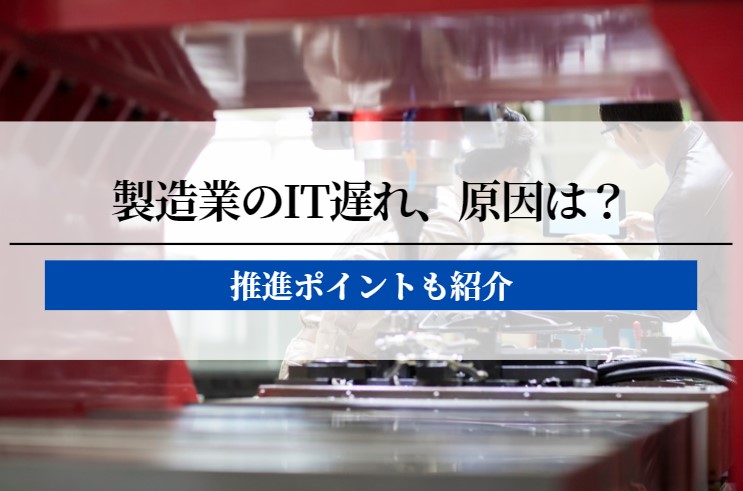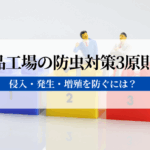工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説

「改善提案を出したいけれど、良いネタが思いつかない」
「当番が回ってきたが、何を書けばいいか分からない」
「どうせ出すなら、現場の役に立ち、評価される提案がしたい」
このような悩みをお持ちではないでしょうか。
改善提案は、現場のムダや危険を見つけ出し、より効率的で安全な職場をつくるための重要な活動です。
しかし、いざ「ネタを探せ」と言われると、なかなか見つからないもの。
本記事では、現場で使える改善提案のネタを5S・安全性・デジタル化・品質・作業効率の5カテゴリに分けて22個ご紹介。それぞれの問題点と改善効果をセットでまとめているので、改善提案書への落とし込みに便利なアイデア集です。
コンテンツ
「5S・整理整頓」の改善提案ネタ5選
1. 使った工具を戻す「定位置ラベル」を貼る
【問題点】
・工具を使った後、戻す位置が決まっていないと「どこに戻せばいいか分からない」「適当に置く」事態が起きる
・結果、次に使う人が探し回ることになり、探す時間がムダにかかってしまう
・工具が紛失したり、私物化されてしまう恐れもある
【改善効果】
・各工具の置き場所に「名前」や「型番」「使用者」などのラベルを貼ることで、誰が見ても一発で分かる状態にできる
・探す手間がゼロになり、戻し忘れも防止
・在庫や破損にも気づきやすくなる
・結果として、作業効率アップ+管理コスト削減の両方につながる
2. 使用頻度ごとに収納場所を見直す(毎日使うものは手元に)
【問題点】
・現在、使用頻度に関係なく収納場所が定められている
・毎日使う道具が離れた棚にあったり、週1回しか使わないものが目立つ場所に置かれていたりする
・必要なものを取りに行くたびに歩数や時間が増えて、ムダが積み重なる
【改善効果】
・使用頻度の高い順に、手元・近距離・遠距離の3層で置き場所を見直す
・移動時間や取り出しのストレスを削減できる
・作業動線もシンプルになるため、疲労軽減やケガ防止効果も期待できる
・結果的に、現場の動き方のロスが削減できる
3. 床に作業エリアや動線のラインを表示
【問題点】
・「作業エリア」「通路」「立入禁止ゾーン」などが曖昧だと、物の置き場が乱雑になったり、通行の邪魔になったりする
・人やフォークリフトの接触事故のリスクも高まる
【改善効果】
・色分けした床ラインでエリアや通路を「見える化」する
・誰でも「ここには置かない/通ってはいけない」が分かるようになる
・動線の最適化+安全性の向上+整頓の維持が一気に実現できる
4. 共有備品の返却期限をルール化する
【問題点】
・「借りたらそのまま」が続くと、使いたいときに共有備品が見つからない
・誰が持っているかも分からないといった状態が頻発する
【改善効果】
・「返却は当日中」「借りるときに記名」などルールを設定する
・備品の所在が明確になり、借りっぱなしや紛失トラブルが減る
・備品管理担当者のストレスも軽減される
5. 使わない工具を思い切って撤去する
【問題点】
・めったに使わない工具や部品が、手の届く位置や見える場所に置かれている
・そのため、よく使う道具が取り出しづらい
・どれが必要でどれが不要かの判断がつきにくい
・棚が乱雑になり、探す時間が増える
【改善効果】
・定期的に工具や備品を見直し、「3ヶ月使ってないものは一旦保管庫へ」といったルールで整理する
・本当に必要なモノだけが残り、探す時間が激減
・使いやすい現場になることで、作業効率・集中力が上がる
「安全性」の改善提案ネタ5選
1. 角のある棚にクッション材を貼る
【問題点】
・通路や作業動線にある棚の角がむき出しのままだと、体をぶつけてケガをする
・運搬中に製品や部品を傷つけてしまうリスクもある
・特に、狭い通路や後ろ向きの作業中は見えづらいため危険
【改善効果】
・ゴムやウレタンのクッション材を貼ることで、接触時の衝撃を吸収してケガを防げる
・物損リスクも下げられる
・小コストで安全性が高まる、コストパフォーマンスの良い改善案
2. 高所作業前に点検リストを導入
【問題点】
・脚立や高所作業台を使う作業では、以下のような危険がある
・器具の破損や不具合に気づかず使ってしまう
・手順が曖昧なまま作業し、バランスを崩す
【改善効果】
・点検リストを作成することで、使用前に器具の状態や足場の安全確認を習慣化できる
・作業者の安全意識が高まる
・「うっかり」を防ぎ、転落・落下事故のリスクを予防できる
3. 指挟み注意の場所にイラストを掲示
【問題点】
・プレス機やコンベア、可動部のある棚など、指を挟みやすい場所があるにも関わらず、注意喚起がされていない
・初めて作業する人が操作した際に、知らずにケガをしてしまうリスクがある
【改善効果】
・「イラスト+赤文字」など、視認性の高い注意表示を設ける
・作業者が瞬時に危険を察知できる
・教育コストも下がる(見れば分かる状態)
・事故予防に直結し、特に新入社員に有効
4. フォークリフトの通行ルートを明示
【問題点】
・フォークリフトと人が同じ通路を使っていると、接触事故のリスクが高い
・特に死角や交差点では「急に出てくる」「気づかない」ことが起きやすく、重大事故になりかねない
【改善効果】
・床に「フォークリフト専用通路」「歩行者通路」をラインで分けて示す
・歩行者とフォークリフトがお互いに避けやすくなる
・「危ない場所」が視覚的にわかるようになる
・ルールを守りやすくなり、事故を未然に防止できる
5. 手袋や保護具の着用チェックリストを設置
【問題点】
・現場によっては「慣れ」で保護具をつけない人が出てきてしまう
・不注意でケガをしたり、万が一のときに大きな事故につながるリスクがある
・管理者も「つけていなかった」ということ自体に気づかないケースがある
【改善効果】
・「今日の持ち物チェックリスト」や「保護具着用確認表」を設置してルール化する
・安全意識が自然と高まる
・チェックが可視化されて、管理者も把握しやすい
・ヒューマンエラーを減らし、組織全体の安全文化が育つ
「デジタル化・ペーパーレス化」の改善提案ネタ5選
1. 紙の工程管理表をGoogleスプレッドシートに移行
【問題点】
・紙で管理していると、「記入忘れ」「字が読めない」「データが集まらない」「紛失する」といったトラブルが多発する
・進捗を全員で共有したい場合でも、情報が現場にしかなく、リアルタイムでの状況把握が難しい
【改善効果】
・Googleスプレッドシートに切り替える
・リアルタイムに更新や共有が可能
・誰が何を入力したか履歴が残る
・複数人で同時編集できる
・進捗の可視化と共有スピードが格段にアップし、管理レベルが向上する
2. 勤怠打刻をICカードやスマホに切り替え
【問題点】
・紙の出勤簿やタイムカードは、打刻忘れ・代筆・記録ミスが起きやすい
・集計にも時間と手間がかかる
・月末の勤怠締めが煩雑化しやすい
【改善効果】
・ICカードやスマホアプリで打刻する
・打刻ミスや不正を防げる
・自動でデータ集計できる
・労務管理の正確性が上がり、事務作業も効率化される
・人件費削減にもつながる
3. 備品管理にバーコードまたはQRコードを導入
【問題点】
・備品の出し入れや在庫状況を手書きで管理していると、入力ミスや数量のズレといったヒューマンエラーが発生する
・棚卸しにも時間がかかる
【改善効果】
・バーコードやQRコードを活用して管理する
・スキャンするだけで在庫を更新
・スマートフォンやハンディ端末でも対応できる
・入力作業が楽になり、棚卸し精度やスピードが向上する
4. 日報をチャットツールで提出・共有する
【問題点】
・紙の日報やメールでの提出は、管理者がチェックするのに時間がかかる
・情報が蓄積しにくい
・共有が滞りやすい(見られない)
【改善効果】
・SlackやLINE WORKSなどのチャットツールに投稿ルールを設ける
・日報が自動で蓄積され、時系列で確認できる
・コメントやリアクションで即座にフィードバックが可能
・報告や確認の手間が減り、チーム全体のコミュニケーションがスムーズになる
5. 作業動画をスマホで撮影&マニュアル化
【問題点】
・文字や写真だけのマニュアルには以下のような課題がある
・動きが伝わらない
・読み手の理解度に差が出る
・教育コストが高い
【改善効果】
・スマートフォンで作業動画を撮影し、要所にテロップを加える
・実際の手の動きや順序がそのまま伝わる
・新人でも1人で学習できる
・教育コストを下げつつ、習得スピードと精度が上がる=属人化防止にもつながる
「品質」の改善提案ネタ4選
1. 異物混入防止のためのエアブロー導線見直し
【問題点】
・エアブロー作業を行う際、周囲の作業エリアや製品にゴミやホコリが飛散する
・製品や部品に異物が混入してしまう可能性がある
【改善効果】
・エアブローの向きや作業位置を見直し、隔離スペースや吸引装置を設ける
・異物の飛散が最小限になる
・異物混入リスクを減らし、顧客クレームや再発防止の負担を減少できる
2. 作業ミスが出やすい箇所にポカヨケをつくる
【問題点】
・同じ部品の付け間違いや向きのミスなど、ヒューマンエラーが繰り返されやすい工程がある
・「気をつけよう」だけの対策では限界があり、再発リスクが常に付きまとう
【改善効果】
・ポカヨケ(ヒューマンエラーを防ぐ仕組み)を導入する
・不適合な部品がはまらない構造になる
・ミスが起きても自動で検知して作業を止める
・ヒューマンエラーによる不良品を物理的に防ぐことで再発ゼロを目指す
3. 検査記録をデジタル入力にして記録ミスを削減
【問題点】
・紙ベースの検査記録には、以下のような「アナログ管理の限界」がある
・記入漏れや記載ミスが起きやすい
・読みづらい文字や書き忘れによる確認作業も発生する
・データ集計や再利用がしづらい
【改善効果】
・検査記録をタブレットやPCから直接入力できるようにする
・リアルタイムで入力や共有ができる
・入力ミスのチェック機能で精度向上
・記録の信頼性とトレーサビリティ(追跡可能性)が高まり、品質保証体制も強化される
4. 不良品発生時の「原因分析テンプレ」を作成
【問題点】
・不良が出た際、記録や報告はしても、なぜ起きたかの分析が曖昧
・再発防止策が「その場しのぎ」で終わってしまう
・属人的な対応で情報が残らない
【改善効果】
・「いつ/どこで/誰が/何をして/どうなったか」を記入する分析用テンプレートを作成する
・誰でも抜け漏れなく報告と共有できる
・原因追求や再発防止のスピードが上がる
・再発防止の精度が上がり、品質が安定する現場をつくる基盤になる
「作業効率」の改善提案ネタ3選
1. 作業台の高さを調整して腰痛を軽減
【問題点】
・現場では、多くの作業台が「平均的な身長」に合わせて一律で設置されている
・実際には、作業者の体格によっては「中腰での作業」「腕を上げ続ける姿勢」などが必要になり、腰や肩に負担がかかる
・結果として、疲労の蓄積 → 作業ミスや生産性の低下、果ては労災にもつながるリスクもある
【改善効果】
・作業台の高さを個人または作業内容に応じて調整(昇降台や作業マットを活用)する
・無理のない姿勢が取れる
・作業精度が安定する
・体への負担が軽減される
・結果として、作業効率が向上し、長時間作業でも安定したパフォーマンスが維持できる
2. よくある質問を「Q&Aボード」にまとめる
【問題点】
・どこに道具があるのか、何番の棚に入っているのかなど同じような質問が何度も繰り返され、その都度ベテランが時間を取られてしまう
・質問される側も、答えるのに集中が途切れ、作業効率が落ちる
【改善効果】
・現場に「Q&A掲示ボード」や「よくある質問シート」を作って貼り出す
・聞かれる前に確認できる
・無駄な中断がなくなり、教える側・教わる側の両方にメリットがある
3. 作業手順書をラミネートして作業場に常設
【問題点】
・手順が口頭や紙ベースで配布されていて、すぐに確認できない
・結果、ミスや不安が発生しやすく、ミスのたびに人に聞いたり、戻って確認する非効率がある
【改善効果】
・防水性のあるラミネート加工+見やすい場所への常設
・作業中でもすぐに手順を確認できる
・新人でも自立して作業可能になる
・確認の手間とミスが減り、教育効率・作業品質が上がる
改善提案がネタ切れなときに試したい視点
「面倒くさい」は改善のヒント
日々の業務の中で、誰でも一度はこんな気持ちになるはずです。
・いちいち確認するのが面倒くさい
・毎回この作業、なんでこんなに手間がかかるんだろう
・探すのに時間がかかってイライラする
その不満こそ、改善提案の原石。
「改善しよう」と構えてしまうと思いつかないものですが、「面倒だったこと」「イラッとした瞬間」は思い出しやすいという人も多いはず。仕事中に「不便だな」と感じたら、その場でメモすることで改善のヒントにしましょう。
ベテラン・新人それぞれにヒアリング
改善提案のネタは、自分1人で考えるよりも他の人の視点を借りる方が効率的です。中でもおすすめなのが、ベテランと新人の両方にヒアリングしてみること。ベテランと新人は、同じ現場でも「見えているもの」がまったく違うためです。
ベテランが持っているのは、言語化されていないノウハウ(=暗黙知)。マニュアルにも手順書にも書かれていませんが、現場の精度やスピードに直結しています。ヒアリングでそれを引き出せば、「見える化して新人教育に落とし込む」「ルール化して品質のバラつきを抑える」といった改善が期待できます。
一方で、新人が持っているのは、「慣れてない目線」だからこその気づき。
・なんでこの工程って、こんなに手順が多いんですか?
・工具の置き場って、どこかに一覧ありますか?
こういった疑問には耳を傾けましょう。
「言われてみれば変」「昔からそうだったけど、今ならもっと効率的にできるかも」といったように、現場を見直すチャンスです。
すでに実施済みの改善に「もう一段階」加えられないかを考える
改善提案に行き詰まったとき、多くの人が「新しいアイデアを探そう」とします。
しかし、実は、すでにやった改善の「その後」に、次のネタが隠れていることもあります。
例えば、過去に「紙のチェックリストを導入した」という改善があったとします。「もう改善済みだから終わり」ではなく、以下のように振り返ってみると、より良い改善のアイデアが浮かびます。
★紙にしてからどんな変化があったか?
★逆に、新たな課題は出ていないか?
★チェックリストが使われなくなってきていないか?
★記入漏れがあるなら、もっと確実な方法はないか?
★集計が面倒なら、スマホ入力にできないか?
まとめ
この記事では、現場の改善提案に役立つ22のネタを紹介しました。
ポイントは、「大きな改革」ではなく「小さな不便」を放置しないこと。
・ちょっとしたラベル付け
・収納の見直し
・安全確認のルール化
・紙からデジタルへの切り替え
こうした一つひとつの積み重ねが、作業効率や品質、安全性の底上げにつながります。
もしネタに困ったら、「不便」と感じた瞬間を思い出してみてください。その気づきこそ、次の改善提案のヒントになるはずです。
製造業のDXはあおい技研
株式会社あおい技研は、製造業に特化した業務改善コンサルティングを提供し、製造現場のDX推進をサポートします。80以上の製造現場での診断や改善の経験を活かし、お客様に合ったDX戦略を提案します。
データ分析、業務効率化システムの開発、現場のデジタル化などを通じて、お客様の業務改善と生産性向上を支援します。
製造業のDXについては、あおい技研にご相談ください。
関連記事
-
【産業用ロボット】主要メーカーの市場シェアはどれぐらい?市場規模などわかりやすく解説
2025年6月30日
-
製造業のIT遅れ、原因は?推進ポイントも紹介
2025年1月29日
-
生産管理システムを製造業の中小企業が自作する方法3つとメリット・デメリット
2022年2月14日
-
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
2025年12月16日
-
製造業DXが進まない理由3つ|進めるときのポイント
2024年6月13日
-
業務効率化でシステム導入するメリット3つ!デメリットも掲載
2023年3月20日
-
製造業の仕事はAI導入でなくなる?今後の動きと活用事例6選
2024年3月4日
-
産業用ロボットとは?サービスロボットとの違いや種類、導入するメリットを解説
2025年6月30日
-
工程能力とは?基礎や工程能力指数の計算式を5つのステップでご解説!
2022年6月15日
カテゴリー
- IT化
- QCD
- QCサークル
- コスト削減
- コンサルタント
- スマートファクトリー
- ボトルネック工程
- 中小企業
- 労働生産性
- 合理化
- 品質担保
- 品質管理
- 在庫管理
- 工場IoT
- 工場効率化
- 工程管理
- 工程管理システム
- 投入資源
- 業務効率
- 業務改善
- 生産ライン
- 生産性向上
- 生産管理
- 生産管理システム
- 経費削減
- 製造業
- 製造業 DX
- 製造業IoT
- 見える化
- 設備管理
新着コラム
-
2025年12月16日
コンタミ(コンタミネーション)とは?製造現場でのリスクと対策
-
2025年11月28日
これで通る!改善提案書の書き方をテンプレートと例文で紹介
-
2025年11月28日
QCとQAの違いは責任・時間軸・業務範囲の3点!それぞれ解説
-
2025年11月28日
PQCDSMEとは?QCDとの違いや現場へ落とし込む視点
-
2025年10月29日
QCサークルの進め方とは?基本の「問題解決型」を解説
-
2025年10月29日
工場の改善提案ネタ事例22選!問題点と改善効果もセットで解説
-
2025年10月29日
課題の洗い出しに特化したフレームワーク5選【製造業の例あり】
-
2025年9月29日
KY活動がネタ切れ…マンネリを打破する6つの着眼点
-
2025年9月29日
工場の粉塵(ふんじん)対策は「発生・拡散・吸入させない」の3原則
-
2025年9月29日
食品工場の防虫対策3原則!侵入・発生・増殖を防ぐには?